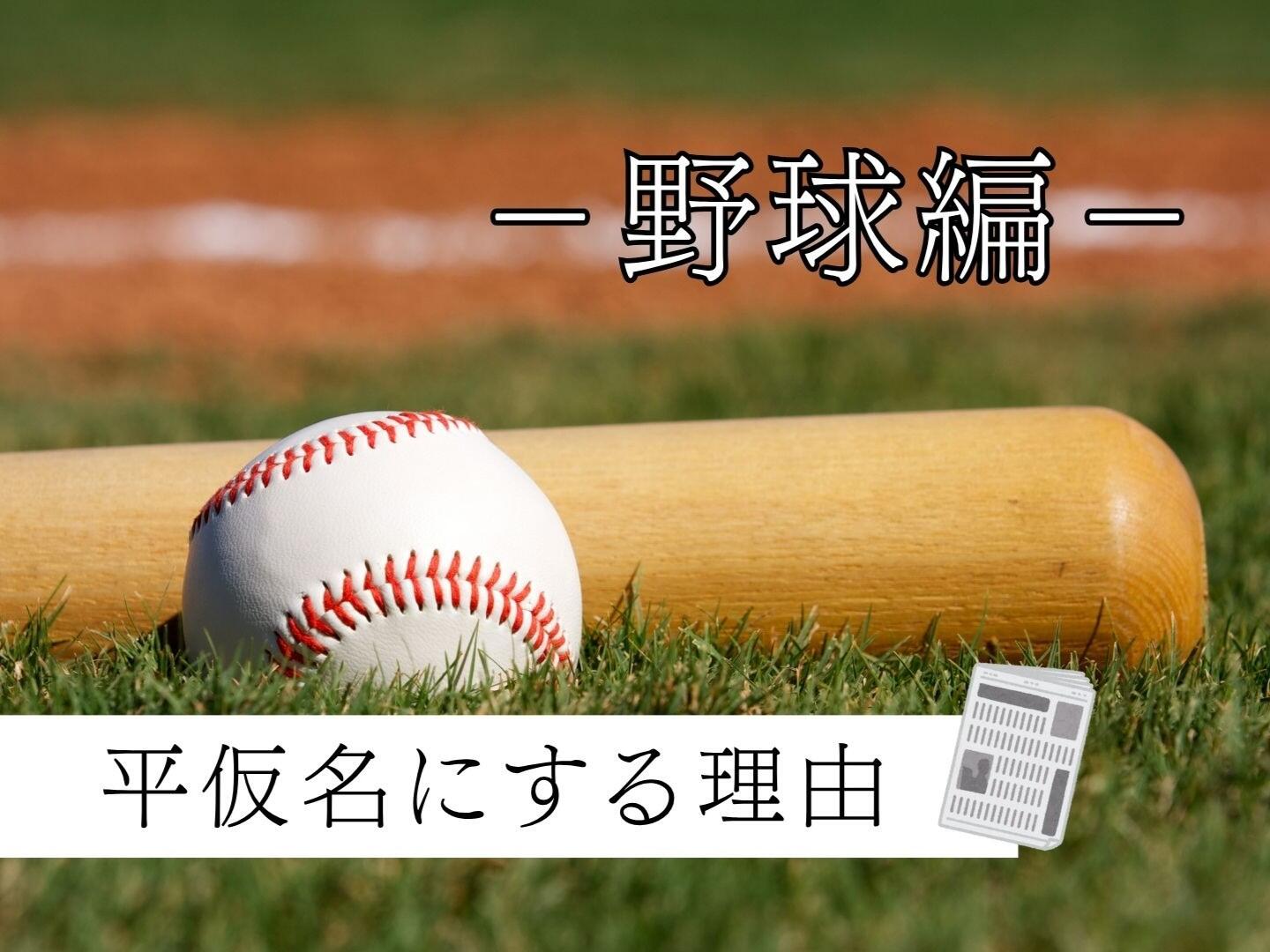単位のはなし

大学生にとってはドキっとする「単位」という言葉。
いえ、今回はそちらではなく、助数詞の「単位」のことです。
私たちは、日常にあふれる数々の「単位」を無意識に使い分けていますが、外国人が「oh my God!!」と嘆いてしまうのが、日本人のものの数え方。
アジア圏では他にも助数詞の存在する言語はありますが、日本語における助数詞はというと・・・
日本語の助数詞は数百あるとも言われており、そもそも私たちもそのすべてを理解しているわけではありません。ただ、「1個」「1頭」「1羽」「1台」「1面」「1玉」「1冊」・・・、と聞けばおおよそどのようなものを指しているのかは瞬時にイメージできます。
また、「1匹」⇒「1本」「1尾」⇒「1切れ」「1枚」⇒「1貫」「1腹」「1粒」(「1パック?」)となると、海で泳ぐ魚が水揚げされ、私たちの食卓にあがるまでの状態変化が、つぶさに想像できますよね。
「a bottle of water」「three cups of coffee」などのように、「a ○○ of ~」「three ○○s of ~」とシンプルに表現する欧米人から見れば、何とも面倒で複雑な日本人のものの数え方。それでもこの面倒さを良しとして私たち日本人は、現代まで脈々とこの言葉の文化を受け継ぎ、日本語ならではの豊かな表現を守ってきました。
例えば、箸を「膳」と数えたり、イカを「杯」と数えたり、うさぎを「羽」と数えたり。いろいろな“イレギュラー”なものも含めて、身の回りのものを改めて数えてみるのもおもしろいかもしれません。
≪参考リンク≫
【コラム:漢字と言葉のおもしろ研究所】 ものの数え方から分かること 中央大学 飯田朝子 教授 「漢検ジャーナルVol.6」(2012.4.2)掲載