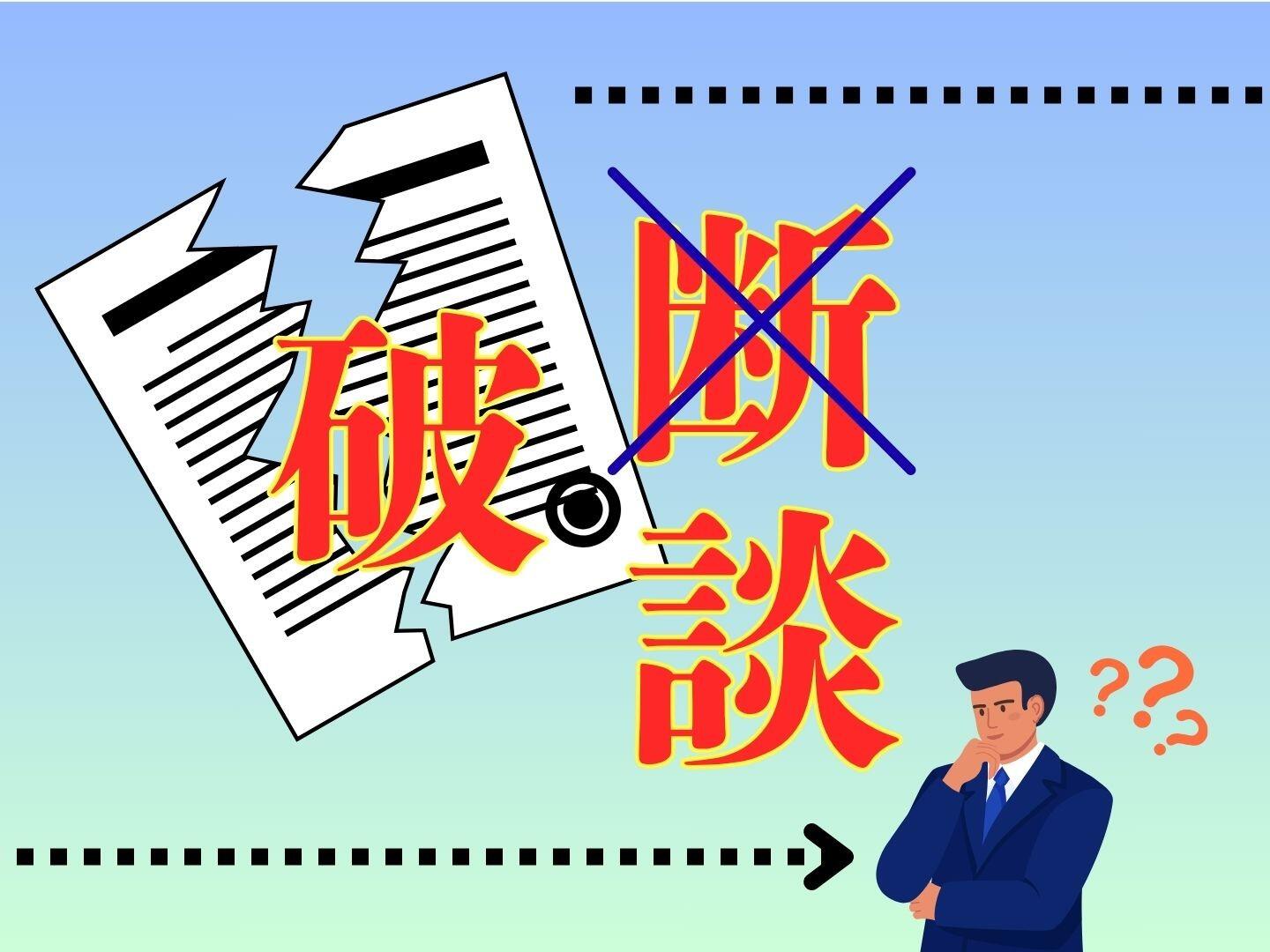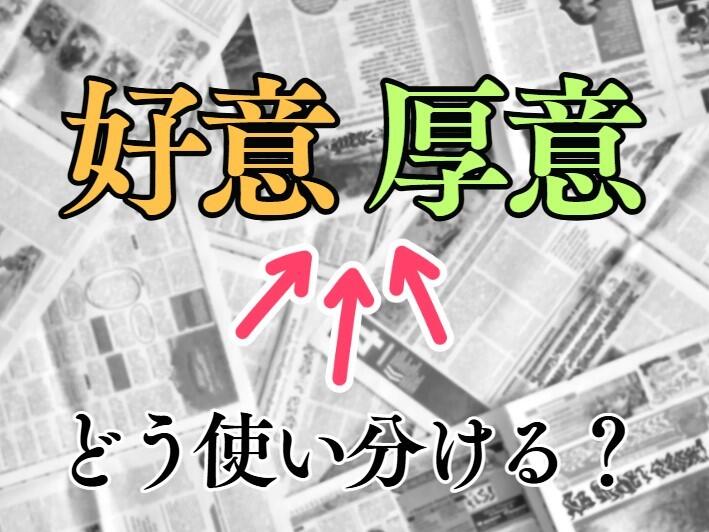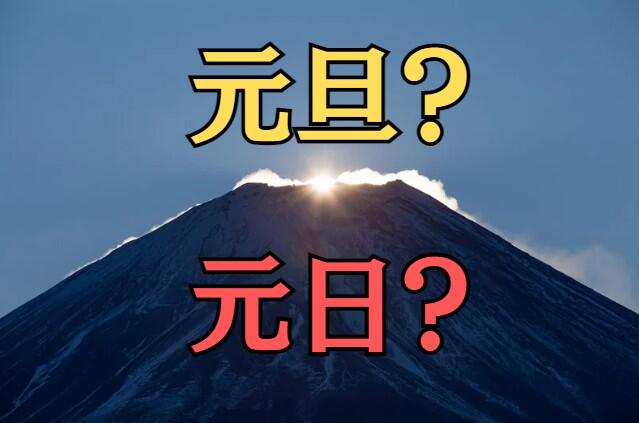新聞漢字あれこれ180 平仮名にする理由・野球編
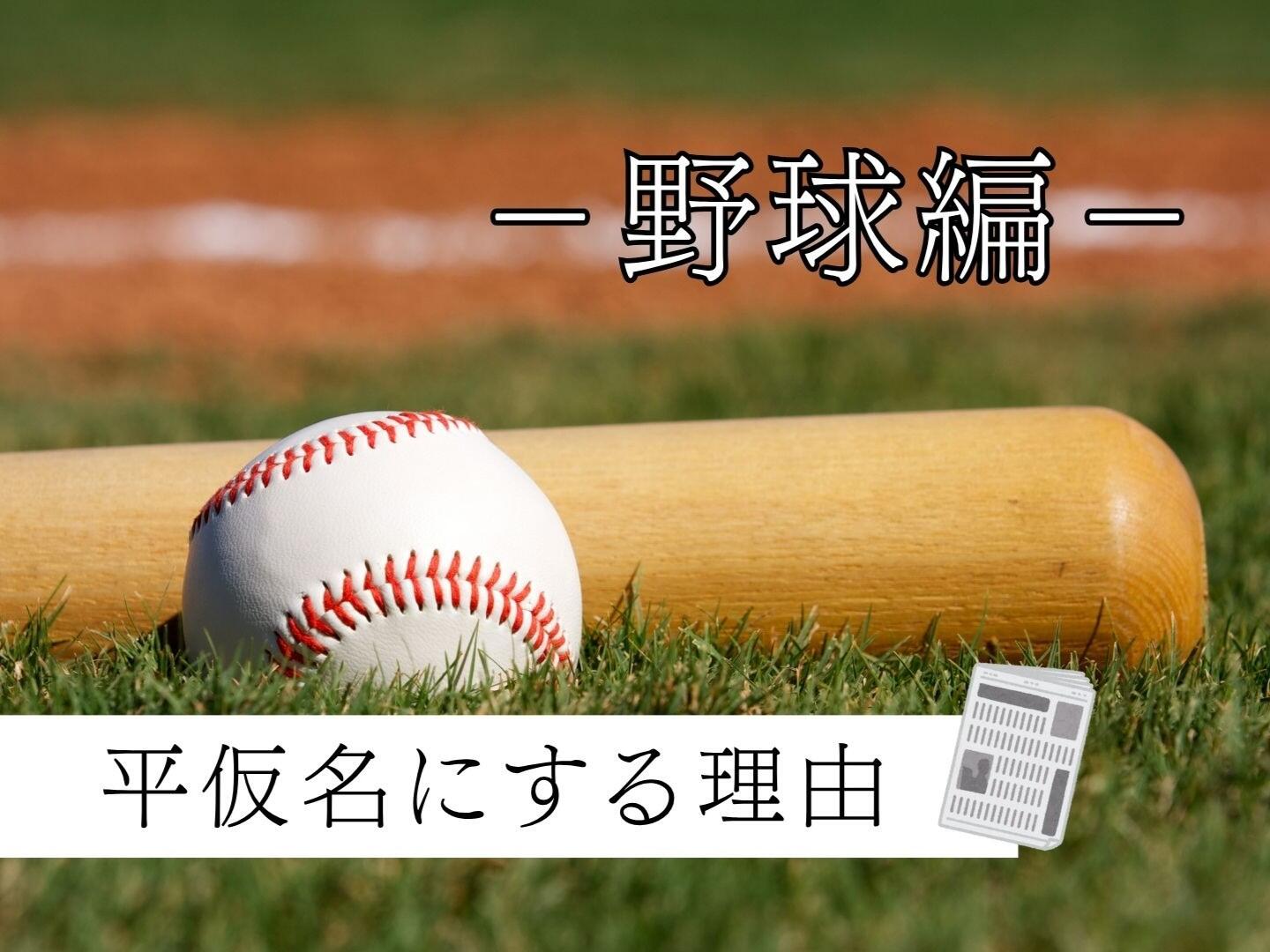
著者:小林肇(日本経済新聞社 用語幹事)
11月も半ばを過ぎ、盛り上がった日米のプロ野球もオフシーズンとなりました。大リーグでは日本人選手らの活躍でドジャースが2年連続でワールドシリーズを制覇したのは記憶に新しいところ。大谷翔平選手の3年連続4度目の最優秀選手(MVP)受賞も決まりました。まだ今季の余韻が残っているうちに、野球記事でよくある漢字と平仮名の使い分けについて見ていくことにしましょう。
走者が返る → 走者がかえる
「三塁走者がホームにかえる」というときに「返る」と書いてくる記事がよくあります。この場合は「かえる」と平仮名書きにするのがルール。得点が入るときは「ランナーが生還した」などと言い、漢字を当てるなら「還る」になるところ、常用漢字表には「還」の読みに、訓の「かえる」はありませんので、平仮名で「かえる」と表記することになります。
毎日新聞のようにスポーツ関係の特殊用語として例外的に「還る」を使っているところはあっても、「返る」とはしません。「返」を使うのは、「戻す」意味で「3点を返す」という場面ではあります。
劣勢を跳ね返す → 劣勢をはね返す
「打線に劣勢を跳ね返す力もなく……」とあれば「跳ね返す」ではなく「はね返す」と書きます。この場合は「はらいのける」意味の「撥」を当てることになり、「撥」が常用漢字ではないため「はね返す」と仮名書きにしています。
もうひとつの「跳」は「はねあがる」意味。打球がフェンスに当たって「はねかえる」ようなときは「跳ね返る」と書きます。
投手を盛り立てる → 投手をもり立てる
攻撃側の好機に、ピンチを迎えた守備側は「野手が投手をもり立てる」ことがあるでしょう。「そばから助けて、いい仕事をさせる」(三省堂現代新国語辞典)意味で、漢字ならば「守り立てる」となります。常用漢字表の「守」の音訓欄に名詞の「もり」はあっても動詞の「もる」がないことから、新聞では「もり立てる」と仮名書きにするわけです。「守り」と書けば「まもり」とも読めてしまい、区別する意味合いもあります。
こうした場面で「盛り立てる」と書いてくるケースがよくあります。それでは「さかんにする」(同)意味になってしまいます。さかんになり盛り上がるのは攻撃側で、守備側ではありません。
ボールを弾く → ボールをはじく
常用漢字表では「弾」に、音の「ダン」と訓の「ひく」「はずむ」「たま」が示されています。訓に「はじく」がないため、打球を飛ばす意味で「バットがボールをはじく」ときは平仮名にします。これによって「ひく」との区別ができます。また、同じ「はじく」でも、「三塁手が打球をはじく」の場合は「ボールを捕り損なってそらす」別の意味になります。
◇
上記の4例はいずれも新聞表記のルールと言ってしまえばそれまでですが、単に機械的に置き換えているわけではありません。漢字の意味の違いや、訓読みの区別をするための工夫だともいえます。連載の第66回でも同様の例をいくつか取り上げています。なぜ平仮名にするのかを考えることも大事なことですね。
次回、新聞漢字あれこれ第181回は12月3日(水)に公開予定です。
≪参考資料≫
『三省堂現代新国語辞典 第七版』三省堂、2024年
『新聞・放送用語担当者完全編集 使える!用字用語辞典 第2版』三省堂、2025年
『新聞用語集 2022年版』日本新聞協会、2022年
『2025年版 毎日新聞用語集』毎日新聞社、2025年
≪参考リンク≫
「日経校閲X」 はこちら
≪おすすめ記事≫
新聞漢字あれこれ66 「ちりばめる」 平仮名の理由 はこちら
新聞漢字あれこれ136 政権をどう「たてなおす」のか はこちら
≪著者紹介≫
小林肇(こばやし・はじめ)
日本経済新聞社 用語幹事
1966年東京都生まれ。1990年、校閲記者として日本経済新聞社に入社。2019年から現職。日本新聞協会新聞用語懇談会委員。漢検漢字教育サポーター。漢字教育士。 専修大学協力講座講師。
著書に『新聞・放送用語担当者完全編集 使える!用字用語辞典 第2版』(共編著、三省堂)、『方言漢字事典』(項目執筆、研究社)、『謎だらけの日本語』『日本語ふしぎ探検』(共著、日経プレミアシリーズ)、『文章と文体』(共著、朝倉書店)、『日本語大事典』(項目執筆、朝倉書店)、『大辞林第四版』(編集協力、三省堂)などがある。2019年9月から三省堂辞書ウェブサイトで『ニュースを読む 新四字熟語辞典』を連載。