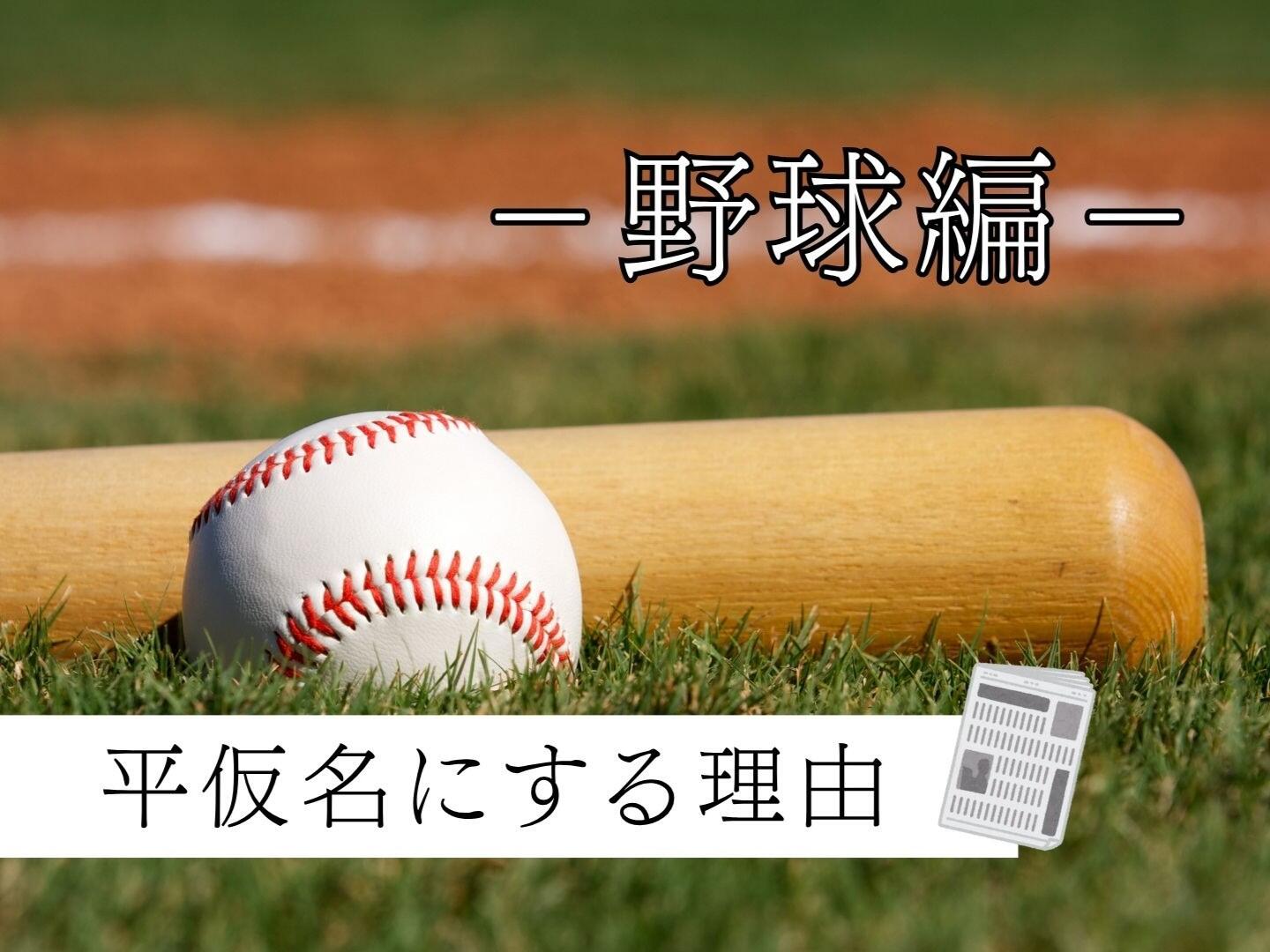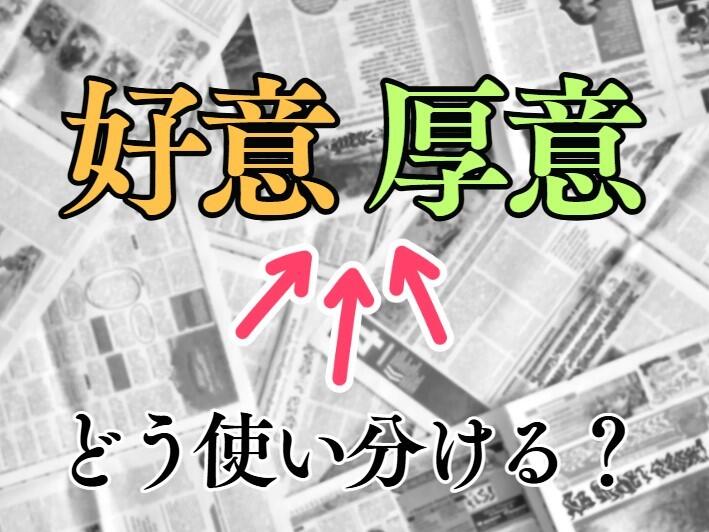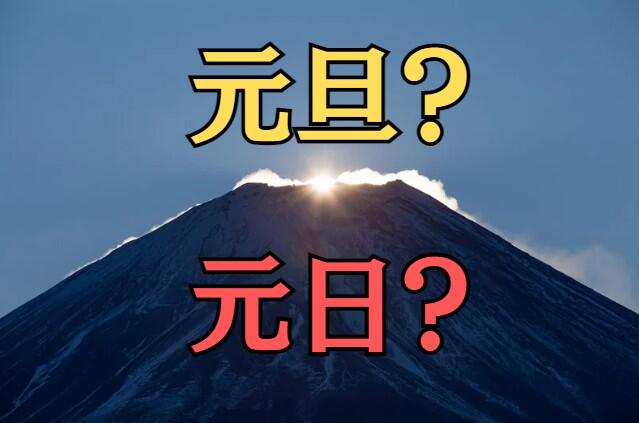新聞漢字あれこれ177 「破談」を「破断」に間違うのは…
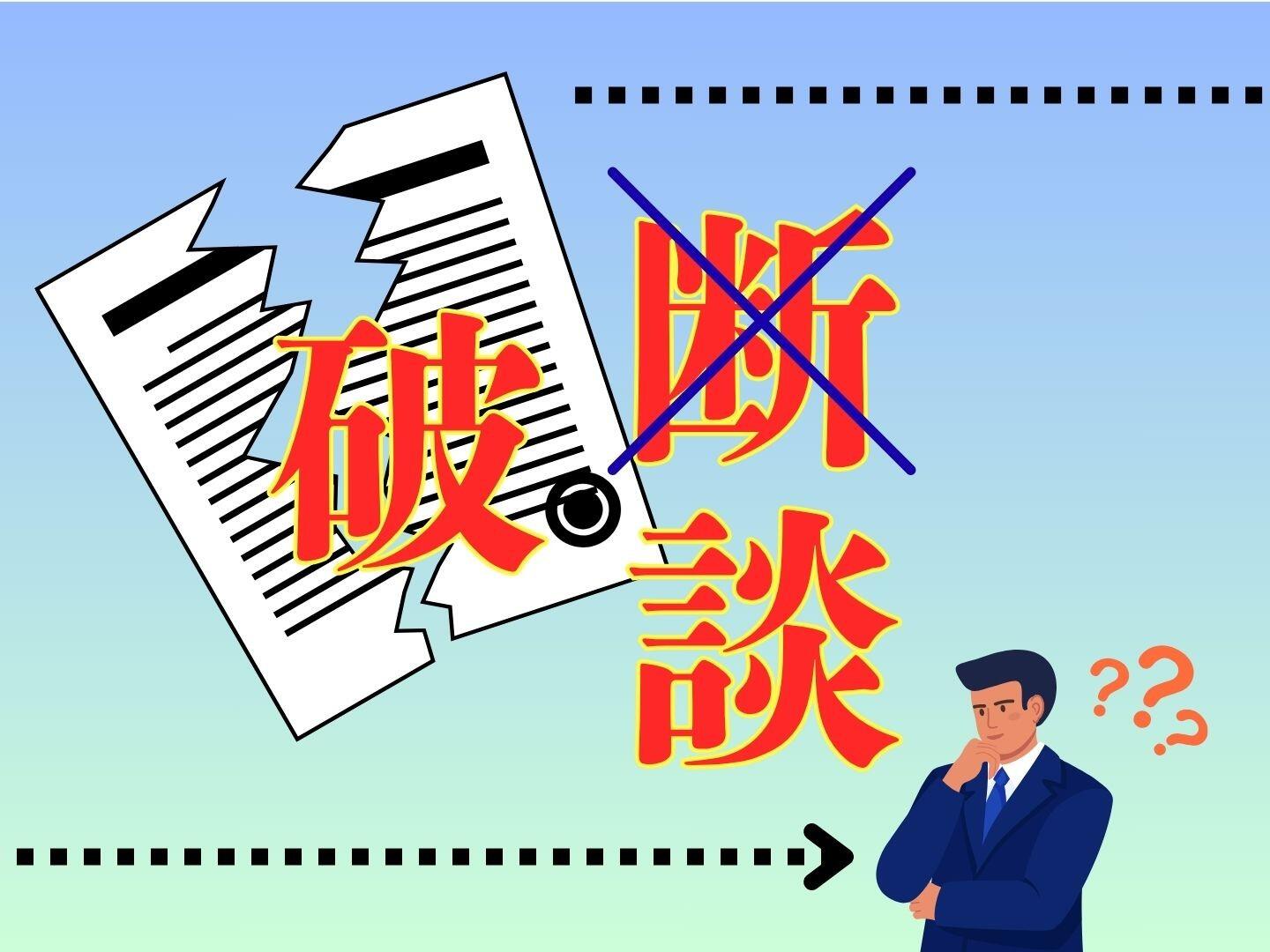
著者:小林肇(日本経済新聞社 用語幹事)
「A社はB社との経営統合が8月に破断して以来、初めての他社との提携になる」。例文のように、意味的に「破談」とすべきところを「破断」に間違う事例が少なくありません。読めばすぐに区別できるはずのものですが、単なる変換ミスというわけではないようです。
【破断】[名・自サ変]金属などの構造物が破壊されて、いくつかの部分に分離すること。「トラックのハブが―する」
【破談】[名]一度取り決めた約束などを取り消すこと。特に、縁談を取り消すこと。「―になる」
破断と破談。『明鏡国語辞典』の第3版では上記のように示されています。意味が大きく異なるので、一読すればすぐに分かるような誤りではあるものの、校閲現場では意外によく目にするものです。記事の執筆段階でなぜ間違うのか。
辞典の品詞・活用欄を見てください。破断と破談はともに名詞ではありますが、破断には「自サ変」とあり、サ変動詞でもあると示されています。破談はサ変動詞ではないため、記者端末では「破断する」とはなっても、「破談する」とは一括変換できません。必要であれば「破談」と「する」を別々に入力することになります。
このような破談を動詞として使う事例が増えつつあります。記事データベース「日経テレコン」で日本経済新聞の記事を検索したところ、1980、1990年代に動詞としての使われ方が少しずつ見られ、2000年代になって多く見られるようになりました。これは他紙でもおおむね同じような傾向です。言葉の使い方の変化が、誤字の発生にも影響していると考えてよいのかもしれません。
例文のような場合、校閲の現場としては「破断して」の「破断」を「破談」に直すのは当然のことですが、増加傾向とはいえ「破談して」をそのままにはせず「破談になって」と修正することも必要になってきます。品詞情報が載っている主な国語辞典16種を見ても「破談」を動詞としているものはまだ一冊もありません。校閲記者は同音異義語に注意を払うのはもちろんのこと、品詞や活用に目配りすることも大事な役割のひとつなのです。

次回、新聞漢字あれこれ第178回は10月15日(水)に公開予定です。
≪参考資料≫
各種国語辞典(表を参照)
≪参考リンク≫
「日経校閲X」 はこちら
≪おすすめ記事≫
新聞漢字あれこれ142 「追及・追求・追究」の使い分け はこちら
新聞漢字あれこれ125 学び直しでテンシン支援 はこちら
≪著者紹介≫
小林肇(こばやし・はじめ)
日本経済新聞社 用語幹事
1966年東京都生まれ。1990年、校閲記者として日本経済新聞社に入社。2019年から現職。日本新聞協会新聞用語懇談会委員。漢検漢字教育サポーター。漢字教育士。 専修大学協力講座講師。
著書に『新聞・放送用語担当者完全編集 使える!用字用語辞典 第2版』(共編著、三省堂)、『マスコミ用語担当者がつくった 使える! 用字用語辞典』(共著、三省堂)、『方言漢字事典』(項目執筆、研究社)、『謎だらけの日本語』『日本語ふしぎ探検』(共著、日経プレミアシリーズ)、『文章と文体』(共著、朝倉書店)、『日本語大事典』(項目執筆、朝倉書店)、『大辞林第四版』(編集協力、三省堂)などがある。2019年9月から三省堂辞書ウェブサイトで『ニュースを読む 新四字熟語辞典』を連載。