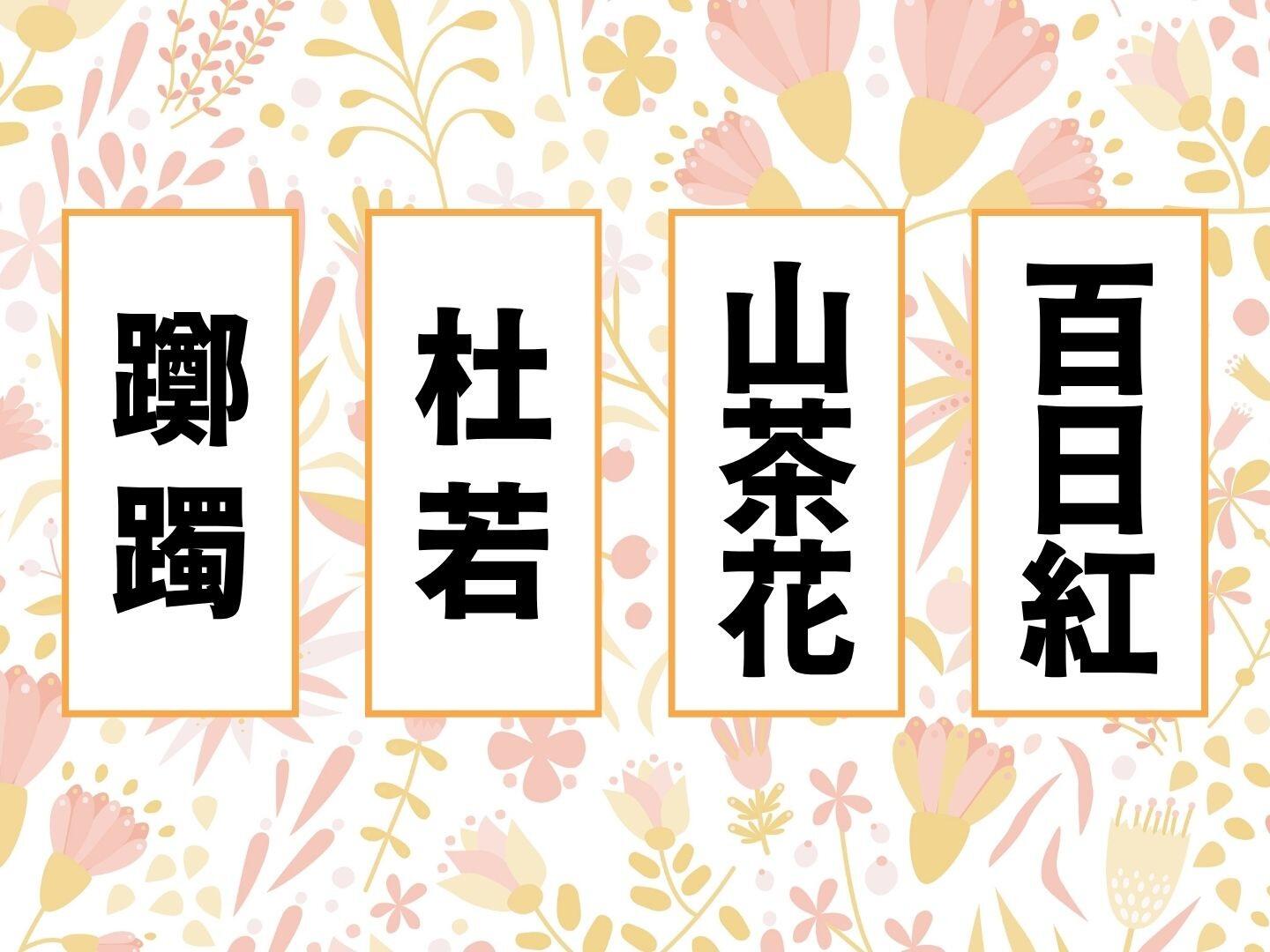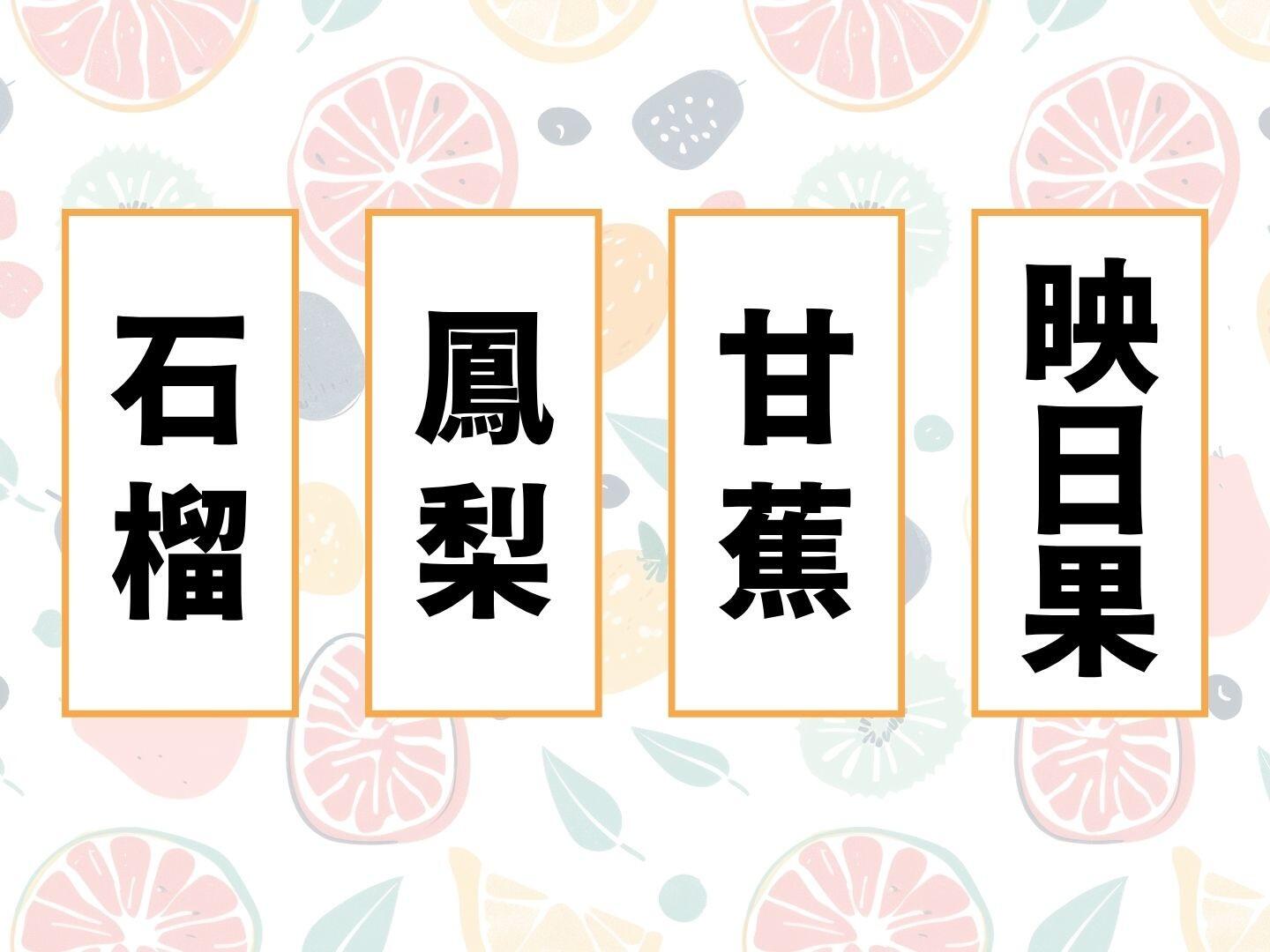難読漢字
アルファベットの“Y”に見えるこの文字は何者?
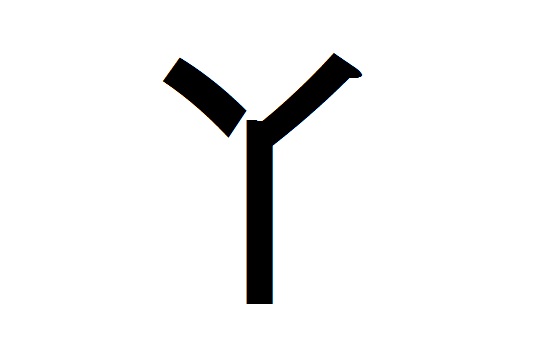
上に示した、ふたまたに分かれた形。これ、何に見えますか?
アルファベットのY(ワイ)?
地図記号の「消防署」もこんなマークだったような…。
アルファベットなのか記号なのか、はたまた一体何者??
この「丫」、実は漢字なのです。
音読みで「ア」、訓読みで「あげまき」と読みます。
意味は、
1、ふたまた。木のまた。
2、あげまき。つのがみ。昔の子どもの髪形。
です。
「あげまき」とは右の図のような古代人の髪型を指します。たしかに、この髪型を表すと「丫」のようになります…かね。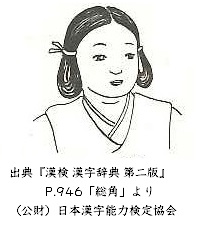
「あげまき」という訓を持つ漢字はほかにも「丱」(音読みでは「カン」・「ケン」)がありますが、こちらも髪型を表したような形です。
さらに、「あげまき」は「総角」もしくは「揚巻」とも書きます。この髪形にするのが主に少年だったことから、子供の頃を指して「総角(そうかく)」とも言うようです。
また、「あげまき結び」という、兜や調度品などに用いられる紐の結び方もありますが、髪型から転じて3つの輪を作って垂らす結び方を指すようになったそうです。
そういえば、『源氏物語』の中にも「総角」という巻名がありますね。
漢検協会がWeb上で公開している漢字検索サイト「漢字ペディア」では、索引の一番初めに来るのが「丫」であり、その形状が珍しいからか閲覧数が常に上位になっています。
「丫」は、現代の日本の中で用いることはあまりない漢字ですが、よかったらトリビアの1つとして覚えてみてください。