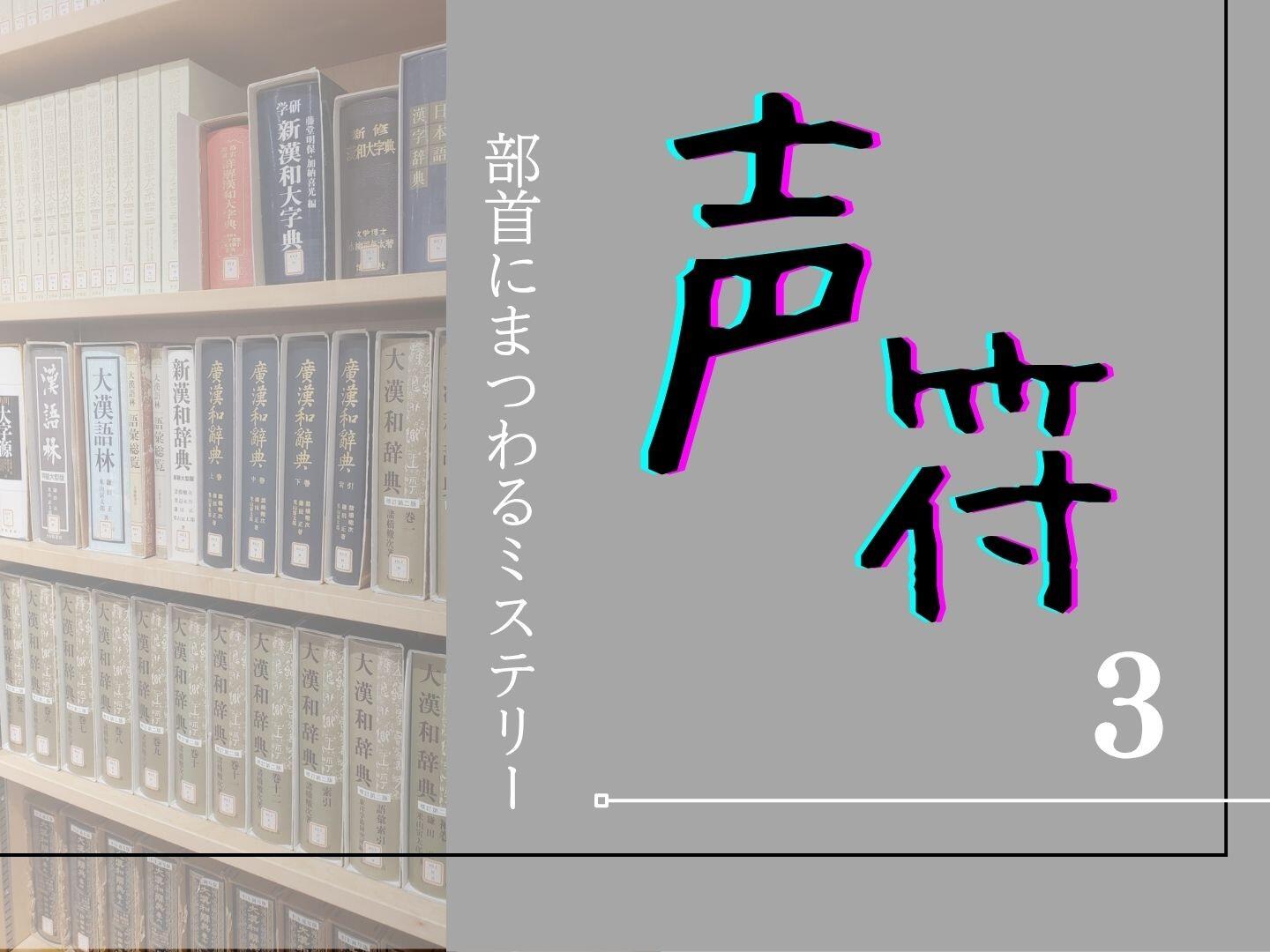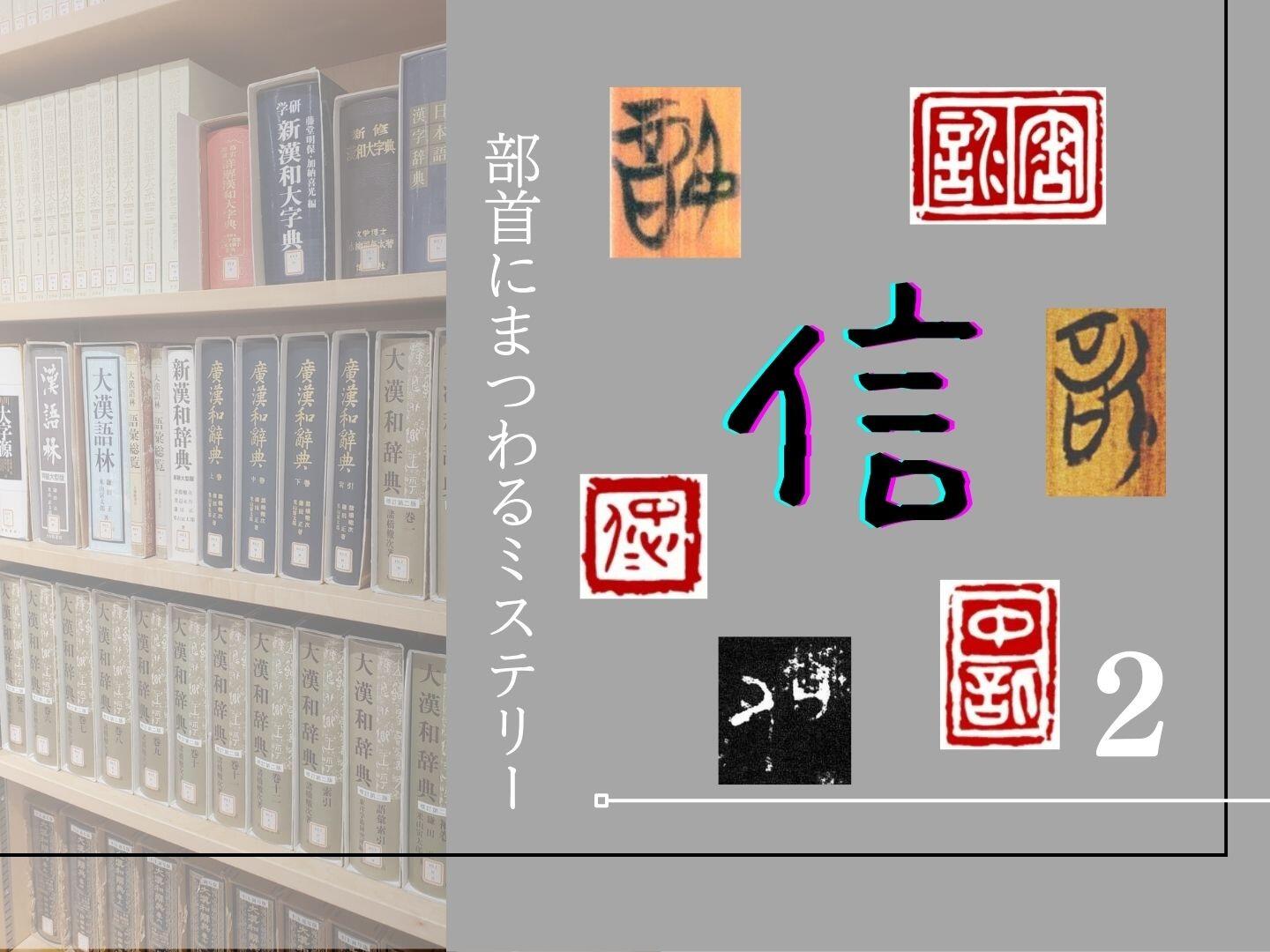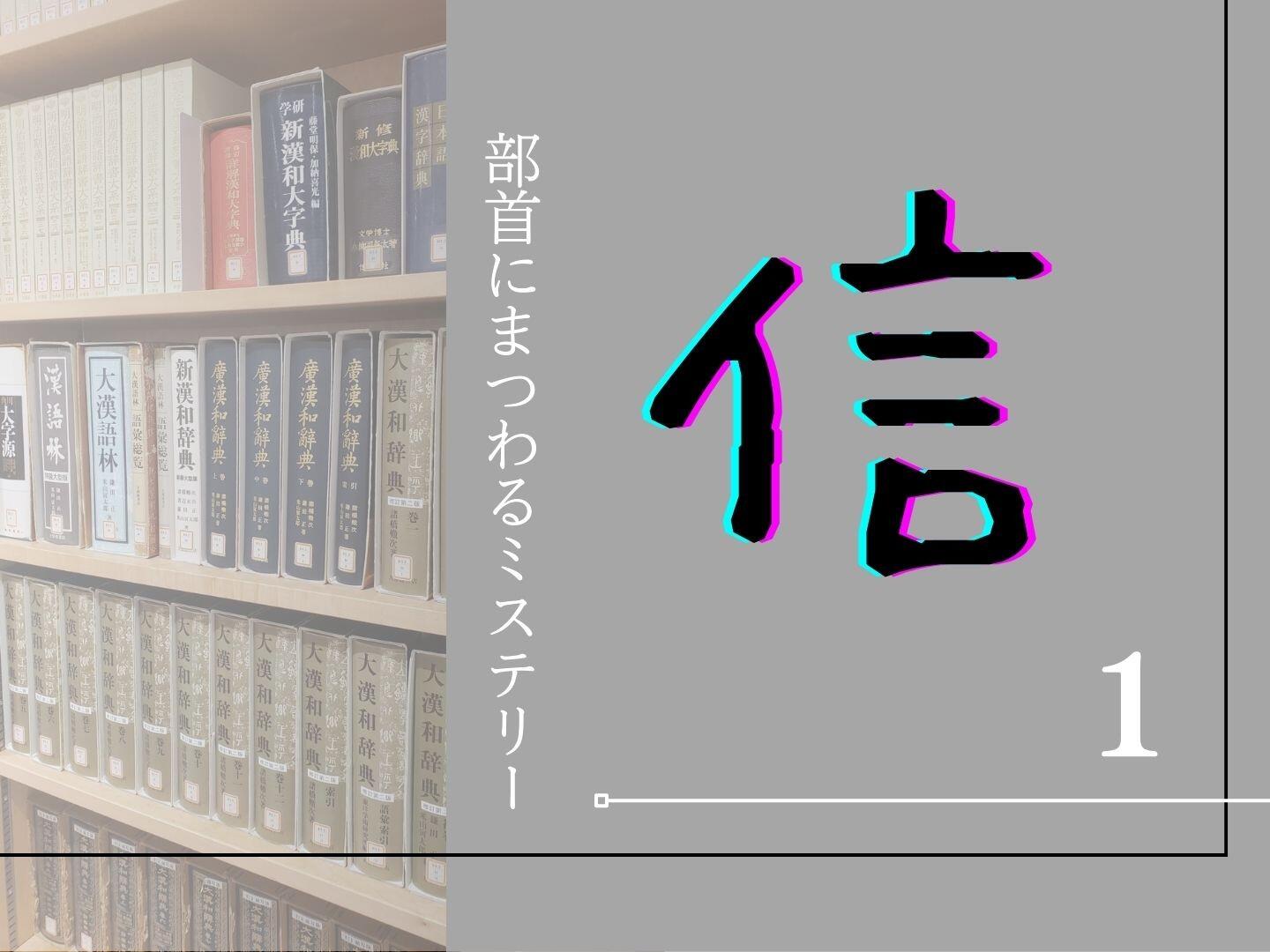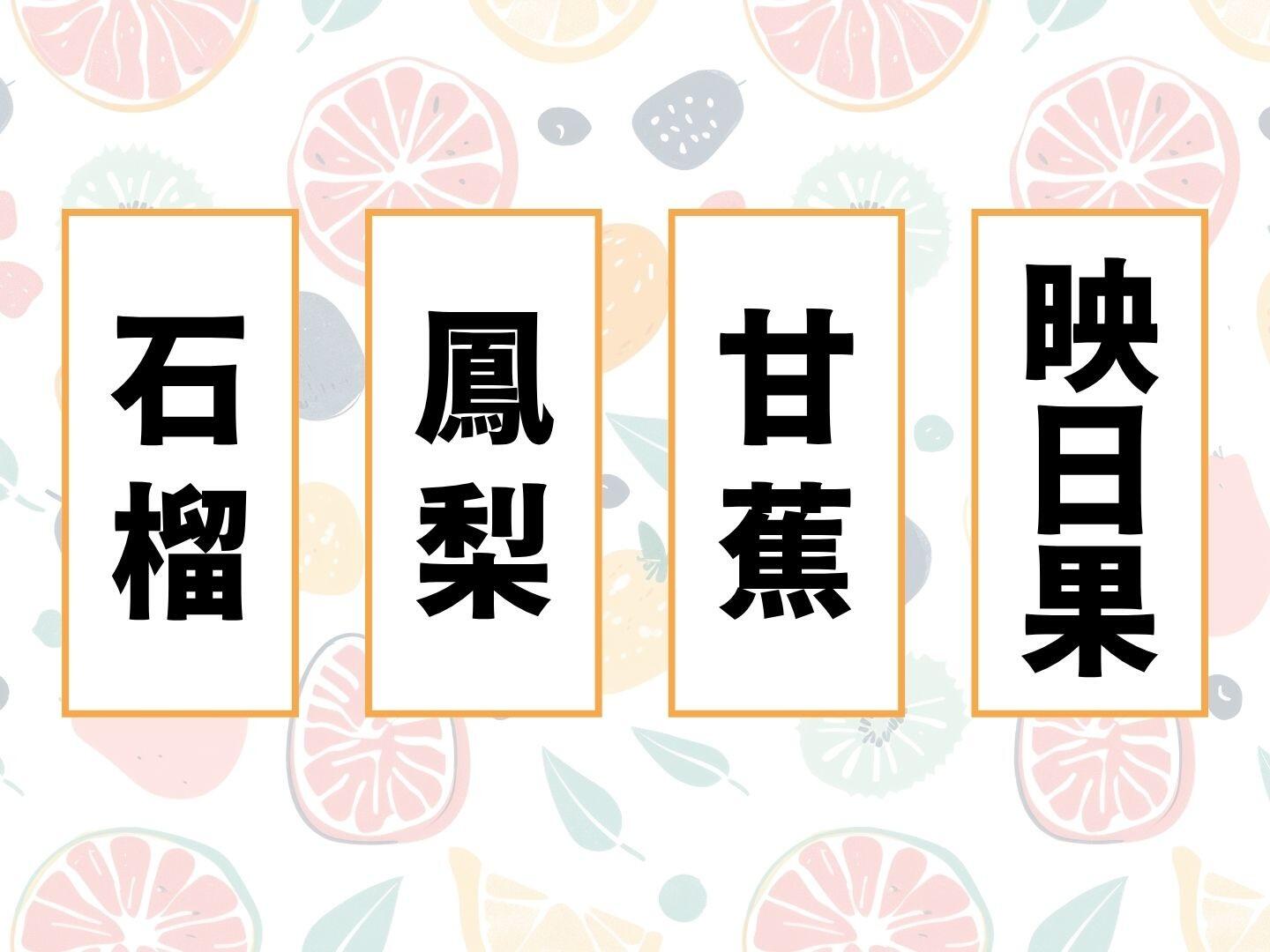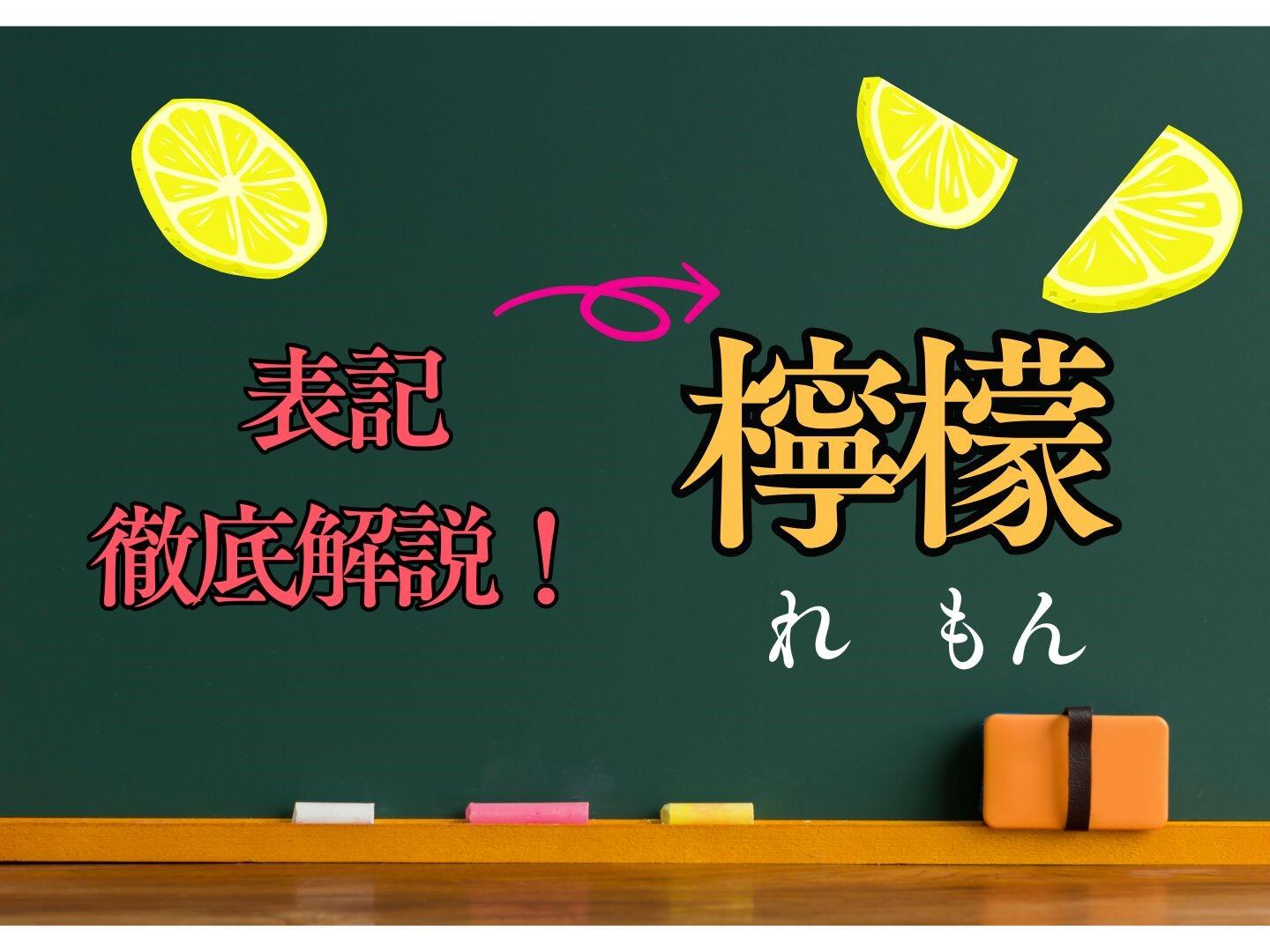不亀手之薬【変わった読み方の常用漢字熟語を解説 1】
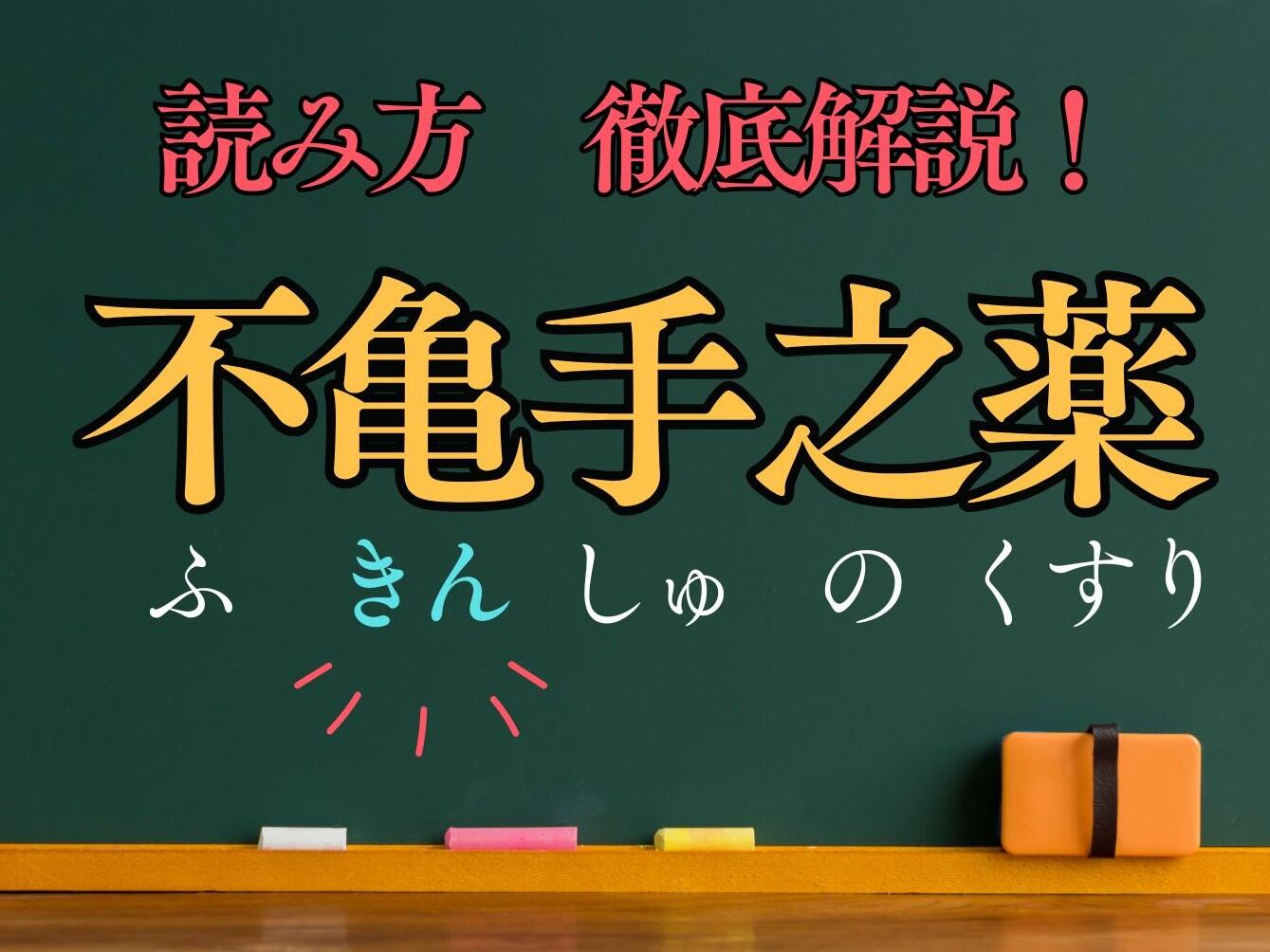
著者:田中郁也(漢字文化研究所主任研究員)
漢検最難関の1級では、約6,000字の対象漢字の中からさまざまな熟語が出題されます。中には、常用漢字でありながら予想もしない読み方やその言葉の意味を知らないと答えられない問題も。
このコラムでは、興味深い熟語を漢字文化研究所の専門家が、読み方や背景などを詳しく解説します!
1)「不亀手の薬」
不亀手の薬とは、あかぎれの薬のこと。『荘子』「逍遥游」に由来する言葉です。前回と同じく先賢の名訳は他に見ていただくとして*1、大雑把にあらすじだけを書いておくと、こんな話です。
(原文)
(前略)宋人有善為不龜手之藥者、世世以洴澼絖為事。客聞之、請買其方以百金。聚族而謀曰、我世世為洴澼絖、不過數金。今一朝而鬻技百金、請與之。客得之、以説呉王。越有難、呉王使之將、冬與越人水戰、大敗越人、裂地而封之。能不龜手一也、或以封、或不免於洴澼絖、則所用之異也。(後略)
(あらすじ)
宋の国にあかぎれを防ぐ特効薬(不亀手之薬)を作るものがいて、日々絹をさらす稼業をしていた。そこによその国の人が来て、そのあかぎれの薬の製造法を百金で売ってほしいと言い、宋国の者は大金に目がくらんで製造法を教えてしまった。製造法を知ったその人物は呉の国に遊説に行った。呉は、ちょうどたまたま越と戦争をしていた時だったので、呉の王は彼を将軍に任命して戦争に赴かせた。将軍に任命されたその人物は冬に水上で越と戦い、あかぎれの特効薬があったおかげで越に大勝したので、王は彼を大名に取り立てた。おなじ薬であっても、片方は大名となり、もう一方は絹を晒す稼業をやめられなかったのは、その使い方が異なったからなのだ。
物事の価値は、それを使う人の視野や発想によって大きく変わるということを伝える寓話です。
2)なぜあかぎれを「亀手」と書くのか
まず、あかぎれを「亀手」と書いた理由について確認しましょう。これは、水仕事などであかぎれてしまった手にはひびが入り、それがまるで亀の紋様のようだから「亀手」と呼んでいるのでしょう。そのことは『荘子』に注釈を施した晋の学者司馬彪(240頃-306年)が、「文坼如亀文也(文の坼くること亀の文の如くなればなり)」といっていることからわかります。
3)本当に「亀手」はキンシュと読むのか
次に、「亀手」の「亀」は本当にキンと読まれてきたのかどうかについて、確認しましょう。
私の手元にある机上版漢和辞典(『漢字源(第六版)』、『漢検漢字辞典(第二版)』、『新字源(改訂新版)』、『漢辞海(第四版)』)では、いずれも〈あかぎれ〉の意味で使う「亀」は「キン」と読むと載っています。これらの漢和辞典が載せる「キン」という発音は、『経典釈文』(隋・陸徳明、583年成書)という、儒教の経典や老子・荘子に出てくる、難解な字や特殊な読み方についてまとめた注釈書に由来します。『経典釈文』では、「亀手」の「亀」の読み方について、反切という発音表記法を用いて「亀、愧悲反、徐挙倫反、李居危反」と記しています(それぞれ、キ/kʏi/,キン/kyĕn/,キ/kʏĕ/。//内は隋唐時代の発音*2 )。ここで三つの発音が示されているのは、それぞれの師匠から受け継いできた学統によって違いがあるためで、うち、「徐」と示されている東晋時代の学者徐邈(344-397)は、この文脈で使われる「亀」をキン(挙倫反、/kyĕn/)と読んでいたようです *3。
『経典釈文』に見える、徐邈が伝えた「キン」という読み方が約1600年後の現代日本でも使われ、あかぎれの薬のことを「不亀手の薬」と読んでいるのです。
4)「亀」をなぜキンと読むのか
清末の学者である李楨は、『荘子』に見える「亀」のこの特殊な読み方について、「皸」(あかぎれ、キン)の仮借であると言っています *4。
「仮借(通仮)」とは漢字の用字法の一つで、発音が同じ、或いは類似することを利用して、違う言葉の字形を借りて言葉を書き記すという方法です。例えば、古典文献の中では、もともと「汝」(ジョ)という字で〈あなた〉という意味を書き表すはずなのですが、これが往々にして、類似した発音である「女」(ジョ)という漢字で書かれています *5。
このような、【同音、或いは類似音であること(上例のジョ)を軸にして、ひとつの字形(女)に、別の言葉の意味(あなた)を担わせる用字法】を仮借(通仮)と呼ぶわけですが、今回の「亀」と「皸」との関係は、これとは少し様相が異なります。
〈あかぎれ〉はふつう「皸」(キン)と書くのですが、上に挙げた『荘子』では「亀」と書き「キン」と読ませることで、あかぎれという言葉を表しているのです。先ほどの仮借の例に寄せて解釈すると、【同じ意味であること(あかぎれ)を軸にして、ひとつの字形(亀)に、別の言葉の発音(キン)を担わせている】とみなせます。このように、同じ意味であることを利用して、別語の発音で読むことを、専門用語で「同義換読」や「義同換読」などとといいます。
有名な同義換読には、南宋の書家として著名な趙孟頫の「頫」(本来の発音はチョウ。同じ〈うつむく〉という意味の「俯」字の発音で読まれたもの)があります *6。ほか、現代日本語の「漁」も同様の例と言えるでしょう(本来の発音はギョ。同じ〈生物を捕らえる〉という意味の「猟」字の発音で読まれたもの。平安末期の西行法師の歌に既に用例がある *7)。
述べてきたところを以下に箇条書きにしておきましょう。
1.あかぎれた手の様子が亀の紋様に似ているので「亀手」と呼ぶ。
2.晋代の学者、徐邈は、亀手の「亀」をキン(挙倫反)と読んでいる。
3.「亀」をキンと読むのは、おなじあかぎれの意味である「皸」(キン)という漢字の発音が使われたためである。このような、意味の類似によって字を別語の発音で読むことを「同義換読」と呼ぶ。
4,同義換読の例には、他に「趙孟頫」の「頫(フ)」、現代日本語における「漁(リョウ)」などがある。
冬場の水仕事にあかぎれはつきもの。読み方が分かれるのは仕方がないとして、せめて指先だけでも割れなければよいのに、と冬になるたびに感じています。
次回は8月12日(火)に公開予定です。
≪注釈≫
1 池田知久訳、藤堂明保監修『荘子』(学習研究社、1992年)など。
2 平山久雄「中古漢語の音韻」(『中国文化叢書1 言語』大修館書店、1967年)の推定音価に拠る。
3 徐邈以外の学者の読み方では「キシュ」となるので、漢和辞典ではこの両方の発音を載せていることが多い。
4 郭慶藩『荘子集釋』(新編諸子集成、中華書局、2018年)に拠る。
5 以下「女/汝」「亀/皸」「頫/府」などの発音は、便宜上日本漢字音で示す。
6 裘錫圭『文字学概要』(商務印書館、1988年。日本語訳書『中国漢字学講義』〈稲畑耕一郎・崎川隆・荻野友範訳、東方書店、2022年〉)、沈兼士「漢魏注音中義同換読例発凡」(『沈兼士学術論文集』〈中華書局、1986年〉所収)などに実例が挙がっているので参考にされたい。
7 「宇治川の 早瀬おちまふ漁舟の かづきにちがふ こひのむらまけ」(『新潮日本古典集成 山家集』(後藤重郎校注、新潮社、1982年)による)。西行法師に用例があることは江戸時代の国学者契沖の『和字正濫抄』巻5「猟師」により知った。
≪おすすめ記事≫
「檸檬」の表記はいつ? どこから?【漢検1級で出題された熟語を解説! 2】 はこちら
クイズ番組で話題の難読漢字にチャレンジ!その2~小学校で習う難読漢字?!~ はこちら