部首にまつわるミステリー【3】〜声符が部首になるとき〜|やっぱり漢字が好き53
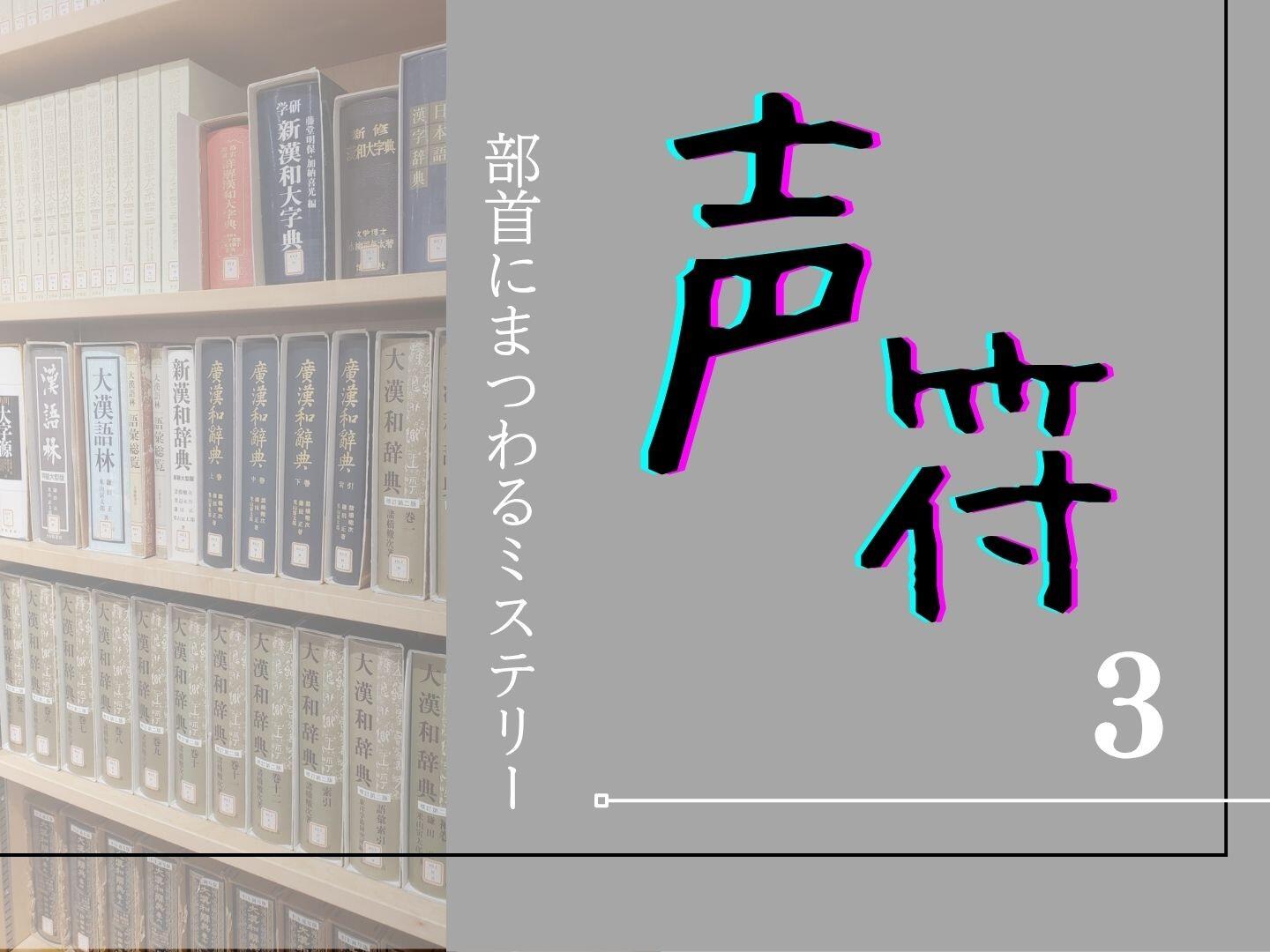
著者:戸内俊介(日本大学文理学部教授)
形声文字では通常、義符が部首として立てられ、声符が部首となる例は少ない。その少数派の一例として「信」字を前号【2】で紹介した。今号では、声符が部首として扱われているいくつかの事例を挙げ、日中の各辞書における取り扱いを見ていきたい。
代表例は「![]() 」(たけかんむり)である。「篤」「竺」「筑」「築」はいずれも「竹」を声符とする形声文字であるが、中国・清代の『康熙字典』はこれらを「
」(たけかんむり)である。「篤」「竺」「筑」「築」はいずれも「竹」を声符とする形声文字であるが、中国・清代の『康熙字典』はこれらを「![]() 」(たけかんむり)の部首に配当する。なお『康熙字典』は現代の漢和辞典の規範となった辞書である。
」(たけかんむり)の部首に配当する。なお『康熙字典』は現代の漢和辞典の規範となった辞書である。
「磔」は『康熙字典』で「石」(いしへん)の部首に収録されるが、本来「石」が声符の形声文字である。
「到」は『康熙字典』では「刂(刀)」(りっとう)の部首に属するが、本来「刀」が声符の形声文字である。
「衡」は『康熙字典』では「行」(ぎょうがまえ)の部首に配当されるが、本来「行」が声符の形声文字である。
さらに「巡」は「辶」を義符とする形声文字であることから、本来は「辶」(しんにょう)の部首に属すべきである。ところが『康熙字典』は「 ![]() (川)」(さんぼんがわ)の部首のもとに採録する。しかし実際には「
(川)」(さんぼんがわ)の部首のもとに採録する。しかし実際には「 ![]() (川)」は「巡」の声符である。
(川)」は「巡」の声符である。
以下ではここまで列挙した文字について、中国の字書や日本の漢和辞典で実際にどのように扱われ、どの部首に配当されているのかを見ていきたい。さしあたり、手元にあった以下の辞書を調査対象とした。辞書の書誌情報の後ろに、その辞書の簡単な紹介やコメントも書き加えた。
【中国の字書】
(後漢)許慎『説文解字』、一篆一行本影印、中華書局、1963年
:目下、最古の漢字字書。初めて漢字を部首によって分類。540種の部首を建てる。
(明)梅膺祚『字彙』、上海辞書出版社、1991年
:画数順に部首を並べる配列形式をはじめて採用。214部の部首を建てる。
(明)張自烈『正字通』、東豊書店、1996年
:部首の分類及び配列形式は『字彙』を継承。214部の部首を建てる。
(清)張玉書・陳廷敬『康熙字典』、同文書局影印本、上海書店、1985年
:康熙帝の勅撰により編纂された。部首の建て方は『字彙』『正字通』を継承し、214部。部首の分類及び配列形式は、のちの漢字辞典の規範となった。
漢語大字典編輯委員会編『漢語大字典(第2版)』、四川辞書出版社、2010年
:世界最大規模の大型漢字字典。部首は『康熙字典』の214部を基礎としつつ、適宜調整を加え、200部を建てる。なお羅竹風主編『漢語大詞典』(漢語大詞典出版社、2001年)も同じ部首建て。
【日本の漢和辞典】
小川環樹・西田太一郎・赤塚忠・阿辻哲次・釜谷武志・木津祐子編『新字源(改定新版)』、角川書店、2017年
:凡例によると、部首の分類・配列はおおむね『康煕字典』にならうも、検索の便宜上『康煕字典』の部首と異なる形を掲げた場合もある。同時に、『康煕字典』の部首分類が不合理な漢字は所属部首を改め、変更した。
鎌田正・米山寅太郎著『新漢語林(第2版)』、大修館書店、2011年
:凡例によると、部首立ては『康煕字典』の部首に基づいたが、一部新しい工夫を加えた。
戸川芳郎監修、佐藤進・濱口富士雄編『全訳漢辞海(第4版)』、三省堂、2016年
:凡例によると、部首の分類及び配列は原則として、『康煕字典』の214部に従う。
諸橋轍次著、鎌田正・米山寅太郎修訂増補『大漢和辞典(デジタル版)』、大修館書店、2019年
:凡例によると、すべての文字を『康煕字典』の214部の部首順に分類した。
1.「篤」
【中国の字書】
『説文解字』 :「馬」の部首。「馬」が義符、「竹」が声符の形声文字と分析。
『字彙』 :「竹」の部首
『正字通』 :「竹」の部首
『康熙字典』 :「竹」の部首
『漢語大字典』:「竹」の部首
【日本の漢和辞典】
『新字源』 :「馬」の部首。「竹」を声符とする形声文字と分析。
『新漢語林』 :「竹」の部首
『漢辞海』 :「竹」の部首
『大漢和辞典』:「竹」の部首
2.「竺」
【中国の字書】
『説文解字』 :「二」の部首。「二」が義符、「竹」が声符の形声文字と分析。
『字彙』 :「竹」の部首
『正字通』 :「竹」の部首
『康熙字典』 :「竹」の部首
『漢語大字典』:「竹」の部首
【日本の漢和辞典】
『新字源』 :「竹」の部首。「竹」を声符とする形声文字と分析。
『新漢語林』 :「竹」の部首
『漢辞海』 :「竹」の部首
『大漢和辞典』:「竹」の部首
3.「筑」
【中国の字書】
『説文解字』 :「竹」の部首。「筑は、竹で奏して曲となす。五弦の楽器。『竹』『巩』から構成され、『巩』は持つ意である。『竹』は音でもある」として、「竹」と「巩」の会意文字と見なしつつ、「竹」は声符でもあると分析(専門的には亦声と呼ばれるもの)。
『字彙』 :「竹」の部首
『正字通』 :「竹」の部首
『康熙字典』 :「竹」の部首
『漢語大字典』:「竹」の部首
【日本の漢和辞典】
『新字源』 :「竹」の部首。「竹」と「巩」によって構成されつつ、「竹」が声符でもある会意形声文字として分析。
『新漢語林』 :「竹」の部首
『漢辞海』 :「竹」の部首
『大漢和辞典』:「竹」の部首
4.「築」
【中国の字書】
『説文解字』 :「木」の部首。「木」が義符、「筑」が声符の形声文字と分析。
『字彙』 :「竹」の部首
『正字通』 :「竹」の部首
『康熙字典』 :「竹」の部首
『漢語大字典』:「竹」の部首
【日本の漢和辞典】
『新字源』 :「木」の部首。「筑」を声符とする形声文字と分析。
『新漢語林』 :「竹」の部首
『漢辞海』 :「竹」の部首
『大漢和辞典』:「竹」の部首
5.「磔」
【中国の字書】
『説文解字』 :「桀」の部首。「桀」が義符、「石」が声符の形声文字と分析。
『字彙』 :「石」の部首
『正字通』 :「石」の部首
『康熙字典』 :「石」の部首
『漢語大字典』:「石」の部首
【日本の漢和辞典】
『新字源』 :「石」の部首。「石」を声符とする形声文字と分析。
『新漢語林』 :「石」の部首
『漢辞海』 :「石」の部首
『大漢和辞典』:「石」の部首
6.「到」
【中国の字書】
『説文解字』 :「至」の部首。「至」が義符、「刀」が声符の形声文字と分析。
『字彙』 :「刀」の部首
『正字通』 :「刀」の部首
『康熙字典』 :「刀」の部首
『漢語大字典』:「刀」の部首
【日本の漢和辞典】
『新字源』 :「至」の部首。「刀」を声符とする形声文字と分析。
『新漢語林』 :「刀」の部首
『漢辞海』 :「刀」の部首
『大漢和辞典』:「刀」の部首
7.「衡」
【中国の字書】
『説文解字』 :「角」の部首。「角」と「大」から構成され、「行」が声符の形声文字と分析。
『字彙』 :「行」の部首
『正字通』 :「行」の部首
『康熙字典』 :「行」の部首
『漢語大字典』:「彳」の部首
※「行」の部首のものは「彳」に配属することを凡例で明記。
【日本の漢和辞典】
『新字源』 :「行」の部首。「行」を声符とする形声文字と分析。
『新漢語林』 :「彳」の部首。
※「行」の部首のものは一括して「彳」にまとめる。
『漢辞海』 :「行」の部首
『大漢和辞典』:「行」の部首
8.「巡」
【中国の字書】
『説文解字』 :「辶」の部首。「辶」が義符、「 ![]() (川)」が声符の形声文字と分析。
(川)」が声符の形声文字と分析。
『字彙』 :「 ![]() 」の部首
」の部首
『正字通』 :「 ![]() 」の部首。
」の部首。
※ただし「宜帰辵部、附![]() 非是。」〔辵(辶)の部首に帰属させるべきで、
非是。」〔辵(辶)の部首に帰属させるべきで、![]() に配当するのは正しくない。〕と注記する。
に配当するのは正しくない。〕と注記する。
『康熙字典』 :「 ![]() 」の部首
」の部首
『漢語大字典』:「辶」の部首。
※検索に不便との理由で「巡」を「 ![]() 」部から「辶」部へ改めたことを凡例で明記。
」部から「辶」部へ改めたことを凡例で明記。
【日本の漢和辞典】
『新字源』 :「辶」の部首。「 ![]() (川)」を声符とする形声文字と分析。
(川)」を声符とする形声文字と分析。
『新漢語林』 :「辶」の部首。「 ![]() (川)」を声符とする形声文字と分析。
(川)」を声符とする形声文字と分析。
『漢辞海』 :「![]() 」の部首
」の部首
『大漢和辞典』:「![]() 」の部首
」の部首
以上、声符がしばしば部首に分類されている「篤」「竺」「筑」「築」「磔」「到」「衡」「巡」の諸字について、中国の字書や日本の漢和辞典における配当状況を一覧した(文字の色分けの意図については次号で説明する)。次号では、この調査結果を踏まえ私見を述べたい。なお、「科」(禾)、「字」(子)、「外」(夕=月)、「式」(弋)、「魁」(鬼)、「麓」(鹿)、「毘」(比)、「碩」(石)もしばしば声符が部首扱いされるが(丸括弧は声符)、紙幅の都合により本稿では割愛した。関心のある方は、ぜひ本稿で取り上げた辞書を用いて調べてみてほしい。
次回「やっぱり漢字が好き54」は11月10日(月)公開予定です。
≪参考資料≫
本文参照
≪参考リンク≫
漢字ペディアで「篤」を調べよう
漢字ペディアで「竺」を調べよう
漢字ペディアで「筑」を調べよう
漢字ペディアで「築」を調べよう
漢字ペディアで「磔」を調べよう
漢字ペディアで「到」を調べよう
漢字ペディアで「衡」を調べよう
漢字ペディアで「巡」を調べよう
≪おすすめ記事≫
やっぱり漢字が好き。7 漢字の発音表記と占い はこちら
あつじ所長の漢字漫談2漢字は「形声」が7割。 はこちら
頭の体操!漢字クイズに挑戦!⑫共通の部首探しクイズ はこちら
≪著者紹介≫
戸内俊介(とのうち・しゅんすけ)
日本大学文理学部教授。1980年北海道函館市生まれ。東京大学大学院博士課程修了、博士(文学)。専門は古代中国の文字と言語。著書に『先秦の機能語の史的発展』(単著、研文出版、2018年、第47回金田一京助博士記念賞受賞)、『入門 中国学の方法』(共著、勉誠出版、2022年、「文字学 街角の漢字の源流を辿って―「風月堂」の「風」はなぜ「凮」か―」を担当)、論文に「殷代漢語の時間介詞“于”の文法化プロセスに関する一考察」(『中国語学』254号、2007年、第9回日本中国語学会奨励賞受賞)、「「不」はなぜ「弗」と発音されるのか―上中古中国語の否定詞「不」「弗」の変遷―」(『漢字文化研究』第11号、2021年、第15回漢検漢字文化研究奨励賞佳作受賞)などがある。










