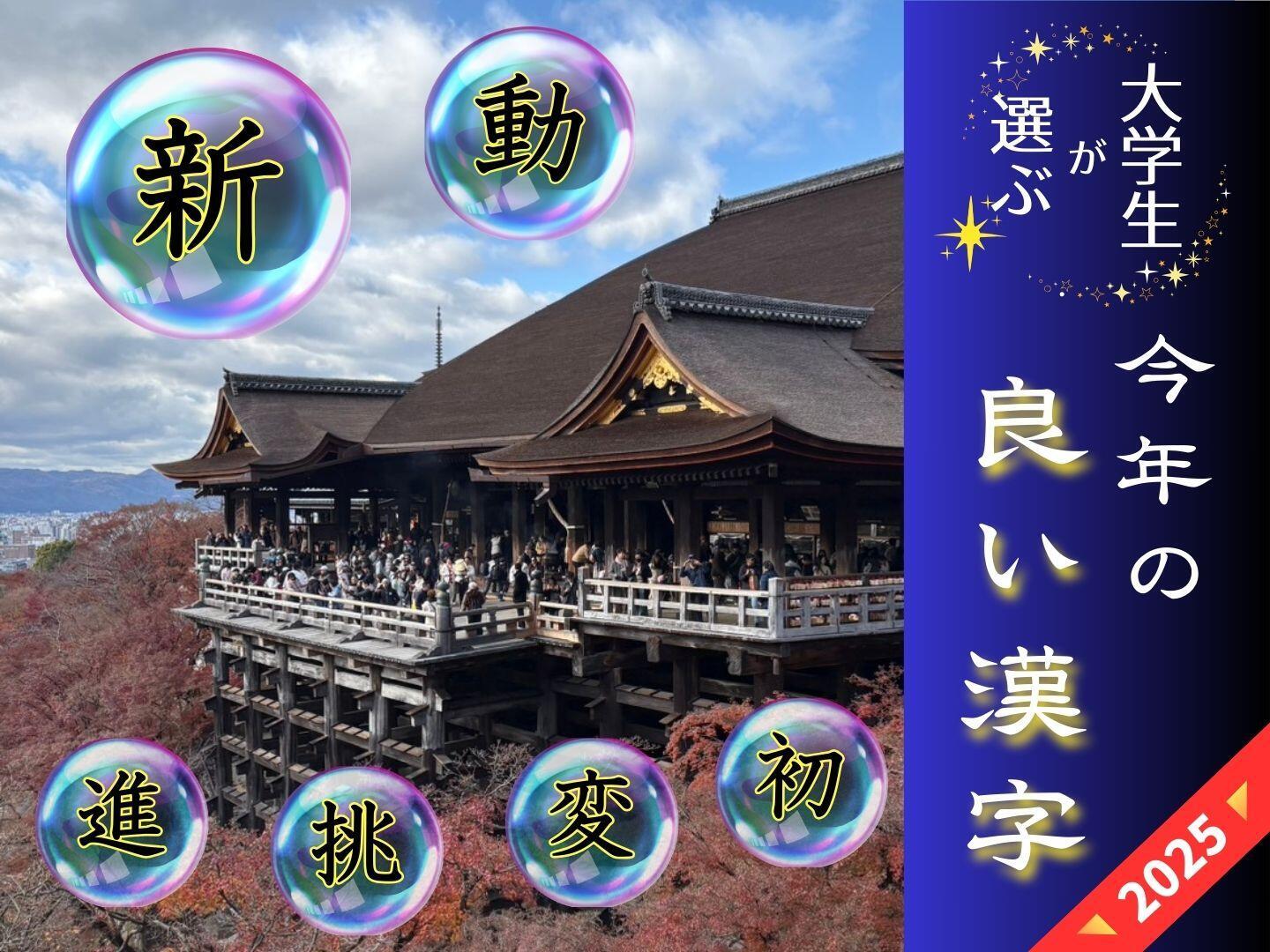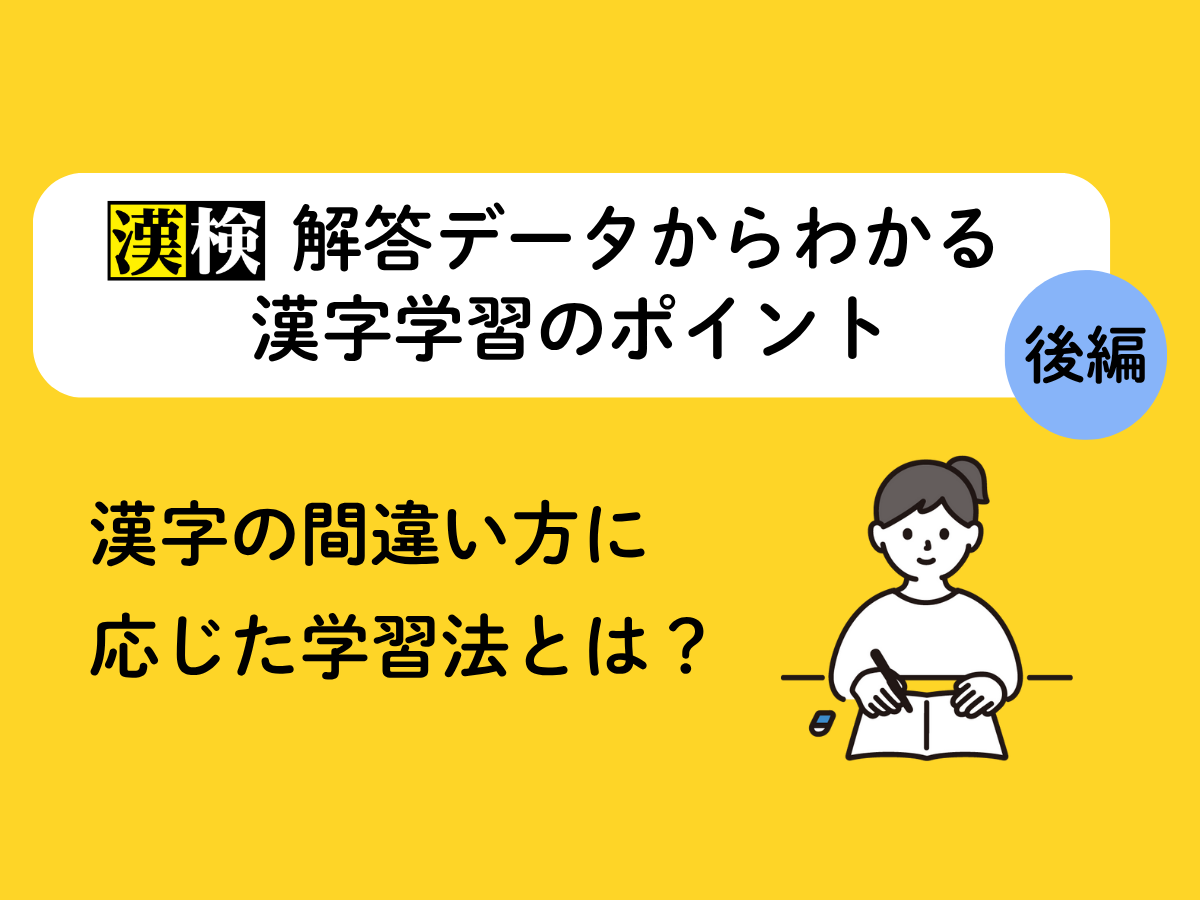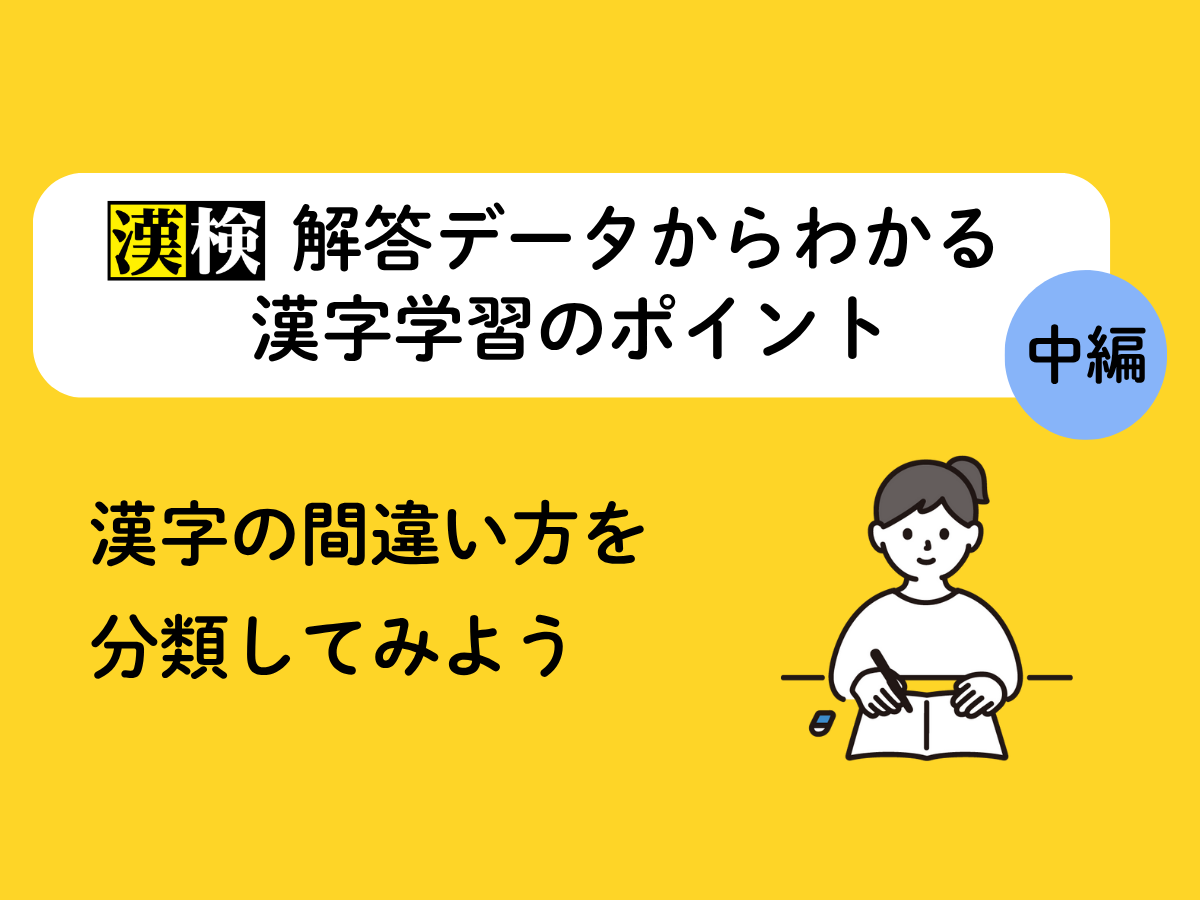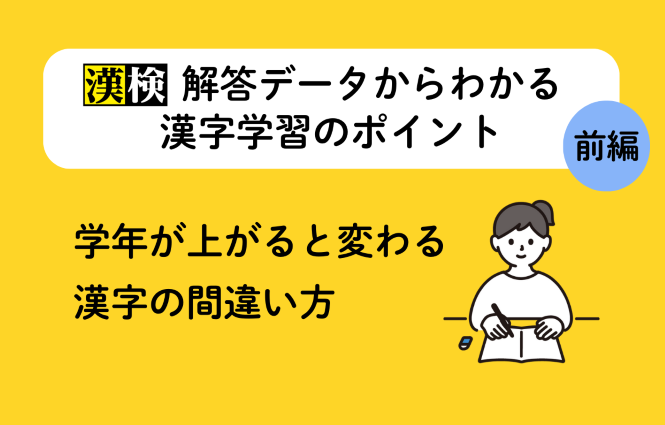「要約力」を鍛えてシンプルでわかりやすい文章を目指そう!

3月から新卒採用が本格的にスタートし、リクルートスーツの学生さんを見かけることが増えました。新卒採用で必ず書かされると言っても過言ではない「エントリーシート」。書き方に悩む学生さんも多いことでしょう。
自分の熱意を伝えようと頑張って書いたつもりなのに、読み返してみると、情報を詰め込み過ぎて一文が長く、何が言いたかったのかわからない…。
「シンプルでわかりやすい文章」を目指したい方には、「要約力」をつけるトレーニングをお勧めします。
今回はその「要約」のポイントについて、佐竹秀雄(公財)日本漢字能力検定協会 現代語研究室室長のコラムからご紹介します。
1.元の文章が表している情報の中で、重要度の大小を見抜く。
要約するときに最もわかりやすいのは、修飾語を省くということです。
例えば 「澄み渡った青い空に巨大な入道雲がもくもくと立ち上っている。」という文を要約するとします。言葉の修飾・被修飾関係を考えると、以下のようになります。
・「澄み渡った」と「青い」は「空」にかかる修飾語
・「巨大な」は「入道雲」にかかる修飾語
・「もくもくと」は「立ち上っている」にかかる修飾語
修飾語をすべて省略し、「空に入道雲が立ち上っている」とすれば要約したことになります。
ただし、「修飾語」を省略すると、元の文とは意味が異なってしまう場合もあるので要注意です。
“要約のときには、元の文章が表している情報の中で、重要度の大小を見抜くことが必要なのです。それには、文章全体の中で、筆者が何を言いたいのかに気を配らなければなりません。文章全体を踏まえて、より重要な情報を残すこと、それが要約のコツなのです。”とコラムにはあります。
2.情報をまとめて別の言葉で置き換える。
少し高度なテクニックとして紹介されている要約方法です。
「彼女は、ハンバーグとエビフライを作ってくれた。」という文は、例えば、「彼女は食事を作ってくれた」と要約することができます。
ただし、この場合は、元の文章で示された言葉を、別の言葉に言い表す力が必要になります。
また、そもそも置き換えてしまってもよい言葉なのかを判断するには、1.で述べた文章中の情報の重要度を見極める力が必要です。
『漢検ジャーナルVol.15』の「知っ得ことば情報」では、要約する方法について、具体的な文章例をあげて説明しています。ぜひお読みください。
≪参考リンク≫
・【コラム 知っ得ことば情報】「情報の重要度」を見極めて、要約の力を身につけよう 「漢検ジャーナルVol.15」(2015.5.1発行)掲載
・「漢検ジャーナル」が気になる人は、こちら!