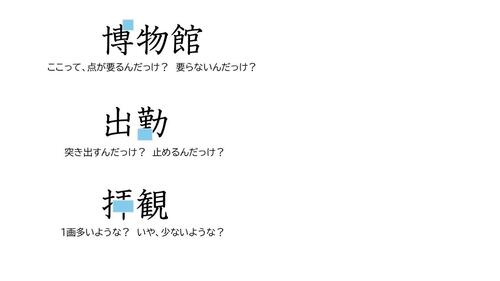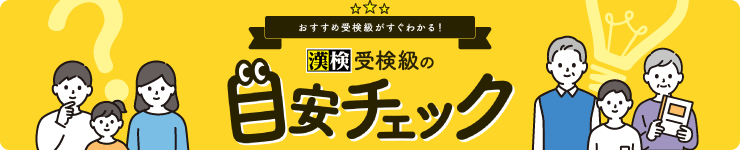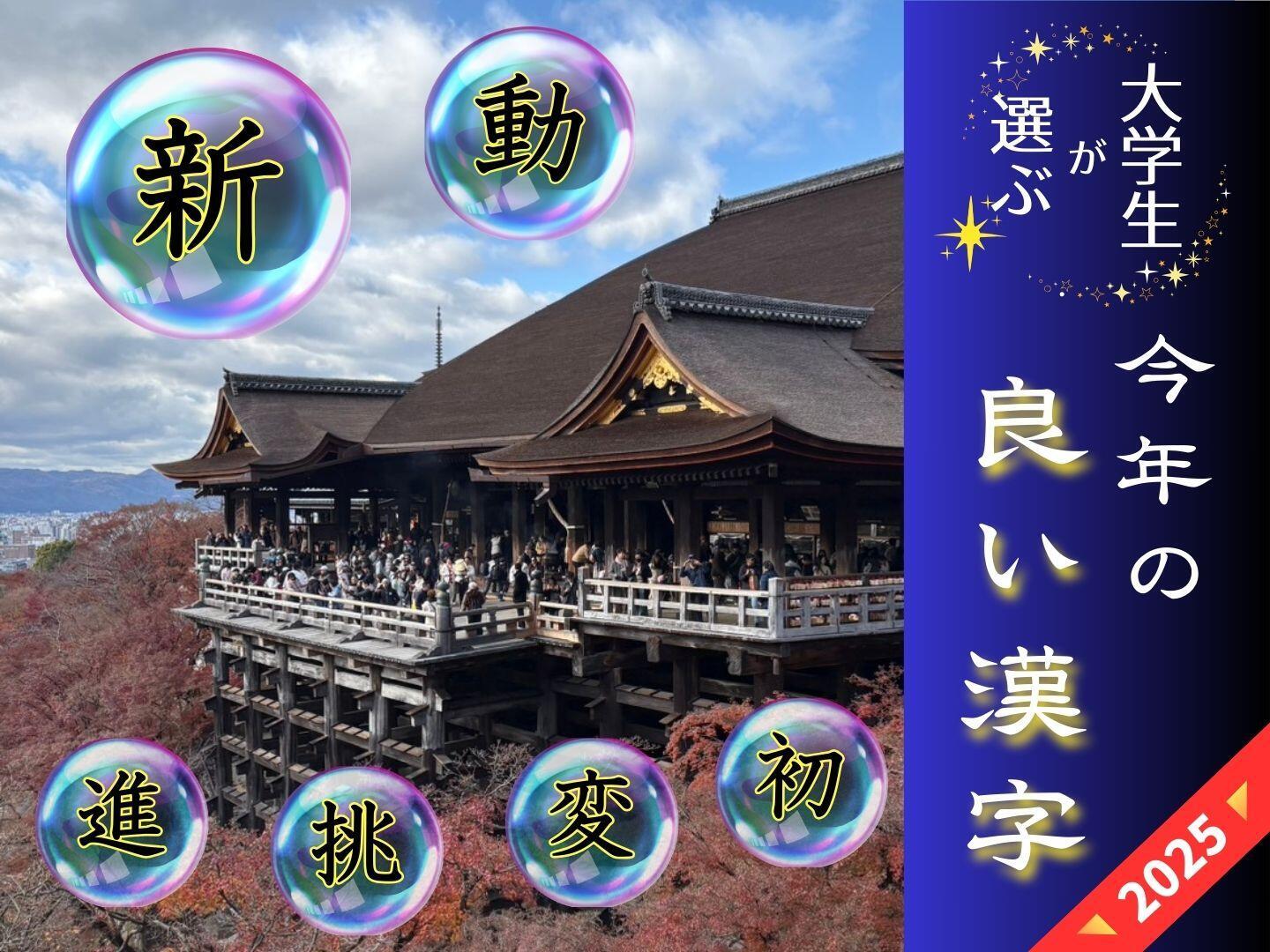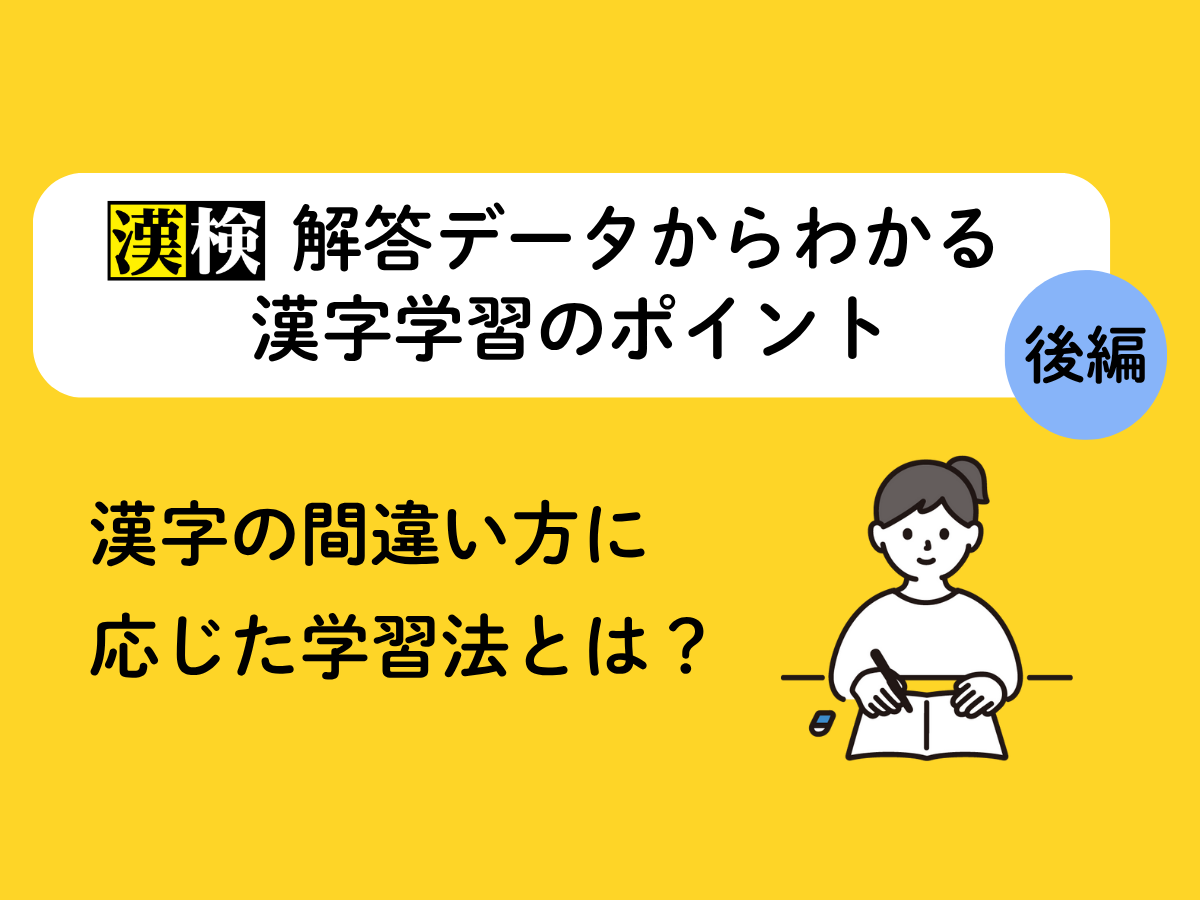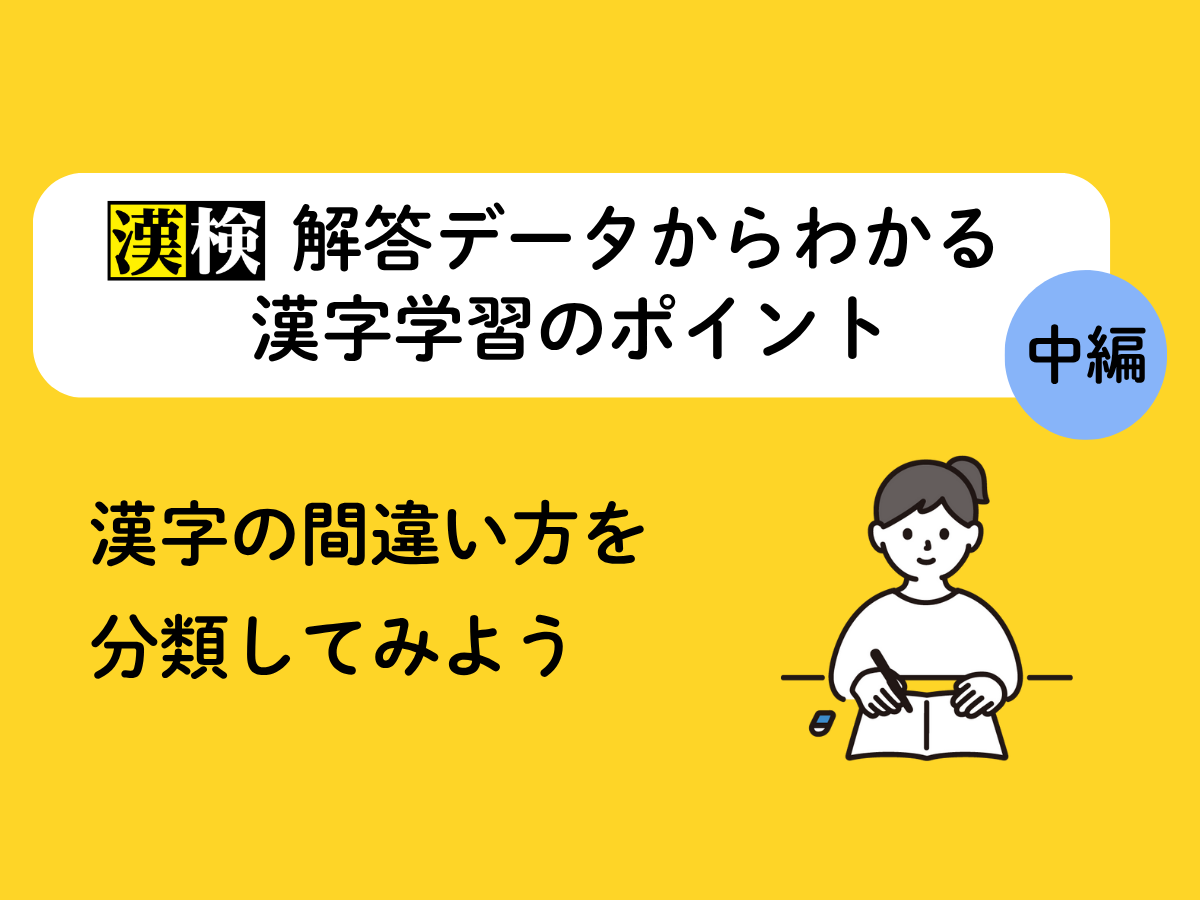「漢検」解答データからわかる漢字学習のポイント【前編】学年が上がると変わる漢字の間違い方
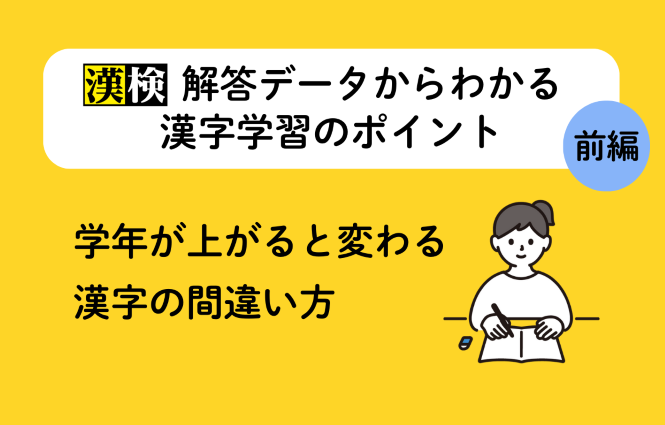
はじめまして、漢検協会 調査チームの調査員Akiです。「漢検」の解答データについて調査・分析しています。
年間約140万人分の答案を採点する漢検協会は、受検者のみなさんが書いた、たくさんの「手書き文字」のデータを保有しています。それら大量の「手書き文字」を手がかりに、みなさんの生活、学習に役立つ漢字の情報を発信していきたいと思います!
さっそくですが、みなさんは、「漢検で×になった答案」や「漢字の書き間違い」……と聞いたとき、どのようなものを思い浮かべるでしょうか?
このような、漢字の「形」に関する「書き間違い」を思い浮かべることが多いのではないかと思います。
特に、ご家庭に小学生のお子さんがいらっしゃる保護者の方ですと、漢字ドリルの丸つけをするときに、このような「書き間違い」に出くわすことがあるのではないでしょうか。
漢字を習い立ての時期には特に、筆画が不安定な字を書いてしまったり、漢字のパーツが左右逆になっていたりということも起きやすいでしょう。こういうときは、お手本の字を見ながら丁寧に書き写して学ぶ、という、誰しも身に覚えがあるだろう昔ながらの反復練習は効果があると思われます。
しかし、小学校高学年からやがて中学校、高校へと年齢が上がっていくほどに、事情も変わっていきます。学ぶ漢字の数は学年を追うごとに増えます。そして、画数が多いというだけでなく、同じ読みの漢字や、意味が近い漢字など、様々な点で複雑さも増していきます。
漢検協会が保有する解答データを見ても、「ちょっとした字の形の間違い」による×よりも、そもそも「まったく別の漢字を書いてしまっている間違い」による×が、多くなってくるのです。
例として、小学校で学習する漢字のうち、音読み「シ」を持つ漢字を数えてみましょう。1年生の時点で学習する「シ」と読む漢字は3字ですが、そこから学年を追うごとに5字(2年生)、7字(3年生)、3字(4年生)、7字(5年生)、6字(6年生)と増えていき、最終的に31字を学ぶことになります。同じ「シ」という読みを持つ漢字でも、この31字を適宜使い分ける必要があるのです。
このようなとき、幼い頃と同じようにただ書き取りの反復練習をするだけで、漢字の力は本当に身につくのでしょうか? もっと別の方法で、漢字の力を身につけることはできないのでしょうか? できれば、より早く、より効果的な方法で。
私たち調査チームは、漢検協会が保有する解答データのうち、×として採点された答案……いわゆる「誤答」のデータの中に、別の漢字学習方法の鍵があるのではと考えています。
次回の中編では、漢検協会が保有する解答データを実際に示しながら、「漢字の書き間違い方」の違いについて解説します。
≪参考リンク≫
あなたにオススメの級がわかる!漢検受検級の目安チェックに挑戦してみよう!
≪おすすめ記事≫
「世」正しい書き順で書ける? はこちら
意外な落とし穴!大量失点につながりかねない書き方って?~漢検・採点現場より②~ はこちら
≪執筆者紹介≫
調査員Aki
「漢検」の解答データを調査・分析する調査チームのメンバー。趣味はカメラ、ドラム、御城印集め、サッカー観戦。よく「多趣味だね」と言われる。