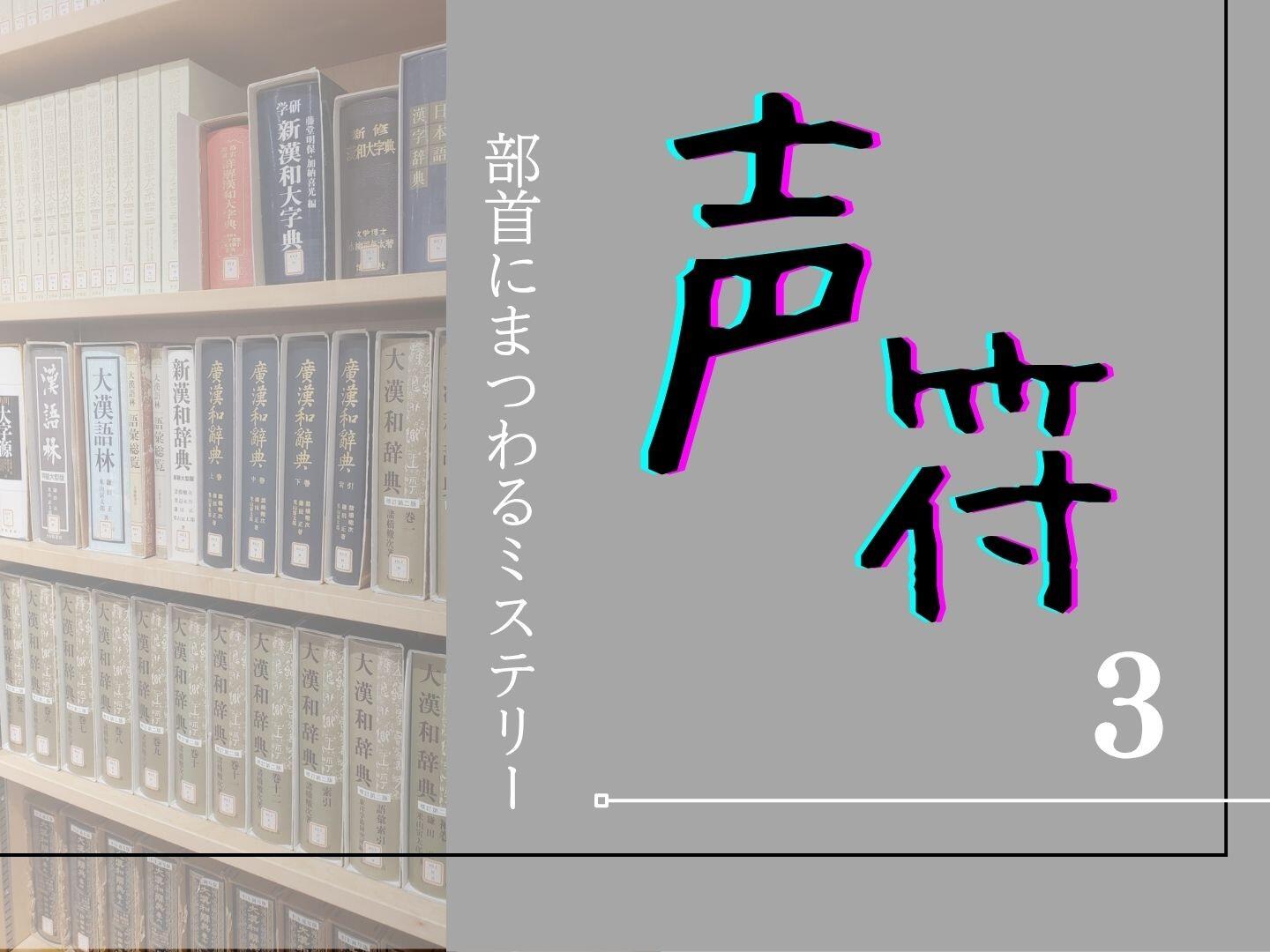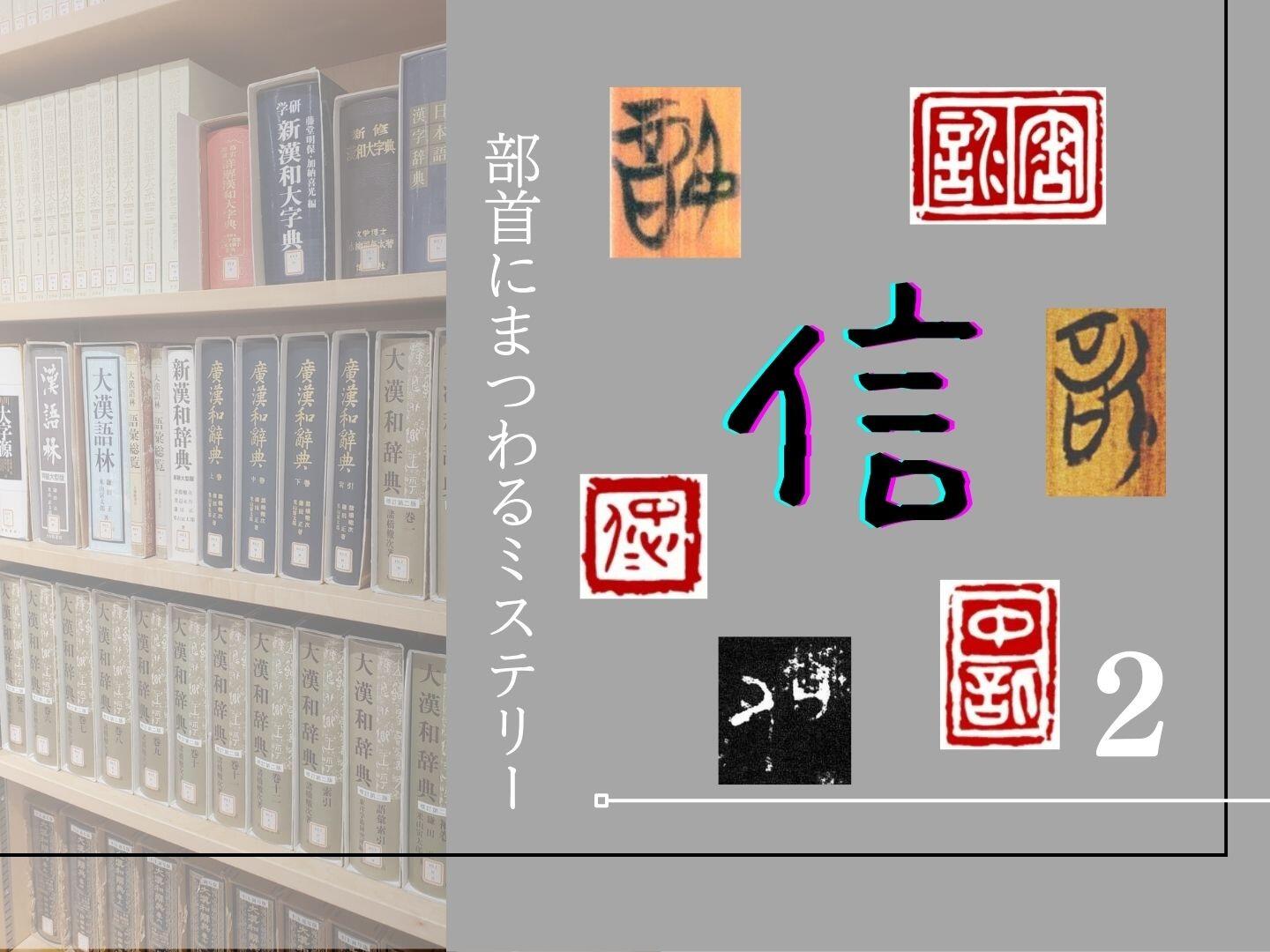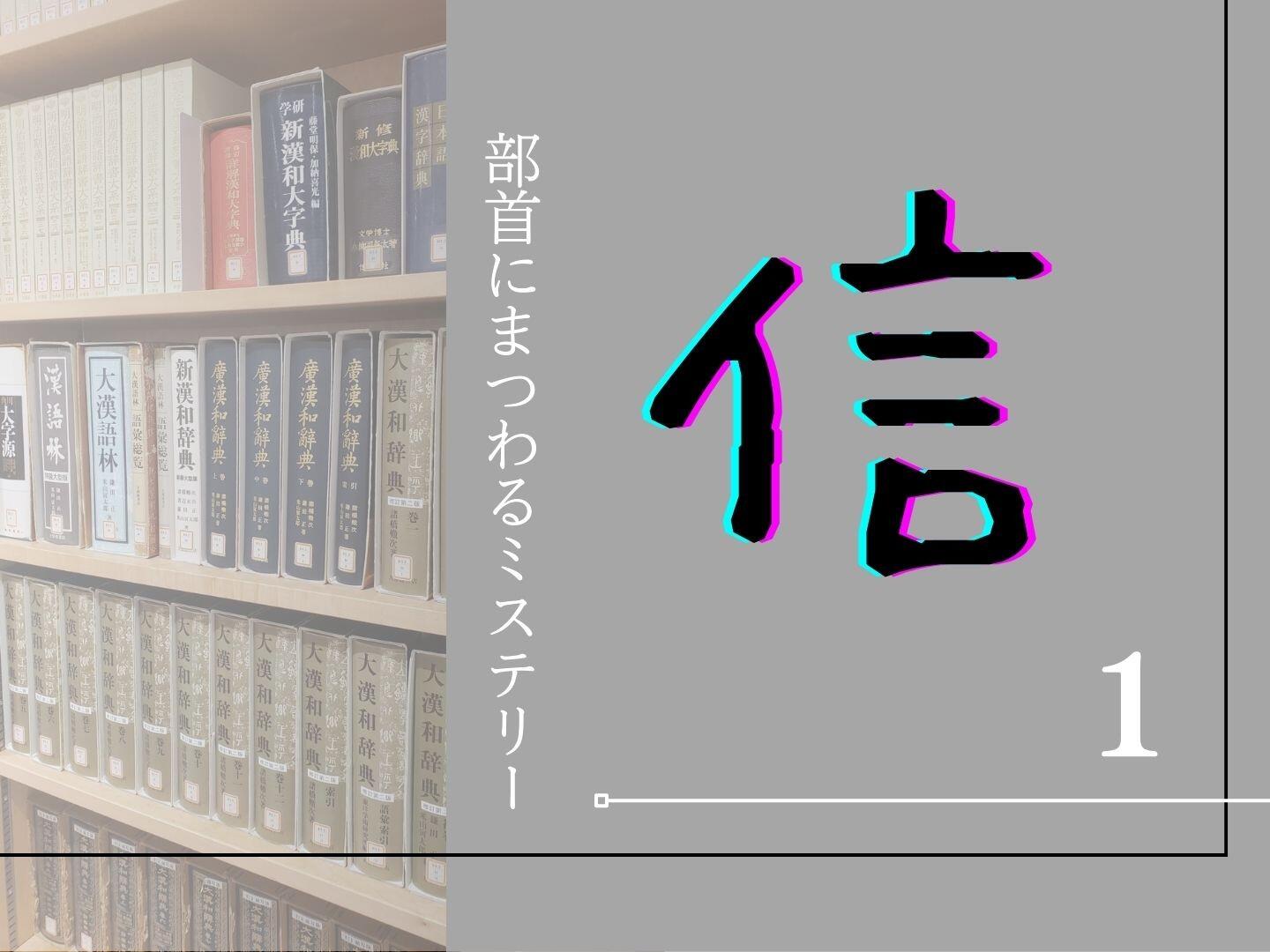漢字コラム9「親」 木の上に立っても・・・

著者:前田安正(朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長)
「親」という字は「木」と「立」と「見」でできています。これは、小鳥が巣立つ時に、親鳥は少し離れた枝から「大丈夫、がんばれ」「こっちの枝に飛んでおいで」と声を掛けて見守る様子が描かれたものなのです。ここに親のあるべき姿があるのです。決して手取り足取り教えるのではなく、親鳥のようにそっと子どもを信じて見守ってあげなくてはならないのです。
こんな訓話を聞いたことがありませんか?
とってもいい話じゃない。子どもの自立を見守ろう、ってことでしょ。何かいけないことでもあるの?
話としてはいいんだけど、これを「親」という字の成り立ちだと勘違いされては困るんだ。
え、違うの?
そうなんだ。「親」が「立+木+見」でできていると説明しているけれど、これは俗説。ほとんどの辞書は、「立+木」の部分は、「辛」と「木」が重なった「![]() 」で「シン」という音を持っていると言います。
」で「シン」という音を持っていると言います。
「辛」は刃物や取っ手のついた針のこと。これで木を切ったり木に刻みを入れたりしたと言います。つまり「![]() 」は「木を切る」ことを表していると言うのです。一説には「辛」を使って新しい位牌の木を選んだとあります。位牌を拝むのは「親しい人」だから「身内」「おや」「父母」を指すようになったというのです。
」は「木を切る」ことを表していると言うのです。一説には「辛」を使って新しい位牌の木を選んだとあります。位牌を拝むのは「親しい人」だから「身内」「おや」「父母」を指すようになったというのです。
そんな大昔から位牌があったのかな。
そこははっきりわからないんだけどね。もう一つの説は「![]() 」には「木を切る」という意味があるので、そこから「刃物を近づけて切る」「じかに触れる」という具合にイメージが展開して、「近い」「直接触れ合う」という感覚が生じたのではないか、と言うのです。中国の語学書「釈名(しゃくみょう)」には「親は
」には「木を切る」という意味があるので、そこから「刃物を近づけて切る」「じかに触れる」という具合にイメージが展開して、「近い」「直接触れ合う」という感覚が生じたのではないか、と言うのです。中国の語学書「釈名(しゃくみょう)」には「親は![]() (しん)なり」と書かれています。「
(しん)なり」と書かれています。「![]() 」は「肌着」のことです。「肌着は直接肌に触れることから「密接な」「近しい」というふうに、意味が膨らんでいったのではないか、と言われています。釈名にはさらに続けて「互いに隠
」は「肌着」のことです。「肌着は直接肌に触れることから「密接な」「近しい」というふうに、意味が膨らんでいったのではないか、と言われています。釈名にはさらに続けて「互いに隠![]() (いんしん)するなり」とあります。「隠
(いんしん)するなり」とあります。「隠![]() 」は「いたみ助ける」という意味です。互いにいたみ助ける関係こそが親子だ、と解釈できるのではないでしょうか。
」は「いたみ助ける」という意味です。互いにいたみ助ける関係こそが親子だ、と解釈できるのではないでしょうか。
≪参考資料≫
「漢字の起源」(角川書店 加藤常賢著)
「漢字語源辞典」(學燈社 藤堂明保著)
「漢字語源語義辞典」(東京堂出版 加納喜光)
「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)
「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)
「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(インターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照
≪参考リンク≫
≪著者紹介≫
前田安正(まえだ・やすまさ)
朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長
1955年福岡県生まれ。早稲田大学卒業。1982年朝日新聞社入社。名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センター長、用語幹事、東京本社校閲センター長などを経て、現職。
朝日カルチャーセンター立川教室で文章講座「声に出して書くエッセイ」、企業の広報研修などに出講。
主な著書に『漢字んな話』『漢字んな話2』(以上、三省堂)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』『「なぜ」と「どうして」を押さえて しっかり!まとまった!文章を書く』『間違えやすい日本語』(以上、すばる舎)など。