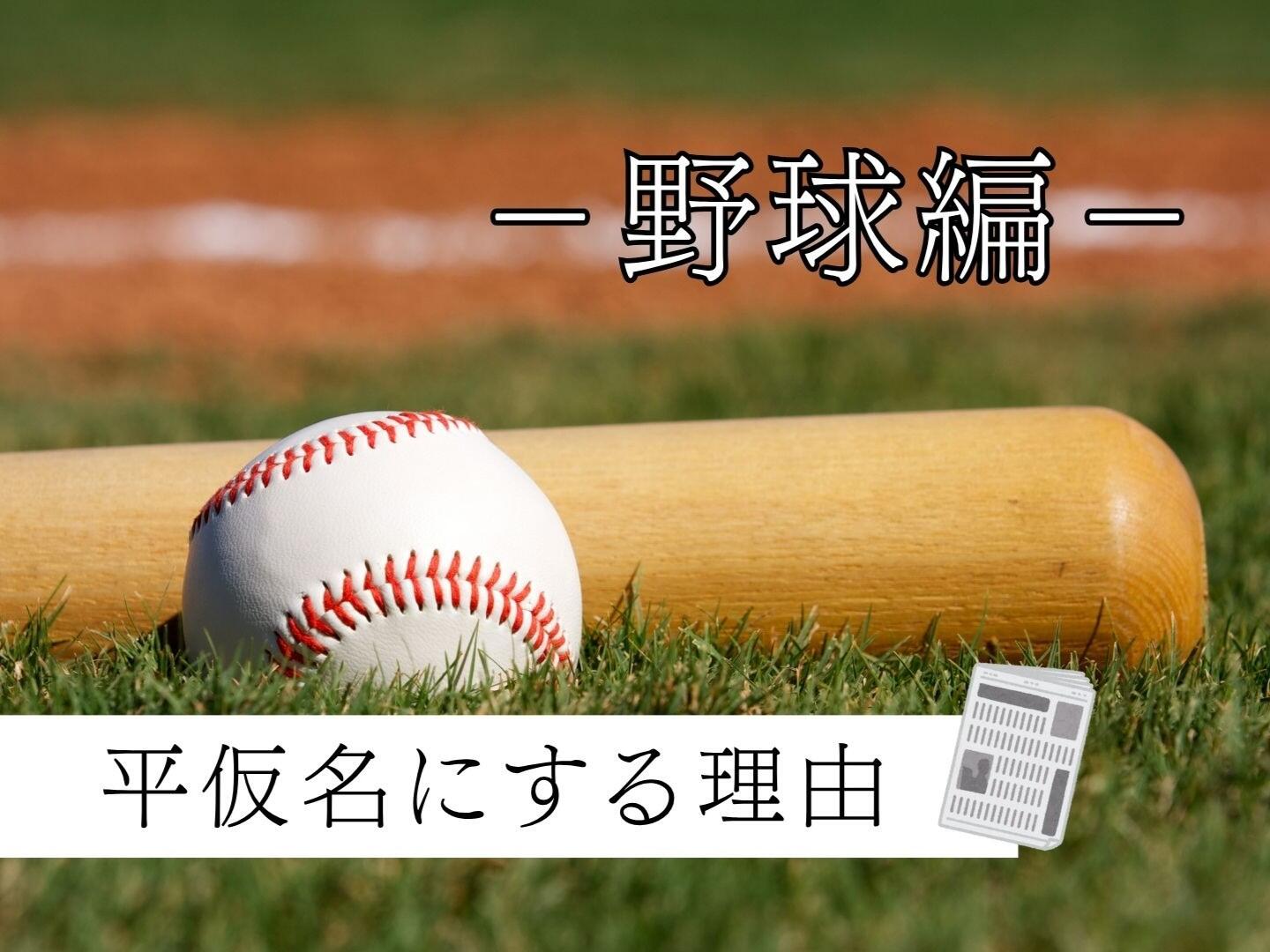「店休日」?それとも「休店日」?~再び二字熟語の語構成を考える~【下】|やっぱり漢字が好き44
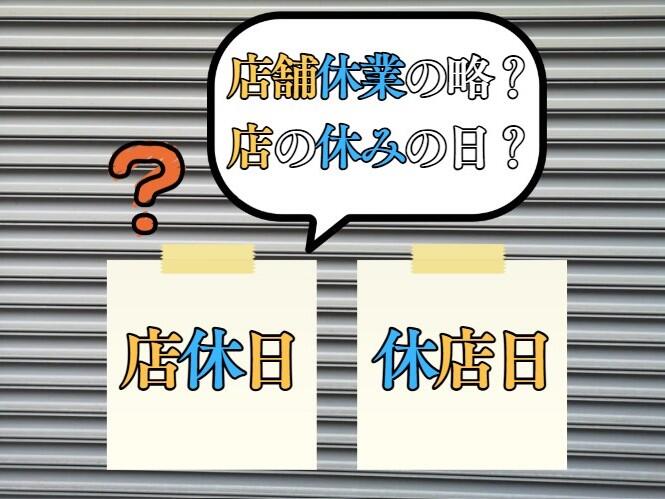
著者:戸内俊介(日本大学文理学部教授)
前々号、前号と「店休」という二字熟語が異例な語順であることを述べたが、今号の【下】ではなぜこのような言い方が生まれ、そして定着したのかについて、私見を提示したい。
この問題については、【上】で紹介した道浦俊彦氏のブログ「平成ことば事情」が「追記」(2004年2月3日)として次のような見解を提示している。
それはさておき、「店休日」「休店日」という言葉が生まれた背景について考えて見ました(原文ママ)。昔は間違いなく、「定休日」と言っていたと思います。それが使えなくなった、つまり、「定休日がなくなった」から、それに代わる休みの日のことを指す言葉が必要になったのではないでしょうか。(中略)それが本当に「365日、無休」に近くなってきて、完全に「定休日」という概念も形もなくなってしまったので、それに伴って「店休日」「休店日」という名称が出てきたのではないでしょうか。
これは1990年代後半以降、日本の小売店が不況のため休みが少なくなったという状況に基づいて立論されたものであるが、道浦氏のこの見解は実はよく調べてみると間違いであることがわかる。筆者が「国立国会図書館デジタルコレクション」を用いて初歩的な調査をしたところ、「店休日」の最も古い例は1937年であることが確認できた。『朝鮮公論』1937年3月号所収の「店員採用の二つの方針」という記事の中に次のようにある。
また店員の修養に對する團體的な指導方法としては店休日の翌日には、學校で毎朝朝會をやって校長先生が一場の訓話をするやうな具合に、朝仕事に就く前に全部を集めて支店長が一場の訓話をやるし、必要の場合には、店が退けてから各種の注意事項を授けるとこにしてゐる。
ここから「店休日」は決して21世紀以降に現れた新しい単語ではなく、戦前から使われていたことがわかる。さらに「休店日」も同じ時代から見られる。たとえば1940年に刊行された大阪毎日・東京日日新聞社エコノミスト部編『統制経済講座 第5』には次のような一文がある。
その他においても前記休店日には菓子の販賣を禁止する。
したがって、「定休日」がなくなった2000年代になってから「店休日」「休店日」という言葉が生まれたという道浦氏の見解は見直しを迫られる。
なおこの道浦氏の文章の中では、なぜ「休店日」ではなく「店休日」が定着したのかについてまでは触れられていない。この問題について、筆者は目下のところ次の3つの可能性があると考えている。
1つ目の可能性は、「店休日」の名称の誕生が「定休日」を前提としているというものである。「定休日」という呼称自体は大正時代以前から存在する。既存の「定休」/tei kyuu/という語の影響で、それと発音の近似した「店休」/ten kyuu/が「休店」よりも優先的に用いられたのではなかろうか。これはやや専門的な言い方をすれば、「類音牽引」(別に存在する語の発音の影響を受ける現象)の一種である。
2つ目は「店休」が略語である可能性である。以前のコラム「やっぱり漢字が好き20「尿禁」?「禁尿」? ~二字熟語の語構成~」で、何かを禁止することを意味する二字熟語に「禁〇」型(「禁輸、禁煙」など)と「〇禁」型(「発禁、駐禁」など)があることを踏まえ、「禁〇」型は漢語本来の語順を反映した構成であるが、それに反する「〇禁」型は実は略語であることを述べた(たとえば、「発禁」=「発売禁止」、「駐禁」=「駐車禁止」など)。そうであるならば、漢語本来の語順を反映しない「店休」は「店舗休業」や「商店休業」の略語である可能性がある。
3つ目は「店休」が「主語+動詞」という語構成ではなく、「修飾語+被修飾語」の語構成である可能性である。つまり、「店休日」=「店の休みの日」。前号で「主語+動詞」の二字熟語の例として「日没、地震、骨折、腰痛、頭痛」を挙げたが、これらはいずれも自然現象や身体の変異を言うものである。英語でも、“sunset”“sunrise”“earthquake”“headache”など平行する語が見られる。いずれも「主語+動詞」という語順をとりながら一語化している。
一方、「政変、人造、国営」などの語も「主語+動詞」の構造に見えるが、これらは「日没、地震」などとは異なり、自然現象や身体の変化を表すものではない。こうした言語事実に基づき、中川正之氏は「政変、人造、国営」などは「日没、地震」型とは異なり、「修飾語+被修飾語」の構造を持つ可能性があると指摘する。もしこの見解を受け入れるならば、「店休」も「政変、人造、国営」と同様に自然現象や身体の変化を表すものではないことから、「修飾語+被修飾語」構造で「店の休み」という意味を表している推測されるのである。
とりあえず思いつく可能性を挙げてみたが、皆さんはどのように考えるだろうか。
さてインターネットで「休店日」を検索したところ、HondaのディーラーであるHonda Carsが一貫して「店休日」ではなく「休店日」を用いていることに気が付いた。何か強いこだわりがありそうで、興味深い。
次回「やっぱり漢字が好き45」は5月26日(月)公開予定です。
≪参考資料≫
中川正之「漢語の語構成」、大河内康憲編『日本語と中国語の対照研究論文集』、くろしお出版、1997年
「国立国会図書館デジタルコレクション」、https://dl.ndl.go.jp/
≪参考リンク≫
≪おすすめ記事≫
「無洗米」を無理やり読み解いてみる【上】|やっぱり漢字が好き28 はこちら
古代中国では「寒い」ではなく「滄(さむ)い」だった? |やっぱり漢字が好き32 はこちら
≪著者紹介≫
戸内俊介(とのうち・しゅんすけ)
日本大学文理学部教授。1980年北海道函館市生まれ。東京大学大学院博士課程修了、博士(文学)。専門は古代中国の文字と言語。著書に『先秦の機能語の史的発展』(単著、研文出版、2018年、第47回金田一京助博士記念賞受賞)、『入門 中国学の方法』(共著、勉誠出版、2022年、「文字学 街角の漢字の源流を辿って―「風月堂」の「風」はなぜ「凮」か―」を担当)、論文に「殷代漢語の時間介詞“于”の文法化プロセスに関する一考察」(『中国語学』254号、2007年、第9回日本中国語学会奨励賞受賞)、「「不」はなぜ「弗」と発音されるのか―上中古中国語の否定詞「不」「弗」の変遷―」(『漢字文化研究』第11号、2021年、第15回漢検漢字文化研究奨励賞佳作受賞)などがある。