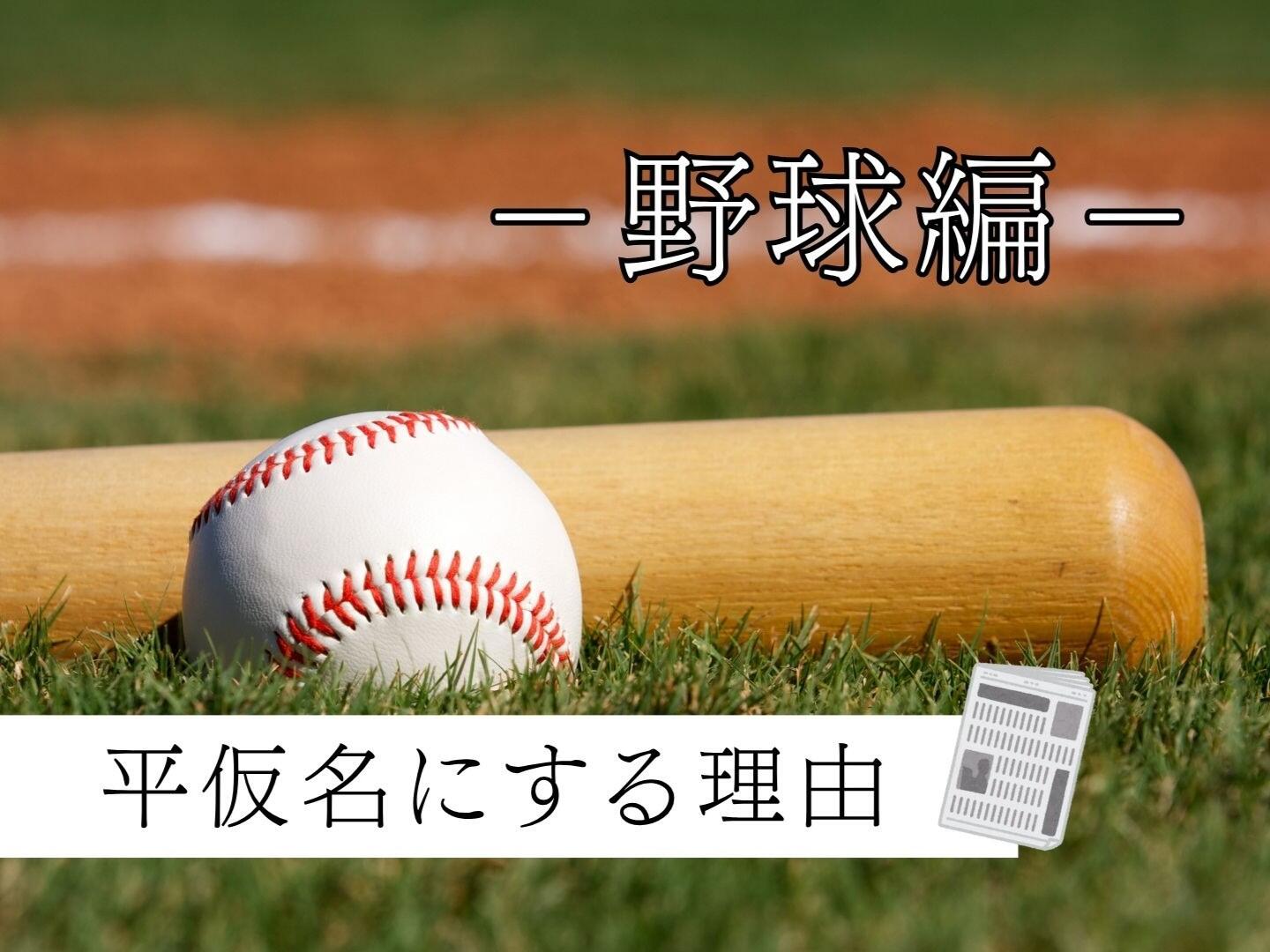「店休日」?それとも「休店日」?~再び二字熟語の語構成を考える~【中】|やっぱり漢字が好き43
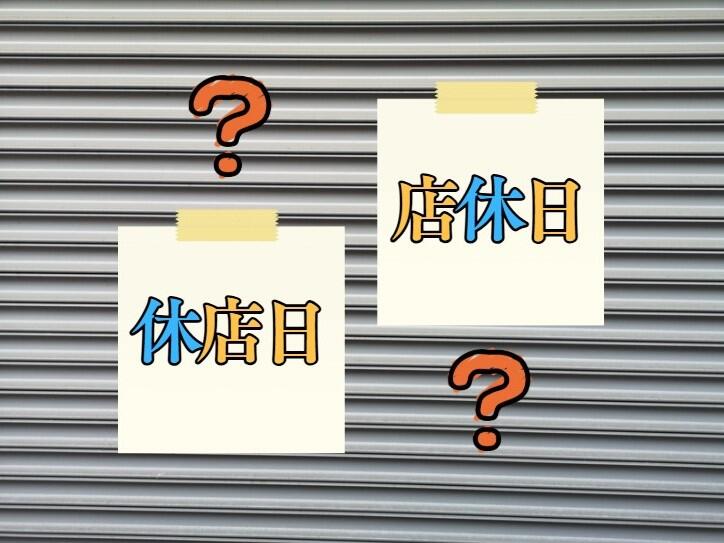
著者:戸内俊介(日本大学文理学部教授)
前号の【上】では、筆者が「店休日」という言い方にやや違和感を覚えたことを述べつつ、「店休日」に対する議論のひとつとして、道浦俊彦氏のコラムを紹介した。
さて「店休」という二字熟語の構成を虚心坦懐に見れば、「主語(店)+動詞(休)」という語順である。すなわち「店が休みである」という意味に読み取れる。同じような語構成の二字熟語には、このほか「日没、地震、骨折、腰痛、頭痛」などがある。
しかし「店が休みである」という表現は、店の人の視点から見れば必ずしも正確ではない。もし店の店主やオーナーが「店が休みである」と言おうものなら、「お前が休みにしたんだろ」と反論される可能性もある。店は従業員の判断で休むものであり、「店を休む、店を休みにする」という言い方がより実情に即しているであろう。
とはいうものの、日本語はたとえ何者かの作為によって生じた事態でも、「(事態)が(このように)なる・なった」と表現する「ナル型」の言語であるとされる。たとえば、電車に乗ったとき、次のようなアナウンスを耳にすることがある。
「扉が閉まります。ご注意ください。」
しかし厳密に言えばこれは奇妙な表現である。扉を閉めているのは電車の運転士や乗務員であり、したがって「扉を閉めます」というのがより正確であろう。しかし現実には「扉が閉まります」という表現が広く用いられている。これは動作主を明示的に表現しない言い方で、日本語における特徴的な表現のひとつと言える。なお、「扉が閉まります」を使うのか、「扉を閉めます」を使うのかは、鉄道会社によっても異なるらしい。東京では「扉が閉まります」を耳にする機会が多いが、京阪電車に乗っているとき、「扉を閉めます」というアナウンスを聞いたことがある。
このほかに「家が建った」とか「部屋がきれいになった」なども、本当は「(誰かが)家を建てた」「(誰かが)部屋をきれいにした」のである。しかし、建てられた家やきれいになった部屋を目にしたとき、ふつうは「家が建った」「部屋がきれいになった」など「ナル型」の表現を用いる。
一方、英語は「スル型」言語であると言われる。たとえば“This song makes me happy”は、無生物の動作主を主語としてたてた言い方で、直訳すると「この歌は私をうれしくする」となる。しかしこのように「(無生物)が〜する」という「スル型」で訳すと、日本語としてぎこちない。「この歌を聴くと私はうれしくなる」というように「ナル型」に訳すと自然な日本語になる。
話を「店休」に戻すと、店は本来、店の従業員が休みとするものであるが、それを「店休」、すなわち「店が休みである」というのは、「ナル型」の表現形式とも言える。
以上は「店休」を「主語+動詞」構造と捉えたものだが、このほか「店休」が「券売」式の語構成である可能性もある。すなわち、「券売」が「券を売る(目的語+動詞)」という日本語の語順に則した語構成であるのと同様に、「店休」も「店を休む(目的語+動詞)」という日本語の語順に則した語構成であるという解釈である。
ここまで、「店休」の語構成に対する2つの解釈を挙げたが、いずれにせよ、他の「休」を用いた二字熟語「休校、休講、休館、休刊、休業」が「動詞+目的語」の漢語(中国語)式語構成であることに比べると、「店休」の構成は異例である。なぜこのような言い方が生まれ、そして定着したのか。次号の【下】ではこの問題について、私見を述べたい。
次回「やっぱり漢字が好き44」は5月12日(月)公開予定です。
≪参考リンク≫
≪おすすめ記事≫
「無洗米」を無理やり読み解いてみる【上】|やっぱり漢字が好き28 はこちら
古代中国では「寒い」ではなく「滄(さむ)い」だった? |やっぱり漢字が好き32 はこちら
≪著者紹介≫
戸内俊介(とのうち・しゅんすけ)
日本大学文理学部教授。1980年北海道函館市生まれ。東京大学大学院博士課程修了、博士(文学)。専門は古代中国の文字と言語。著書に『先秦の機能語の史的発展』(単著、研文出版、2018年、第47回金田一京助博士記念賞受賞)、『入門 中国学の方法』(共著、勉誠出版、2022年、「文字学 街角の漢字の源流を辿って―「風月堂」の「風」はなぜ「凮」か―」を担当)、論文に「殷代漢語の時間介詞“于”の文法化プロセスに関する一考察」(『中国語学』254号、2007年、第9回日本中国語学会奨励賞受賞)、「「不」はなぜ「弗」と発音されるのか―上中古中国語の否定詞「不」「弗」の変遷―」(『漢字文化研究』第11号、2021年、第15回漢検漢字文化研究奨励賞佳作受賞)などがある。