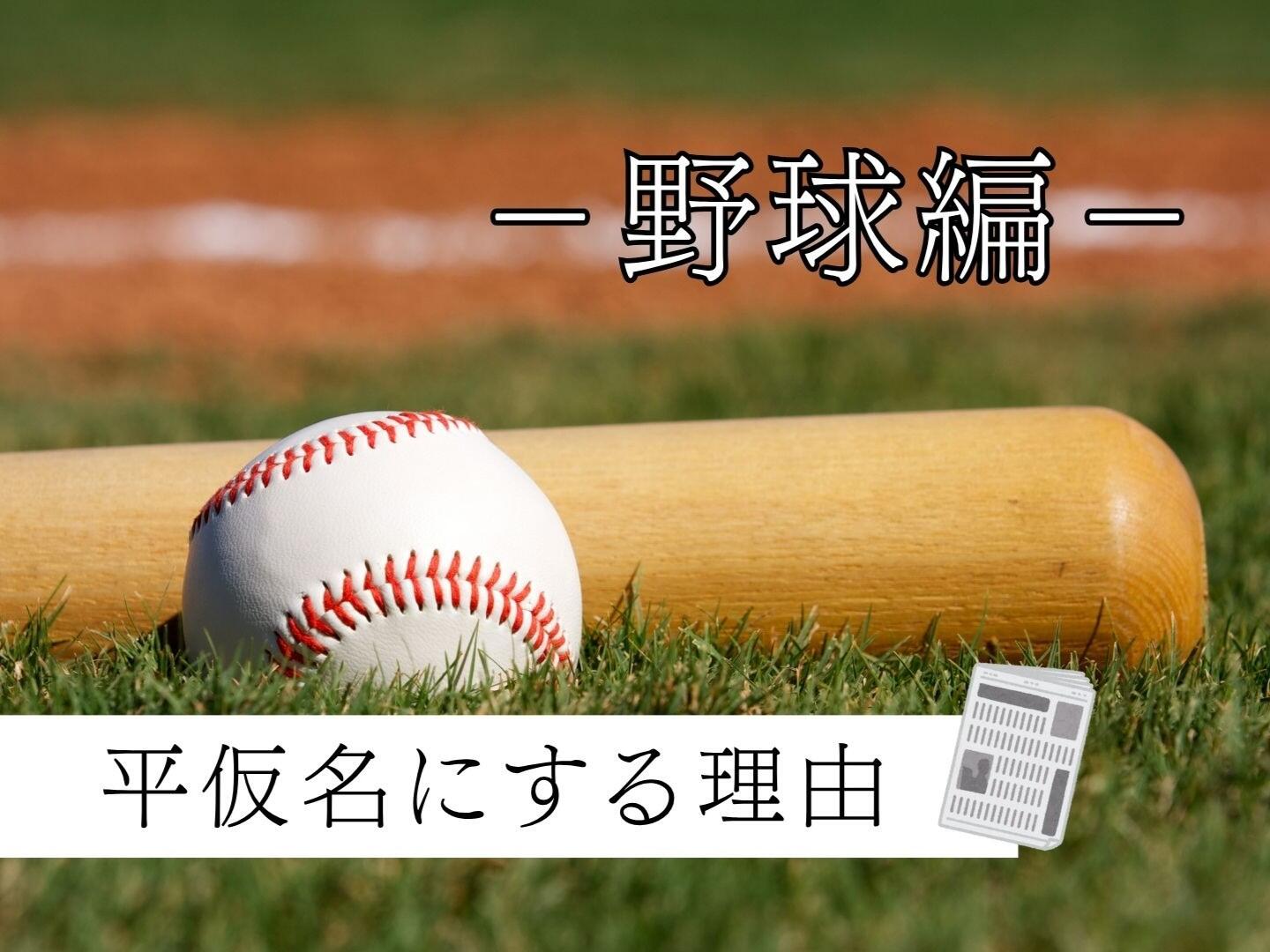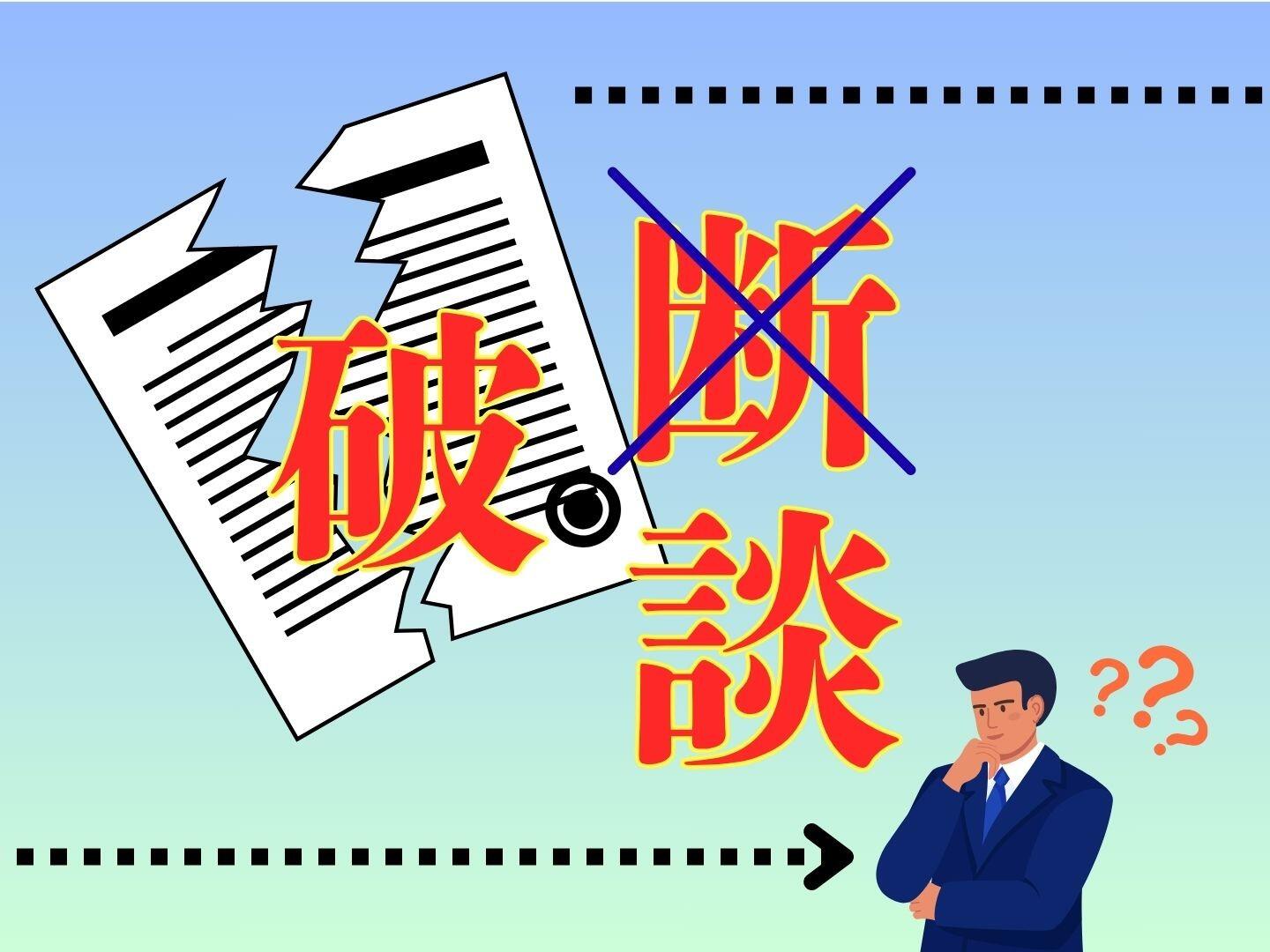新聞漢字あれこれ173 「奇」の読み方が気になります

著者:小林肇(日本経済新聞社 用語幹事)
「きしくも……」。6月の日曜日、テレビをつけたまま作業をしていたところ、アナウンサーの言い間違いと思われる音声が耳に入ってきました。少し気になって、後でネット検索をしてみると、SNS上に間違いを指摘する文言がいくつか見られました。
アナウンサーが読んだ原稿に「奇しくも」と書いてあったのでしょうか。これは「きしくも」ではなく、「くしくも」と読みます。形容詞「奇し」の連用形「くしく」に助詞「も」が付いたもので「不思議にも……」といった意味になります。私が見たSNSには「きしくもじゃない! くしくもだ! アナウンサーが間違えてどーする」と手厳しい言葉がつづられていました。不特定多数の人が視聴するテレビ番組だけに、誤読が気になった人が何人もいるようでした。
なぜ誤読をしてしまうのか。常用漢字表で奇の読みには「キ」の音しかないこと、「『奇なる縁』『奇をてらう』『事実は小説より奇なり』のように音読みを単独で用いる用法も、古めかしい響きがあるものの現役である」(『漢字ときあかし辞典』)こともあってか、「奇しくも」も「きしくも」と読むと思い込んでいる人がいるのでしょう。『放送で気になる言葉 2025』(日本新聞協会)では、読み方に迷いやすい言葉として「奇しくも」を取り上げ、「古風な言葉ではあるが、今もときおり使われる。『キシクモ』は誤り」と解説しています。
放送現場での読み間違いは致命的なことになりかねません。場合によっては視聴者に意味が正しく伝わらないことも出てきます。新聞などの文字媒体ならばそういうことはないと思われがちですが、さにあらず、新聞校閲の現場でもよくあること。記者が読み方を誤ったまま端末で入力すれば、間違った原稿ができあがってしまいます。新聞記事データベースで検索すると、日本経済新聞社の媒体で30年以上前の記事に3件ほど「きしくも」と書かれたものがありました。このときの校閲担当者が「きしくも」と読むものと思っていたのかは、今となっては確認のしようがありません。
連載の第155回で取り上げた「一段落」のように、「いちだんらく」を「ひとだんらく」と誤読して記事を入力したとしても、漢字で書かれてあれば問題は生じません。これが「きしくも」のように平仮名で表記されてしまえば、誤字としてさらされることになります。書き手もそうですが、校閲記者も常識を疑われます。平仮名1字で信頼が損なわれることもあるのです。
次回、新聞漢字あれこれ第174回は8月20日(水)に公開予定です。
≪参考資料≫
『NHK 日本語発音アクセント新辞典』NHK出版、2016年
『漢字ときあかし辞典』研究社、2012年
『大辞林 第四版』三省堂、2019年
『放送で気になる言葉 2025』日本新聞協会、2025年
≪参考リンク≫
「日経校閲X」 はこちら
≪おすすめ記事≫
新聞漢字あれこれ158 「脈絡」 脈略ではありません! はこちら
新聞漢字あれこれ82 誤読で起こるミスいろいろ はこちら
新聞漢字あれこれ44 コロナ渦の影響はいかに? はこちら
≪著者紹介≫
小林肇(こばやし・はじめ)
日本経済新聞社 用語幹事
1966年東京都生まれ。1990年、校閲記者として日本経済新聞社に入社。2019年から現職。日本新聞協会新聞用語懇談会委員。漢検漢字教育サポーター。漢字教育士。 専修大学協力講座講師。
著書に『マスコミ用語担当者がつくった 使える! 用字用語辞典』(共著、三省堂)、『方言漢字事典』(項目執筆、研究社)、『謎だらけの日本語』『日本語ふしぎ探検』(共著、日経プレミアシリーズ)、『文章と文体』(共著、朝倉書店)、『日本語大事典』(項目執筆、朝倉書店)、『大辞林第四版』(編集協力、三省堂)などがある。2019年9月から三省堂辞書ウェブサイトで『ニュースを読む 新四字熟語辞典』を連載。