「オリンピック」を「五輪」と表記した経緯とは?
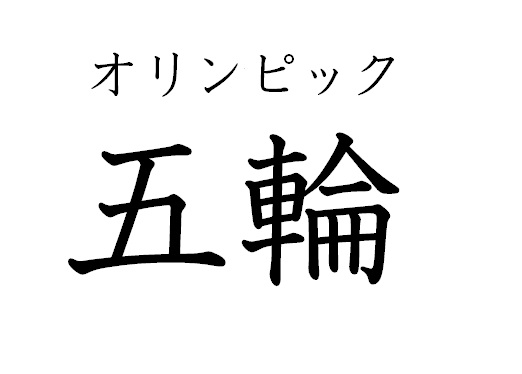
いよいよリオデジャネイロオリンピックも後半戦。ますます応援に熱が入ってきました。「漢字カフェ」でもオリンピックにちなんだ話をご紹介してきましたが、今日も懲りずにオリンピックの話題をご紹介したいと思います。
今日のテーマは「オリンピック」を「五輪」と表記した経緯について。
新聞やインターネットのニュースなどを見ていると、「リオ五輪」の表記をよく目にします。オリンピックシンボルが五つの輪をモチーフにしていることから、「五輪」=「オリンピック」であるとすんなり受け入れてきましたが、いつからこの表記が用いられているのか気になりました。
「五輪」は日本独特の表記!
「五輪」が漢字表記であることから中国発祥なのでは?と思ってしまいそうが、実は中国語とは全く関係がありません。中国語ではオリンピックのことを「奥林匹克運動会」と表記し、略して「奥運」または「奥運会」と表現することもあります。つまり、中国で「五輪」と表現しても通じません。さらに 『当て字・当て読み漢字表現辞典』(三省堂)の「オリンピック」の項目に「『五輪』はゴリンと読まれ、戦前に日本で新聞記者がスペースを節約するために造り出したもの」とあり、日本語独特の当て字表現であることがわかります。
では、いったい誰がどのようにして「オリンピック」を「五輪」と表記するようになったのでしょうか。
ヒントは宮本武蔵!?
初めて「五輪」という表記が用いられたのは、1936年(昭和11年)7月25日の「読売新聞」。1週間後に開幕するベルリンオリンピックで、前回大会開催地のアメリカ・ロサンゼルスから大会旗が届いたというニュースを「五輪旗・伯林(ベルリン)に着く」と三段見出しで伝えた記事が最初の「五輪」の使用例だそうです。当時、運動部の記者だった川本信正さんが、「オリンピック」では新聞の見出しに使うのに長すぎるため省略できないかと社内から相談を受けて考案しました。「国際運動」などの候補が挙がる中、「五輪」を思いついたのは宮本武蔵の『五輪書』の文字にヒントを得たからだそうです。
オリンピックシンボルの五つの輪には「五つの大陸」という意味以外にも五つの自然現象「水の青・砂の黄色・土の黒・木の緑・火の赤」を示しているという説があります。一方で、宮本武蔵の『五輪書』は、仏教で万物を構成するとされる五輪「地・水・火・風・空」になぞらえた五つの巻で成り立っています。「神秘的」という点では、古代ギリシャで行なわれていた神の祭典から発生したオリンピックと、古い時代からアジアを中心に広がった仏教と両者のイメージが重なっているようにも感じますね。
2020年の東京オリンピック招致が決定した2013年の「今年の漢字」第1位は「輪」でした。私たちは「輪」の字からも「オリンピック」をイメージするほど「五輪」という表現に慣れ親しんでいます。「五輪」の表記があるおかげで、私たちは新聞・ニュースなどでオリンピックのニュースをいち早く見つけることができるわけです。短くてイメージにあったわかりやすい、まさに素晴らしい発明と言えますね。
≪引用・参考文献≫
・「オリンピック」を「五輪」と表記したのは誰? 2012.7.24掲載
・読売ONLINE 「なぜオリンピックは「五輪」と言うの? 2016.7.5掲載










