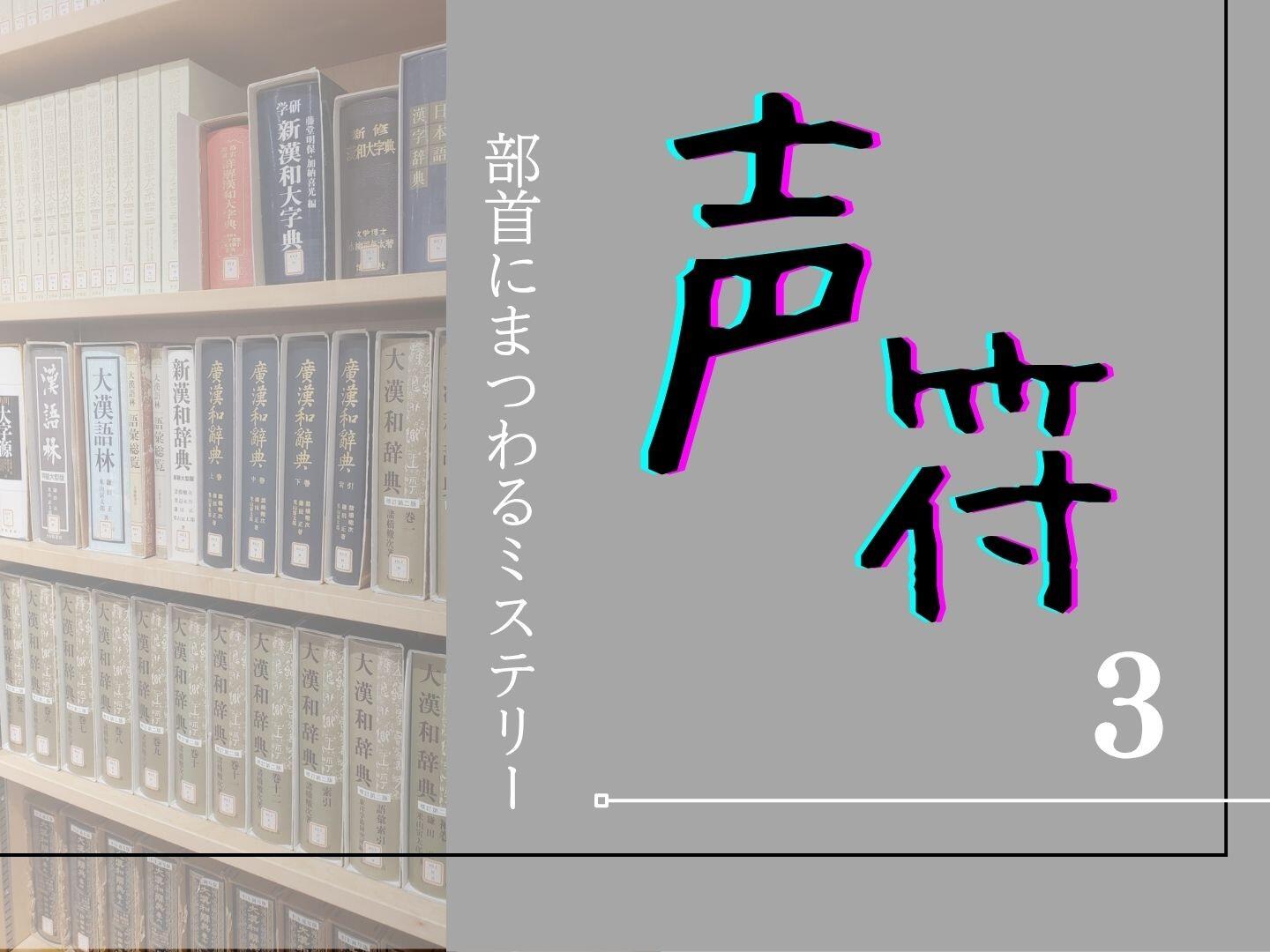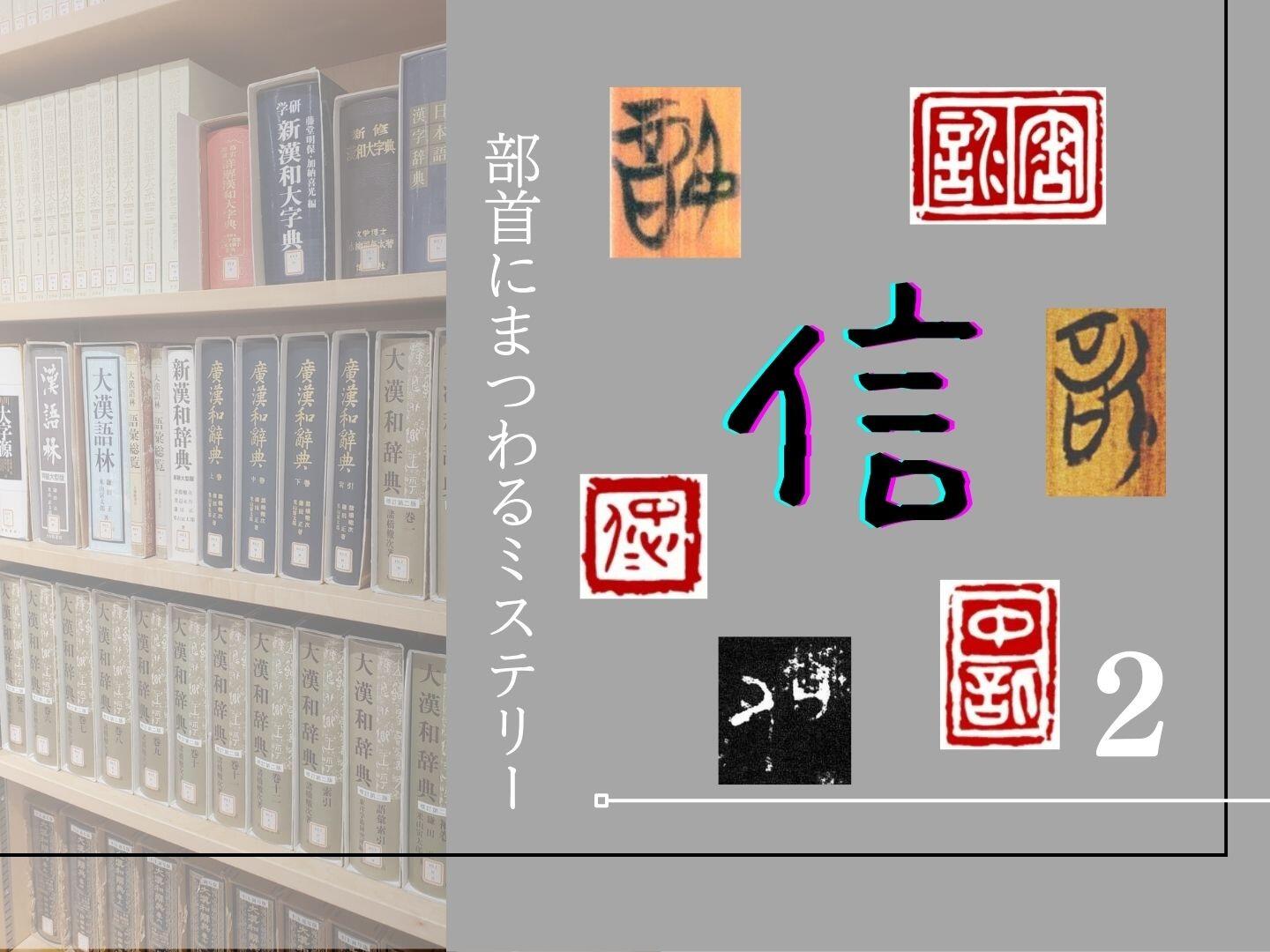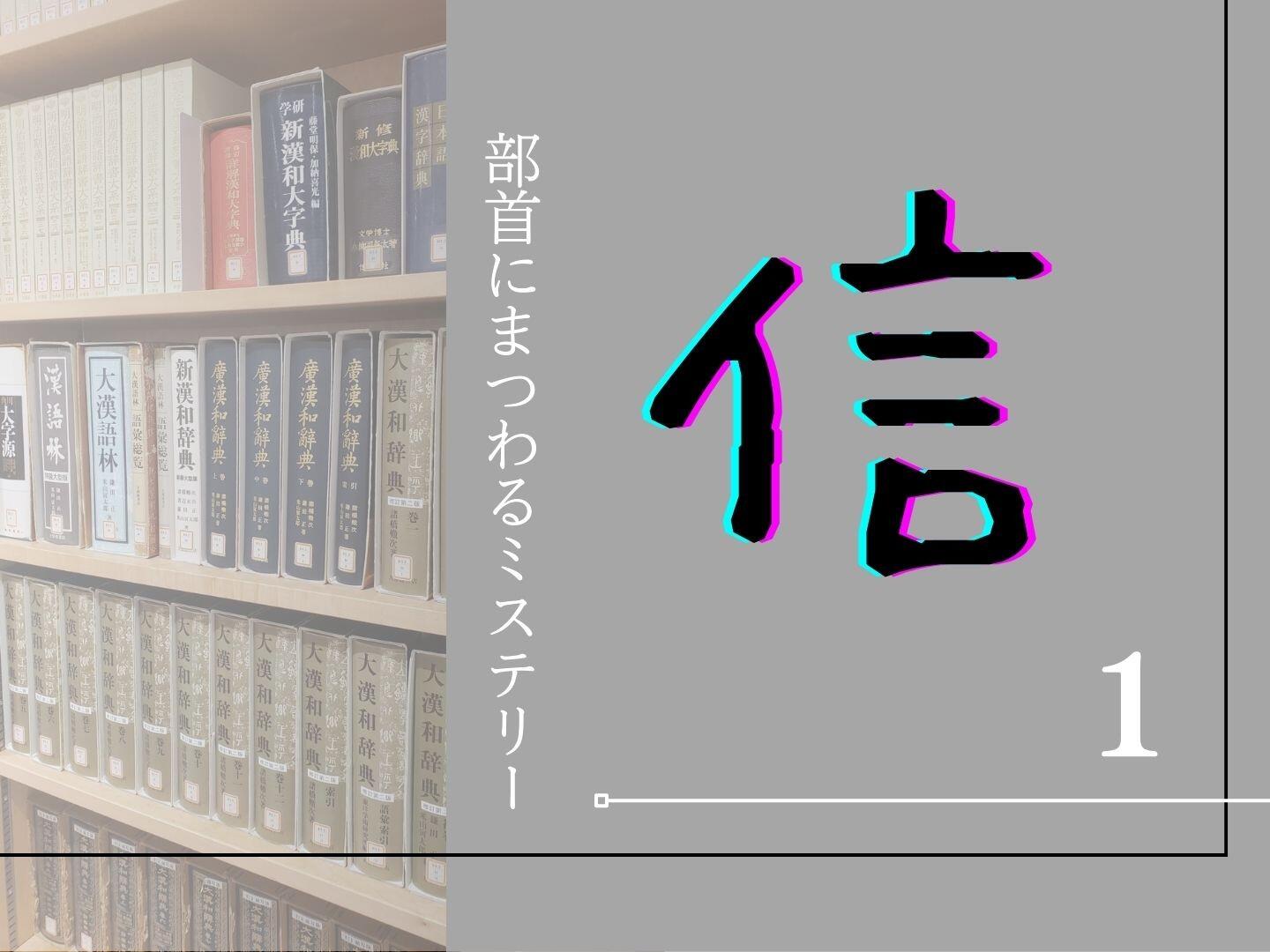あつじ所長の漢字漫談24 胸をしめつけられる漢字

著者:阿辻哲次(京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長)
毎年この時期になると、私はある一つの漢字を思いだして、胸が締めつけられる思いがします。
平成23年3月11日に、東北地方を中心に未曾有の大災害が襲いました。あれからもう7年が経とうとしていますが、原発の事故などもあって、復興はまだまだ厳しい状況にあります。災害で肉親を失われた方や、被災された方々にはまったく申しあげることばもありません。微力な個人ではなにもできませんが、一日も早い復興をお祈り申しあげます。
大震災の直後から、被災地のとんでもない被害の状況を報じる連日のニュースの中に、私には胸を締めつけられる漢字がひとつありました。それは「閖」という漢字です。
仙台市の南に位置し、仙台空港がある名取市の東部で、太平洋に面したところに「ゆりあげ」という名称の地域があって、漢字では「閖上」と書きます。「閖」はここ以外では使われない珍しい漢字ですが、この漢字が作られたいきさつについて、名取市のHPに掲載される「なとり100選」には次のように書かれています。
閖上の「閖」という文字は珍しく、辞書にもほとんど掲載されていません。この漢字が生まれたのは、仙台藩4代藩主・伊達綱村に由来があります。
綱村公は、大年寺山門からはるか東のゆり上浜を望み、こう言いました。「門の中に水が見えたので、門の中に水という文字を書いて『閖上』と呼ぶように」。ゆり上の「ゆり」の文字が「淘」から、この「閖」にあてられたと言われています。従来の漢字にはない日本で作られた文字(国字)です。
http://www.city.natori.miyagi.jp/natori100/019.htm
殿様のきまぐれといえば失礼ですが、まことにお気楽な話だといわざるをえません。山上にあるお寺の門から遠くに海岸が見えるところなど、ここだけに限らず、日本全国いたるところにありますが、この殿様のデンでいけば、そこはすべて「閖」という字で表されることになるはずです。
しかし恐れ多くも殿様から漢字を賜った住民には「まことにありがたき幸せ」で、「閖」はこうしてこの海岸を意味する地名として使われることとなりました。もともとはその地域だけで使われる、笹原宏之先生が命名された「方言漢字」にすぎなかったものが、明治になって戸籍が作られた時にこの漢字は全国区になりました。たとえばこの地域に暮らしていたAさんが京都の祇園に引っ越ししたら、祇園のある京都市東山区の区役所はAさんの転入届に「宮城県名取市閖上から転入」と書かねばならず、この段階で「閖」という漢字が宮城県名取市以外の場所でも使われることになります。こうして「閖」が全国で必要な漢字になったので、この漢字が「JIS漢字」第2水準に収録され、みなさんがお使いの携帯電話やスマホでも簡単に表示できるようになりました。
殿様の一時的な興趣から作られた漢字が、国家規格にまで取りこまれた事実に興味をもった私は、いまから15年ほど前に、この漢字を見るためだけに閖上に出かけたことがありました。
JR名取駅からタクシーに乗りました。閖上は魚がおいしくて、特に赤貝が名産、東京の寿司屋で出される上質の赤貝はほとんどここのものだ、という話を運転手さんから聞きながら15分ほど走ると、そこが閖上漁港でした。時刻はお昼前で、競りも出荷もすんだ漁港は静かで、まわりにはひなびた漁村がひろがっていました。
お昼ご飯に、港近くのお寿司屋さんで特産の赤貝を堪能し、ふたたびタクシーで駅に戻る途中に「閖上中学校」があったのでちょっと立ち寄ってもらいました。「閖」という漢字が書かれた校門や門札などを写真に撮っていると、運転手さんが不思議そうな顔で「この漢字そんなに珍しいかねぇ。私ら子どものころから見慣れているけどねぇ」とつぶやいたのが印象的でした。
駅まで戻る車内でも、最近近くに大形スーパーができたので、このあたりにもたくさんの人が来るようになったとか、赤貝がお好きだったら通販でも買えますよとか、話し好きの運転手さんがいろいろ楽しませてくれました。
その閖上が、想像を絶する津波によって壊滅的な被害を受けたというニュースを見た時、私は涙が止まりませんでした。テレビに映る閖上漁港は目を疑うほどの膨大なガレキの山と化し、被災された方々が厳しい寒さのなかを着の身着のままで避難されていたのは、私が写真を撮らせていただいた閖上中学校の校舎でした。ニュースは同校の生徒さんが14名も遭難されたとの痛ましいことを告げ、また学校の建物も甚大な被害を受けたけれども、多くの人の避難所として使われていると伝えていました。
その閖上を、私は昨年にようやく再び訪れることができました。閖上だけでなく、被災地はまだまだ前途多難でしたが、それでも復興は着実に進められており、あのとき避難所として使われた中学校は、その後近くに移転してしばらく仮校舎で運営されていましたが、平成30年から、新しい場所に校舎を建てて、あらたに名取市立閖上小・中学校という小中一貫校として開学するとのことです。
現地の人々の台所であった魚市場は、漁港から場所を移して、仮設店舗ではあるものの、新鮮な魚や貝を販売する「閖上さいかい市場」として再開されていました。商店に並ぶ品揃えもかなり豊富で、おかげで私も久しぶりに閖上の赤貝などの海産物を味わうことができました。
珍しい漢字にひかれて訪れただけがご縁の街でしたが、復興は着実に進んでいると感じられました。すばらしい街のファンとして、一日も早い完全な復興を心から願っています。
≪著者紹介≫

阿辻哲次(あつじ・てつじ)
京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長
1951年大阪府生まれ。 1980年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。静岡大学助教授、京都産業大学助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。文化庁文化審議会国語分科会漢字小委員会委員として2010年の常用漢字表改定に携わる。2017年6月(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所長就任。専門は中国文化史、中国文字学。人間が何を使って、どのような素材の上に、どのような内容の文章を書いてきたか、その歩みを中国と日本を舞台に考察する。
著書に「戦後日本漢字史」(新潮選書)「漢字道楽」(講談社学術文庫)「漢字のはなし」(岩波ジュニア新書)など多数。また、2017年10月発売の『角川新字源 改訂新版』(角川書店)の編者も務めた。
●『角川新字源 改訂新版』のホームページ
![]()
≪記事写真・画像出典≫
・記事上部画像:閖上さいかい市場 著者撮影
・記事中画像:閖上中学校 同上
閖上の赤貝 同上