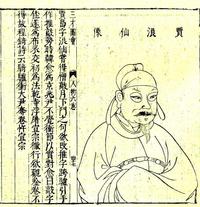あつじ所長の漢字漫談28 お坊さんと「すいこう」

著者:阿辻哲次(京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長)
京都のど真ん中祇園にある漢字ミュージアムの近所には、建仁寺や知恩院、さらには清水寺など有名なお寺がたくさんあって、桜や紅葉の季節には、近ごろは特に外国からのお客さま中心に、毎日ものすごい数の人が訪れます。 観光地の近くだけでなく、京都にいると、ふだんの生活でもなにかにつけてお寺が意識されますので、しばらく前にこの欄で「寺」という漢字を取りあげ、さらにこの間はお釈迦さんの誕生日「花祭り」にちなんで、「卍」という漢字を取りあげました。ここまで仏教にからんできたいきさつもあって、今回は「僧」という漢字を考えて見ることとしました。
仏教といえばお坊さん、つまり僧侶ですが、「僧」は古い文献では仏教関係のもの以外にはほとんど見えない漢字で、中国最古の字典である後漢の許慎『説文解字』にも、見出しの漢字としては収録されていません。しかしのちに仏教が中国に浸透するにつれて、一般的にも重要な漢字と認識されてきたのでしょう、北宋時代に徐鉉(じょげん、916-991年)という人が『説文解字』の本文を校訂した時に、それまで収録されていなかった漢字を追加した文字(「新附字」といいます)の中に「僧」があって、そこに
僧は、浮屠の道人なり
と記されています(八篇上「人」部末尾)。
ここにいう「浮屠」(ふと、また「浮図」とも書かれます)は、梵語(サンスクリット語)Buddhaの音訳で、Buddhaはブッダですから仏さまのことですが、そこから意味がひろがって、仏教に関する全般的なことを表します。「僧」とはその「浮屠」の「道人」すなわち仏教での修行者のことだというわけです。字の構成は意味を表す《人》と、発音を表す《曾》を組み合わせた、ごく単純な形声文字にすぎません。
仏教の修行者をこのように「僧」という漢字で表すのは、サンスクリット語のサンガの音訳語「僧伽」(そうぎゃ)の省略形であることによるのだそうです。仏教の研究書によれば、サンガはもともと「団体」を意味することばだったそうですが、後に仏教に帰依して自ら修行し、その教えを伝道する出家者の教団を指すようになりました。正式には四人以上の修行者が集った組織を「僧伽」と呼んだようですが、日本では一人のお坊さんをも「僧」、あるいは「僧侶」と呼んでいます。いずれにせよ僧はサンスクリット語からの音訳で、そのことは『魏書』の「釈老志」という仏教関係の文献に「沙門と謂い、或いは桑門と曰う、また声相い近し、すべてこれを僧というは、皆な胡の言なり」と記されている通りです。
この「僧」という漢字にまつわることばの一つに、「推敲」があります。「推敲」と漢字で書くとなんのことかわからないかもしれませんが、小学校の国語の授業で作文を課せられた時からあとずっと、いやというほど耳にしてきた「すいこう」を漢字で書くと、「推敲」となるのです。
「すいこう」すなわち「推敲」とは、詩や文章をよりよいものにするために何度も文章を練り直すことをいいますが、それはもともと唐代のある詩人の苦吟から生まれたことばでした。
唐の時代に賈島(かとう 779-843)という詩人がいました。この詩人は筆が遅く、作品がなかなか形にならないことで知られていましたが、ある時突然に、ちょっといい対句のフレーズが浮かびました。
それは、
鳥宿池中樹 鳥は宿る 池中の樹
僧推月下門 僧は推す 月下の門
というものでした。
しかし苦吟するタイプの彼は、「推す」という所を「敲(たた)く」とした方がいいのではないかとも考えました。「推す」も捨てがたいが、「敲く」には視覚的な効果のみならず、音楽的な響きもある……。どちらがいいかと考えながら馬に乗っていると、向こうから政府高官の行列がやってきました。高官の行列がきたら、一般人は道端に寄って通り過ぎるのを待たなければいけないのですが、しかし彼は詩作に夢中でそれに気づかず、とうとう高官の行列と衝突してしまいました。
この無礼者め! と詩人はたちまち取り押さえられ、高官の前に連れて行かれました。詩人は頭を深々とさげ、「申し訳ありません。つい考えごとをしておりまして…」 とわびたところ、この高官が実は韓愈(かんゆ)という、のちに唐代を代表する名文家の一人にも数えられる、きわめて高名な人物だったのです。
韓愈はそのころ長安の知事を務めていましたが、かねてより高名な詩人でもあり、詩作にふけったあまり行列にぶつかった若き詩人と、たちまち詩の話に花が咲きました。
賈島はさっそく苦吟中の詩について、「推す」がよいか「敲く」がよいかを韓愈にたずね、しばらく考えた韓愈が、「『敲』がベターであろう」と答えました。
この賈島の「推」と「敲」の文字遣いの逡巡から、のちに「推敲」ということばが生まれました。小学校の国語の授業でも習うこのことばは実は非常に古い来歴があるものなのですが、「敲」が当用漢字にも常用漢字にも入らず、もちろん小学校で学習する漢字ではないので、ひらがなで「すいこう」と書かれるようになり、おかげで学生はもちろん、作文を指導するほとんどの国語の先生たちにも、なんのことやらさっぱりわからない用語になってしまいました。
ところでこの時に「僧」が「推したり敲いたり」したのは、いったいだれの家の門だったのでしょうか。この時代の僧は飲酒も妻帯を認められていませんでしたから、居酒屋でもガールフレンドの家でもなかったことは確実です。
≪参考リンク≫
漢字ペディアで「推敲」を調べよう
漢字ペディアで「僧」を調べよう
≪著者紹介≫

阿辻哲次(あつじ・てつじ)
京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長
1951年大阪府生まれ。 1980年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。静岡大学助教授、京都産業大学助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。文化庁文化審議会国語分科会漢字小委員会委員として2010年の常用漢字表改定に携わる。2017年6月(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所長就任。専門は中国文化史、中国文字学。人間が何を使って、どのような素材の上に、どのような内容の文章を書いてきたか、その歩みを中国と日本を舞台に考察する。
著書に「戦後日本漢字史」(新潮選書)「漢字道楽」(講談社学術文庫)「漢字のはなし」(岩波ジュニア新書)など多数。また、2017年10月発売の『角川新字源 改訂新版』(角川書店)の編者も務めた。
●『角川新字源 改訂新版』のホームページ
![]()
≪記事写真・画像出典≫
記事上部:マツ / PIXTA(ピクスタ)
記事中:『説文解字』の「僧」 汲古閣刊本
賈島の図 『三才圖會』