四字熟語根掘り葉掘り12:「快刀乱麻」の解決を求む!
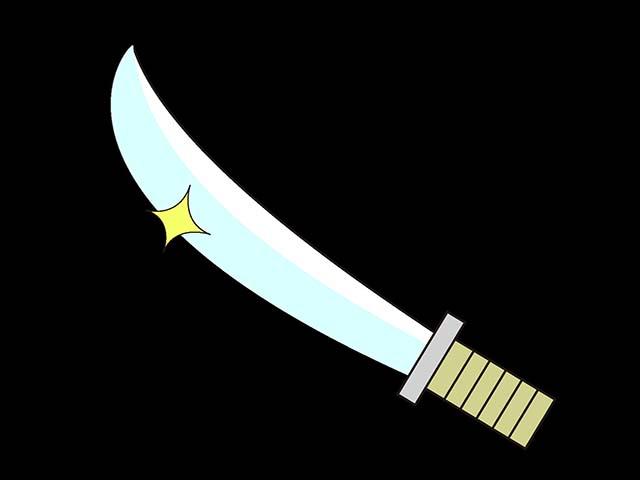
著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)
四字熟語の中には、中国の古い本に出て来るお話から生まれたものが、たくさんあります。そこで、四字熟語の辞典を作るとなると、そういうお話についてきちんと調べることも、重要な作業となります。
ただ、元のお話がはっきりしている四字熟語ばかりとは限りません。中には、それらしい話がいくつかあるものの、どれとも決めかねるものもあります。その最たるものは、「快刀乱麻(かいとうらんま)」でしょう。
この四字熟語は、「快刀、乱麻を断つ」の略。〈切れ味のいい刀で、もつれた麻を断ち切ってしまう〉ところから、〈困難な問題を思い切った手段で鮮やかに解決する〉ことのたとえとして使われます。
このことばの元になったものとして取り上げられるお話は、私の知っている限りでも、4つあります。
1つめは、現在では断片的にしか残っていない、ある歴史書に出て来るもの。1世紀、後漢王朝に仕えたある人物が、「乱糸」つまり〈もつれた糸〉をほどくように命じられて、刀でそれを断ち切っています。
2つめは、中国の正式の歴史書の1つに出て来るもの。6世紀、ある豪族が、息子たちに「乱糸」をほどかせたところ、ある息子だけが刀ですぱっと切りました。1つめと似たようなお話ですが、こちらには、この子がやがて成長して皇帝の座に就いた、という後日談があります。
3つめは、12世紀の大慧宗杲(だいえそうごう)という禅僧の語録から。そこでは、悟りを開いた瞬間のことを、やはり「乱糸」が刀で断ち切られたようだ、と表現しています。
最後だけはちょっと毛色が違って、紀元前4世紀の西アジアでの話。ゴルディオンという町で、「これをほどいた者はアジアの王となるであろう」という予言の伝わる複雑な結び目を、かのアレクサンドロス大王が剣ですぱっと断ち切った、というお話です。
「快刀、乱麻を断つ」という表現そのものは、近代になって使われるようになったものなので、どれが元のお話であっても、おかしくはありません。なおかつ、どのお話にも、断ち切られたのが〈麻〉だとは出て来ないのが、困ったところ。もしかすると、この4つ以外のお話があるのかもしれません。
諸説入り乱れている「快刀乱麻」の元ネタ問題。どなたか、鮮やかにこれを解決してくださる方は、いらっしゃいませんでしょうか……?
≪参考リンク≫
≪著者紹介≫
円満字二郎(えんまんじ・じろう)
フリーライター兼編集者。
1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。
著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)など。
また、東京の学習院さくらアカデミー、名古屋の栄中日文化センターにて、社会人向けの漢字や四字熟語の講座を開催中。
●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/
≪記事画像≫
著者作成










