四字熟語根掘り葉掘り21:「百発百中」を逆手に取ると……
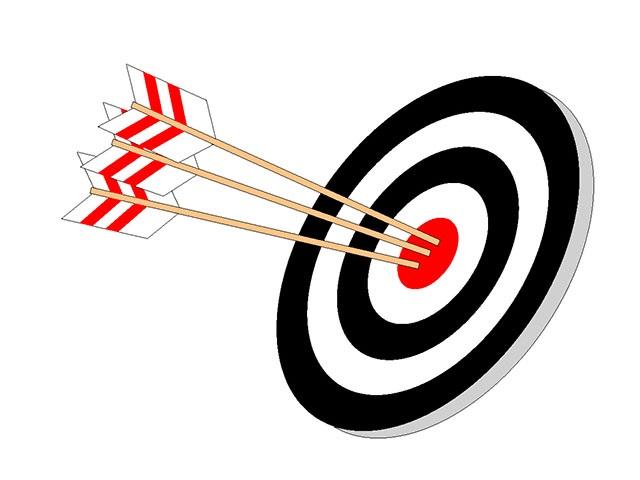
著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)
四字熟語というと、古めかしくて重厚なことばだというイメージがありませんか?
たしかに四字熟語の中には、中国の古典に由来する、1000年以上にわたる長い歴史を持つことばが少なくありません。また、漢字ばかりが4つ並び、多くはそれがすべて音読みで読まれるところから、むずかしそうで、硬い響きを持つことが多いのも、事実です。
ただ、現在では、四字熟語をもっと生き生きと、軽快に使っている例も、よく見られます。
たとえば、「百発百中」。これは、紀元前数百年という大昔の中国で活躍した、伝説的な弓の名人にまつわるお話から生まれた四字熟語。なんでも、この名人、150メートルも離れたところから柳の葉っぱをめがけて矢を放って、「百発百中」だったというから、ものすごい腕前です。
ここから、「百発百中」は、〈ねらったことが、必ずその通りになる〉ことを意味するようになりました。弓や射撃だけでなく、競馬の予想やクイズの解答に至るまで、人並み外れた正確さを強調するために使われるのが、ふつうです。
ところが、現代の人気作家、有川浩さんは、それとはちょっと違った用い方をしています。たとえば、『図書館戦争』の主人公、笠原郁(かさはら・いく)は、子どものころ、兄たちと一緒に暴れ回る一方で、読書が大好きな少女でした。そこで、
「小学校の六年間は、郁が教室で本を読んでいると級友から百発百中「似合わない」と声がかかった。」
となるわけですが、この「百発百中」は、郁の読解力の正確さを表しているわけでもなければ、級友の洞察力の鋭さを表現しているわけでもありません。〈ねらったことが、必ずその通りになる〉という意味を強調する「百発百中」の特徴を逆手に取って、〈本人がねらっているわけでもないのに、必ずそういう結果になってしまう〉ことを、ユーモラスに描き出しているのです。
四字熟語とは、長い歴史の中を受け継がれてきた、表現力の高いことばです。その表現力の高さをうまく生かすことによって、文章に新しい魅力を付け加えることができるのです。
私が、文章表現としての四字熟語にポイントを置いた辞書を作りたいと考えたのは、そこに理由があります。その拙著、『四字熟語ときあかし辞典』(研究社)が、いよいよ10月18日に発売になります。ぜひとも書店で手に取って、ご覧いただけたらと願っています。
≪参考リンク≫
≪著者紹介≫
円満字二郎(えんまんじ・じろう)
フリーライター兼編集者。
1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。
著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)など。
また、東京の学習院さくらアカデミー、名古屋の栄中日文化センターにて、社会人向けの漢字や四字熟語の講座を開催中。
●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/
≪記事画像≫
筆者作成










