四字熟語根掘り葉掘り27:おめでたいのは「千里同風」
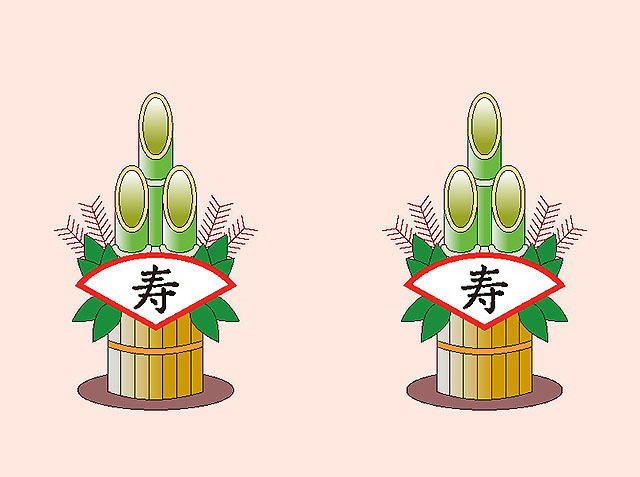
著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)
みなさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。
さて、年賀状によく使われる四字熟語といえば、もちろん「謹賀新年」。もっとも、このことばを載せている四字熟語辞典を私は見たことがありません。あまりにもありふれていて、わざわざ意味を説明するまでもないからでしょう。
ただ、昔は、「千里同風(せんりどうふう)」という四字熟語も、年賀状でよく使われたようです。日本の民俗学の父、柳田国男は、『年中行事覚書』(講談社学術文庫)という著書の中で、次のように述べています。
「私などの小学校にいる頃までは、年始状には必ず千里同風という言葉を使わせられた。」
柳田国男は、1875(明治8)年の生まれですから、小学校のころというと、明治10年代の後半。当時の小学生はずいぶんおカタい年賀状を書いていたものですね。それとも、彼の育った環境が、特別だったのでしょうか。
その後、1913(大正2)年に、「詩歌之助」なる謎の人物が刊行した『筆伝墨語 僕が手紙』(田中宋栄堂)という本があります。その中に、「千里同風とは、能(よ)く正月の賀状に書く句に候」という一節があるということは、この当時も、「千里同風」は年賀状で人気のある四字熟語だったのでしょう。
実際、大正時代に出版された手紙の書き方の本を調べてみると、年賀状の文例として、「千里同風」を含むものがけっこうな頻度で見つかります。たとえば、
「新年の御慶(ぎょけい)、千里同風、目出度く申し納め候。」
というのが、その典型的なパターンです。
「千里同風」の「千里」とは、〈広い世の中、どこでも〉という意味。「風」は、ここでは「風俗」のことで、「同風」とは、〈生活習慣が同じである〉こと。「千里同風」で、〈どこでも同じようなことが行われている〉ことを指して使われます。
つまり、「新年の御慶、千里同風、目出度く申し納め候」というのは、〈新年のよろこびはどこでも同じですね、「おめでとう」と申し上げます〉といった意味なのでしょう。年賀状で使われる「千里同風」には、遠く離れた相手と同じよろこびを分かち合いたい、という気持ちが込められているように思われます。
手紙の書き方の本で見る限り、昭和に入ると、「千里同風」を年賀状に用いる習慣は、廃れていったようです。おそらく、「千里同風」の4文字だけでは、そこまでの意味をくみ取ることがむずかしく感じられるようになったのでしょう。
とはいえ、私たちは、めったに会うことのできない相手のことを思う気持ちを失ってはいないか、振り返ってみる必要がありそうです。
≪参考リンク≫
≪著者紹介≫
円満字二郎(えんまんじ・じろう)
フリーライター兼編集者。
1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。
著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)など。
また、東京の学習院さくらアカデミー、名古屋の栄中日文化センターにて、社会人向けの漢字や四字熟語の講座を開催中。
ただ今、最新刊『四字熟語ときあかし辞典』(研究社)に加え、編著の『小学館 故事成語を知る辞典』が好評発売中!
●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/
≪記事画像≫
筆者作成










