四字熟語根掘り葉掘り32:乾杯の歌と「比翼連理」
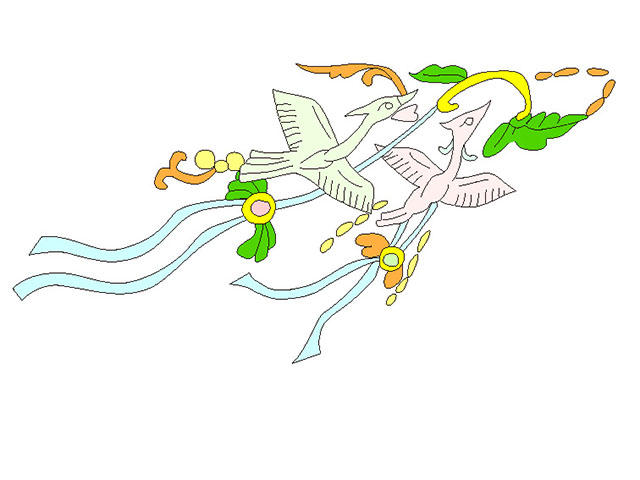
著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)
イタリアの作曲家、ヴェルディのオペラ『椿姫』に、「乾杯の歌」と呼ばれる有名な曲があります。ヒロインのヴィオレッタが開いたパーティーで、彼女に恋するアルフレードが高らかにうたう歌。日本でも、披露宴の乾杯の際などにBGMとして使われることがあります。
しかし、それはいけない、という人もいます。なぜなら、『椿姫』は、一度はアルフレードとの愛に生きようとしたヴィオレッタが、やがて別れさせられ、さみしく死んでいくという悲劇だから。縁起がよくない、というわけです。
「比翼連理(ひよくれんり)」についても、同じようなことがいわれることがあります。これは、8〜9世紀の中国の詩人、白楽天の『長恨歌(ちょうごんか)』という物語詩に出て来る、次のような一節に基づく四字熟語です。
天に在りては願わくは比翼の鳥と作(な)り
地に在りては願わくは連理の枝と為(な)らん
「比翼の鳥」とは、〈いつも並んで飛ぶ、仲がいいつがいの鳥〉。この2羽は、胴体がくっついているともいいます。一方、「連理の枝」とは、〈くっついて木目がつながってしまった2本の枝〉のこと。ここから、「比翼連理」は、〈いつまでも結びついて離れないほど、深い愛情〉のたとえとして用いられるようになりました。うるわしい四字熟語ですよね。
でも、『長恨歌』は、絶世の美女、楊貴妃の悲恋を描いた作品。皇帝の愛を得て人も羨む暮らしをしていた彼女は、突如、起こった反乱に巻き込まれて命を落とします。そこで、「比翼連理」を披露宴のスピーチなどで使うのは、不吉だとされることがあるのです。
私も、拙著『四字熟語ときあかし辞典』ではそんな解説をしたものでした。ところが、先日、TBS系のテレビ番組、『世界くらべてみれば』を見ていて、そんなことまで気にすることはないのかなあ、という気になってきました。
番組では世界のパワースポットを取り上げていて、イタリアのヴェローナにある、ジュリエットの家が紹介されていました。恋愛成就にご利益あり、というわけですが、『ロミオとジュリエット』といえば悲劇も悲劇、最後には二人とも死んでしまうじゃないですか!
にもかかわらず、ジュリエットの家には、世界中から観光客が押しかける。中には、そこでプロポーズをしたというカップルまで! このお二人、行く末は大丈夫かいな、と余計なことが心配になってきました……。
音楽であれ四字熟語であれ、その表現力が強ければ、元になったお話を離れて広く使われるようになっていくもの。縁起なんて、気にしなくていいのかもしれないですね。
≪参考リンク≫
≪著者紹介≫
円満字二郎(えんまんじ・じろう)
フリーライター兼編集者。
1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。
著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)など。
また、東京の学習院さくらアカデミー、名古屋の栄中日文化センターにて、社会人向けの漢字や四字熟語の講座を開催中。
ただ今、最新刊『四字熟語ときあかし辞典』(研究社)に加え、編著の『小学館 故事成語を知る辞典』が好評発売中!
●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/
≪記事画像≫
並んで飛ぶ鳳凰(『唐代図案集』より筆者作成)










