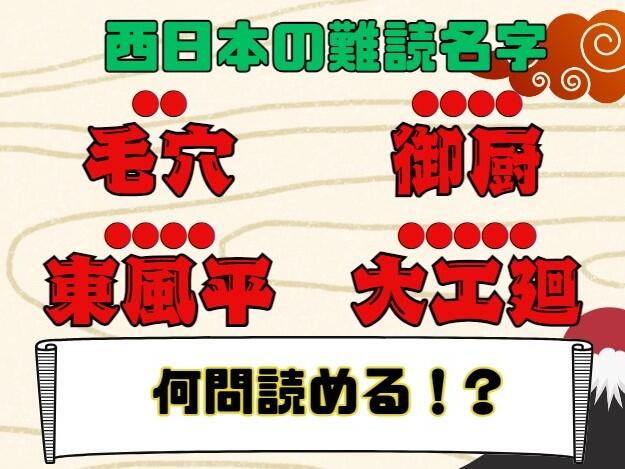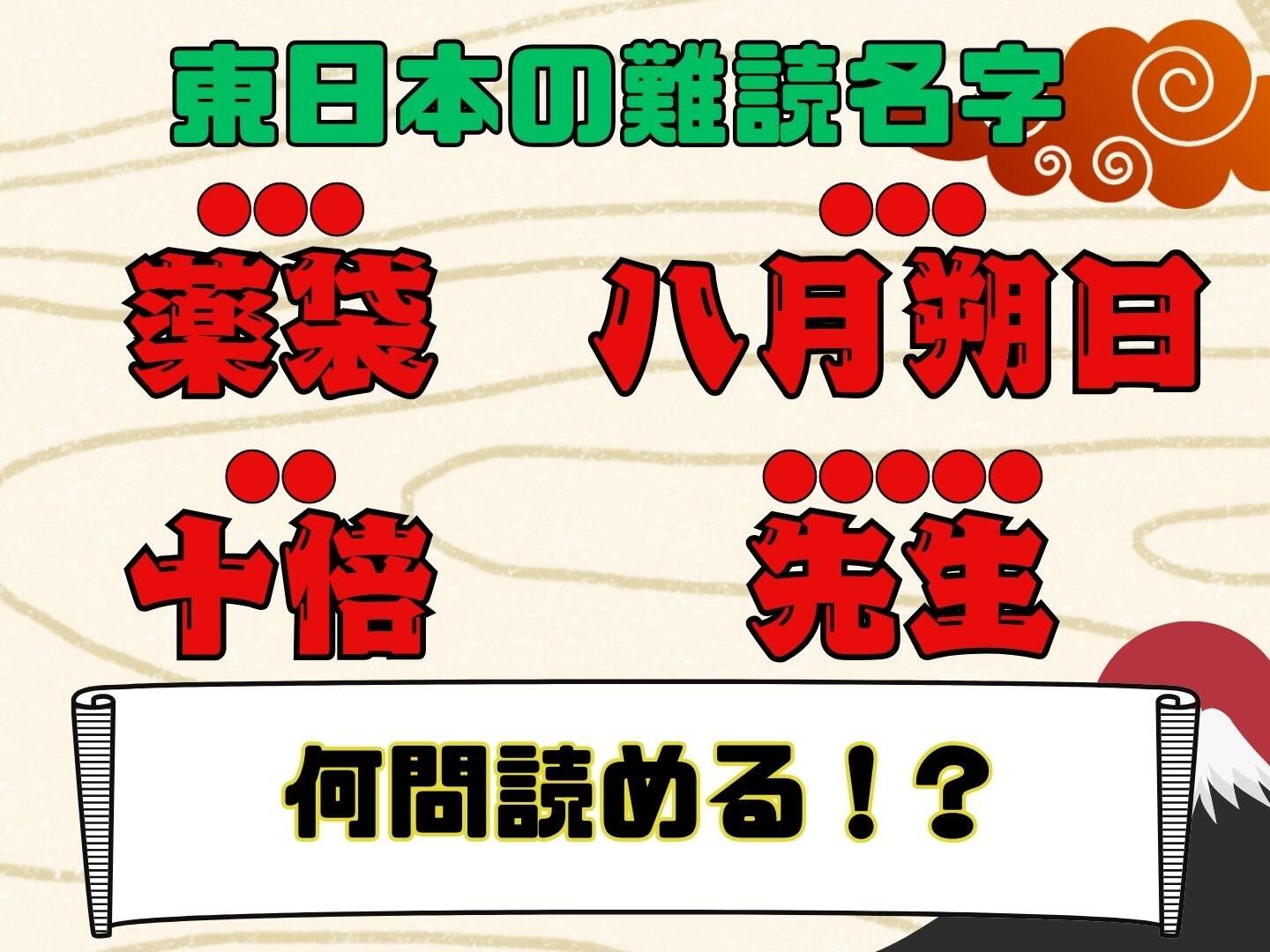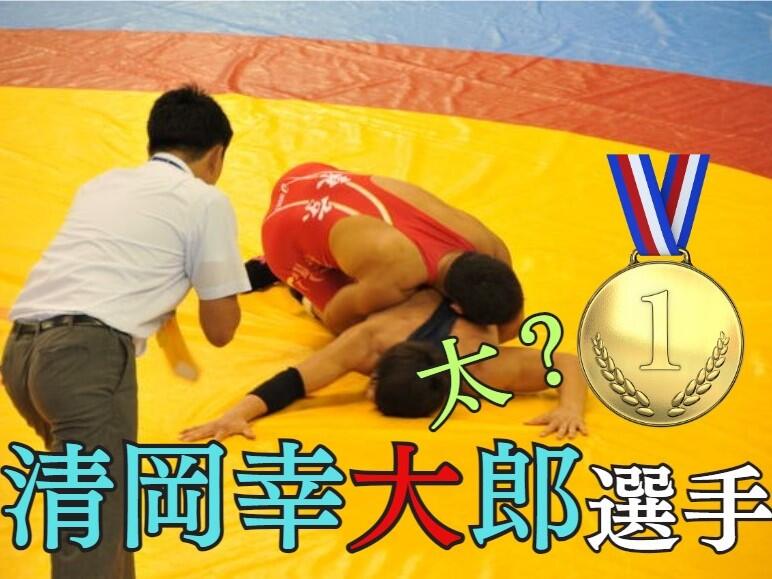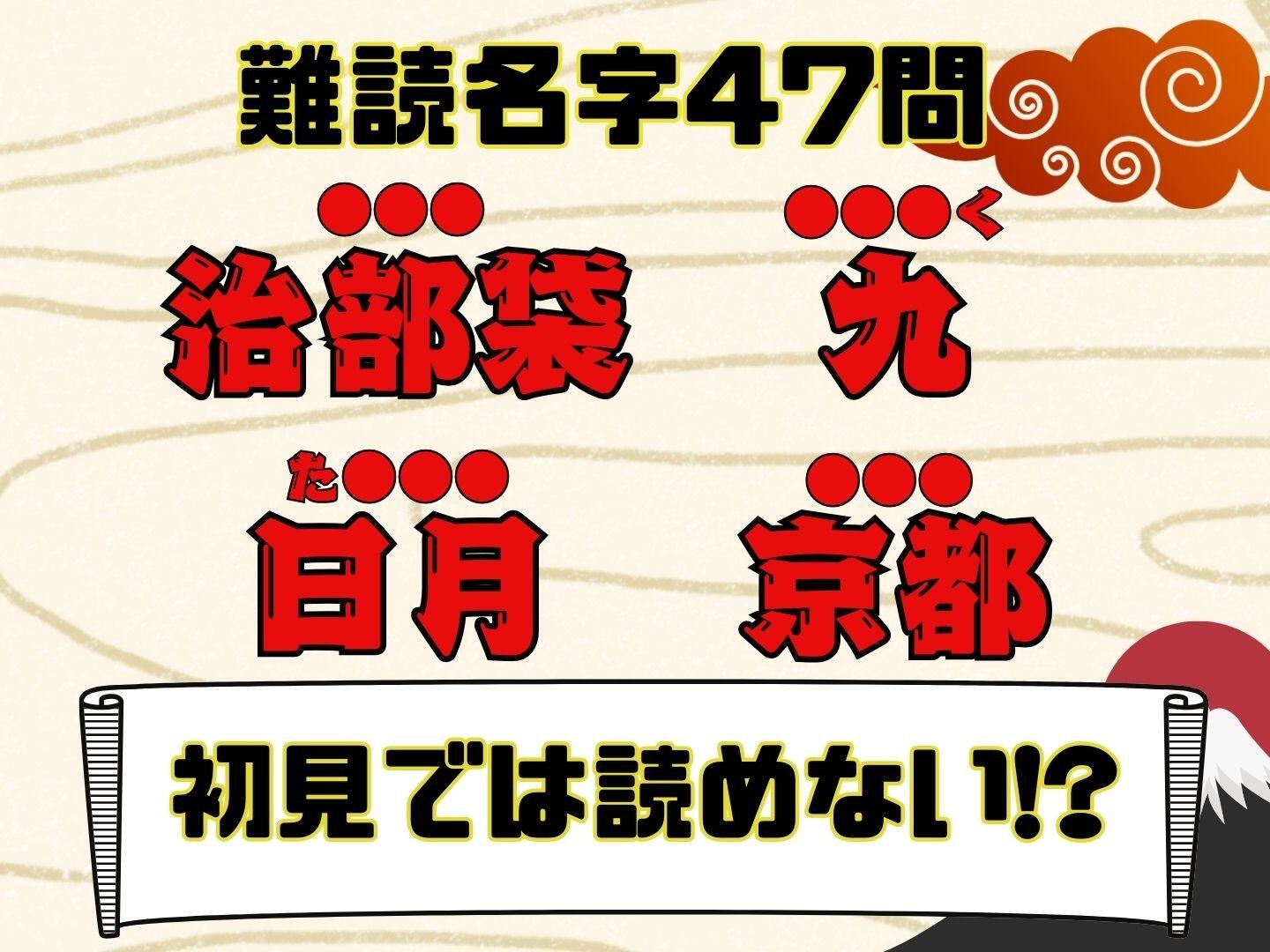新聞漢字あれこれ25 誤字ではなかった――「謎の漢字」を追って<前編>

著者:小林肇(日本経済新聞社 用語幹事)
笹原宏之・早稲田大学教授の著書『謎の漢字』の中に「![]() 」という字が出ています。これは作曲家・山田耕筰の「耕」の字の誤字の例として紹介されたものなのですが、2017年春の叙勲受章者の中にこの字を使った名前の方がいたのです。実在した謎の漢字――。
」という字が出ています。これは作曲家・山田耕筰の「耕」の字の誤字の例として紹介されたものなのですが、2017年春の叙勲受章者の中にこの字を使った名前の方がいたのです。実在した謎の漢字――。
『謎の漢字』では、「山田耕『筰』の秘密」として、「山田耕作」から「山田耕筰」への改名のエピソードが紹介されています。指揮棒を振る山田が後頭部の髪が少なくなったことを知人から指摘されたことから、せめて名前の上にカツラを着せてみようかと、『康熙字典』から見つけ出したのが「筰」という字。「作」に「毛」すなわち「ヶ」を2つ加えたもので、初めはペンネームとして用い、1956年の再婚を機に戸籍上も「耕筰」に改められました。そんな思いで行われた改名も、もとの「耕作」のままにされたりするなど間違われることが多かったようで、笹原教授も「実際に、竹冠の位置が見事に前方にずれた新しい字体によって、その名が印刷されたパンフレットも目撃したことがある」(同書)といいます。
「山田耕筰」の誤字というだけで正しい字としては存在しないものだと思われた「![]() 」の字を持つ名前の人が実在すると分かったのは2017年7月のことでした。そのころ、笹原教授にお会いした際に「今年はこんな外字を採集しています」とリストを渡したところ、後日「
」の字を持つ名前の人が実在すると分かったのは2017年7月のことでした。そのころ、笹原教授にお会いした際に「今年はこんな外字を採集しています」とリストを渡したところ、後日「![]() という、小著に書いた字が出てきていてびっくりしました。山田耕筰からの何らかの影響があったのか、とても気になっております」というメールが届きました。私は『謎の漢字』を読んでいたのにもかかわらず、恥ずかしながら指摘されるまで「
という、小著に書いた字が出てきていてびっくりしました。山田耕筰からの何らかの影響があったのか、とても気になっております」というメールが届きました。私は『謎の漢字』を読んでいたのにもかかわらず、恥ずかしながら指摘されるまで「![]() 」の字の重大性に気づいていなかったのです。そして、調べようとは思いながらも日々の業務に追われ、何カ月も放置したままにしていました。
」の字の重大性に気づいていなかったのです。そして、調べようとは思いながらも日々の業務に追われ、何カ月も放置したままにしていました。
私が怠けているのを察したのでしょうか、同年11月、笹原教授から「2018年1月開催の漢字漢語研究会で発表しませんか」という誘いが来たのです。これはいけないとばかりに、資料をまとめ始め「叙勲記事に見える漢字の地域性 ―新聞外字調査から―」というタイトルで発表することを決めました。「![]() 」の字も発表対象に含まれます。ただ、受章者の方にいきなり見ず知らずの者が名前のいわれについて問い合わせるというのも……などと考え、ちゅうちょしていました。
」の字も発表対象に含まれます。ただ、受章者の方にいきなり見ず知らずの者が名前のいわれについて問い合わせるというのも……などと考え、ちゅうちょしていました。
ちょうどそのころに読んだ安岡孝一・京都大学人文科学研究所付属東アジア人文情報学研究センター教授の論文「Unicode 10.0に見る日本の国字」に「![]() 」の字に触れている箇所がありました。2017年6月に発表されたUnicode 10.0では7473字の漢字追加が行われており、このなかで日本から提案されたのは1645字。そのうちの116字が由来の分からない「謎の漢字」とされていました。「
」の字に触れている箇所がありました。2017年6月に発表されたUnicode 10.0では7473字の漢字追加が行われており、このなかで日本から提案されたのは1645字。そのうちの116字が由来の分からない「謎の漢字」とされていました。「![]() 」の字も116字のなかの1字とされていたのです。
」の字も116字のなかの1字とされていたのです。
「謎の漢字」を解き明かすため、叙勲受章者の本人にいよいよ当たらなければならなくなりました。年が明けた2018年1月初め、命名の由来を質問する手紙を出しました。
※2019年発行の『住民基本台帳ネットワーク漢字辞典』には「![]() 」の字も収録され、「耕の別体」と記されています。
」の字も収録され、「耕の別体」と記されています。
●後編に続きます●
≪参考資料≫
小林肇「叙勲記事に見える漢字の地域性 ―新聞外字調査から―」第115回漢字漢語研究会資料、2018年
笹原宏之『謎の漢字』中公新書、2017年
安岡孝一「Unicode 10.0に見る日本の国字」情報処理学会研究報告、2017年
安岡孝一・安岡素子『住民基本台帳ネットワーク漢字辞典』京都大学未踏科学研究ユニット・学知創生ユニット・人文科学研究所、2019年
毎日新聞校閲部編『読めば読むほど 日本語、こっそり誇れる強くなる』東京書籍、2003年
≪参考リンク≫
≪おすすめ記事≫
新聞漢字あれこれ14 「附属」と「付属」、どう区別? はこちら
新聞漢字あれこれ23 大阪伝統の「すし」を表現! はこちら
≪著者紹介≫
小林肇(こばやし・はじめ)
日本経済新聞社 用語幹事
1966年東京都生まれ。金融機関に勤務後、1990年に校閲記者として日本経済新聞社に入社。編集局 記事審査部次長、人材教育事業局 研修・解説委員などを経て2019年から現職。日本新聞協会新聞用語懇談会委員。漢検漢字教育サポーター。漢字教育士。 著書に『謎だらけの日本語』『日本語ふしぎ探検』(共著、日経プレミアシリーズ)、『文章と文体』(共著、朝倉書店)、『日本語大事典』(項目執筆、朝倉書店)、『加山雄三全仕事』(共著、ぴあ)、『函館オーシャンを追って』(長門出版社)がある。
≪記事画像≫
書:中村 渚