七五三と漢数字【下】 | やっぱり漢字が好き31
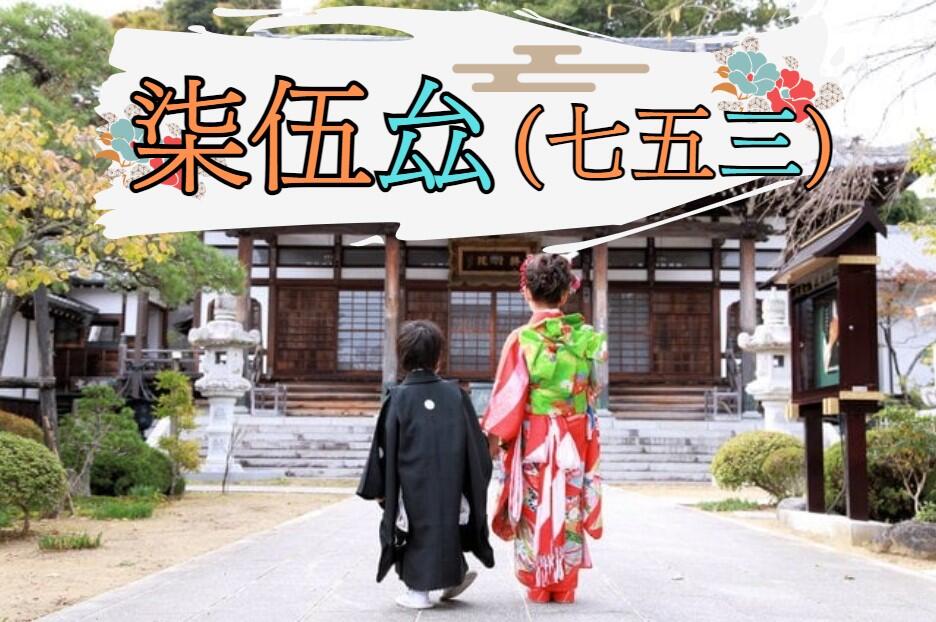
著者:戸内俊介(日本大学文理学部教授)
前号から、七五三にちなんで、古代中国の3を表す漢字の歴史的変遷を見ているが、今号では引き続き戦国時代の3を見ていきたい。
戦国時代(前5世紀~前221年)になると3を表す漢字の種類はさらに増加する。これは近年の出土文献の増加と共に明らかになったことである。
(3) 三赤(新蔡楚簡甲三206号簡)
(4) 晶(三)真呉甲(曽侯乙墓122号簡)
(5) 厽(三)術(郭店楚簡『性自命出』14号簡)
(6) 參(三)郤(上博楚簡『姑成家父』1号簡)
(7) 參(三)邦(清華簡『子産』25号簡)
(8) (三)立事(山東出土陶文:古陶3.36)
(9) (三)|
(二)|
(一)(清華簡『算表』1号簡)
信じられないかもしれないが、これらはすべて3を表す漢字である。しかも同時代に共存していた。(3)は最も一般的な「三」で、後続する「赤」は容積の単位である。
(4)は字形としては「晶」に近いが、「晶」とは何の関係もなく、これも3を表す文字である。「晶(三)真呉甲」は「3セットの甲冑」の意味。
(5)の文字はふつう「厽」で楷書化されるが、「品」で楷書化することもある。これも無論「品」とは関係がなく、3を表す文字である。
(6)(7)はともに「參」字と見なされるが、(7)は(6)の略字であろう。(6)の「三郤」は、中国春秋時代(前8世紀~前5世紀)の晋の有力氏族であった郤(げき)氏のうち、権勢を誇った「郤犨(げきしゅう)、郤錡(げきき)、郤至(げきし)」の3人を指す。また(7)の「三邦」は「夏商周」の3代の王朝である。
(8)は(5)の「厽」と「三」が組み合わされたように見える文字である。「三立事」は「3回目の立事の役職」といった意味であろう。
(9)は「三」と「戈」からなる文字で、直後に「二、一」といった基数が羅列されている。
ではなぜ西周から戦国時代にわたって、3を表す文字に複数の種類が用意されているのか、それぞれの3を表す文字に用法上の違いがあるのか。この問題について目下論文を準備中であり、ここで筆者の考えを提示することは差し控えるが、ただ1つ言えることは、西周から戦国時代の「三」と「參」は現在の小字と大字の関係にあたるというわけで決してはない。
秦の統一(前221年)を機に(4)(5)(7)(8)の表記は見えなくなり、3を表す漢字は「三」ないし「參」を用いるようになった。現代の我々は、この秦の表記上の習慣をいまだ引き継いでいる。
次回「やっぱり漢字が好き32」は11月15日(金)公開予定です。
≪参考資料≫
河南省文物考古研究所編著《新蔡葛陵楚墓》、文物出版社、2003年
荊門市博物館編《郭店楚墓竹簡》、文物出版社、1998年
湖北省博物館編《曾侯乙墓》、文物出版社、1989年
高明編《古陶文彙編》、中華書局、1990年
清華大学出土文献研究与保護中心編《清華大学蔵戦国竹簡》(壹)-(玖)、中西書局、2010年-2019年
馬承源主編《上海博物館蔵戦国楚竹書》(一)-(九)、上海古籍出版社、2001-2012年
≪参考リンク≫
漢字ペディアで「三」を調べよう
漢字ペディアで「参」を調べよう
≪おすすめ記事≫
やっぱり漢字が好き。2 なぜ“4”は「四」と書くのか?(上) はこちら
≪著者紹介≫
戸内俊介(とのうち・しゅんすけ)
日本大学文理学部教授。1980年北海道函館市生まれ。東京大学大学院博士課程修了、博士(文学)。専門は古代中国の文字と言語。著書に『先秦の機能後の史的発展』(単著、研文出版、2018年、第47回金田一京助博士記念賞受賞)、『入門 中国学の方法』(共著、勉誠出版、2022年、「文字学 街角の漢字の源流を辿って―「風月堂」の「風」はなぜ「凮」か―」を担当)、論文に「殷代漢語の時間介詞“于”の文法化プロセスに関する一考察」(『中国語学』254号、2007年、第9回日本中国語学会奨励賞受賞)、「「不」はなぜ「弗」と発音されるのか―上中古中国語の否定詞「不」「弗」の変遷―」(『漢字文化研究』第11号、2021年、第15回漢検漢字文化研究奨励賞佳作受賞)などがある。










