四字熟語根掘り葉掘り54:「徹骨徹髄」は師匠から弟子へ
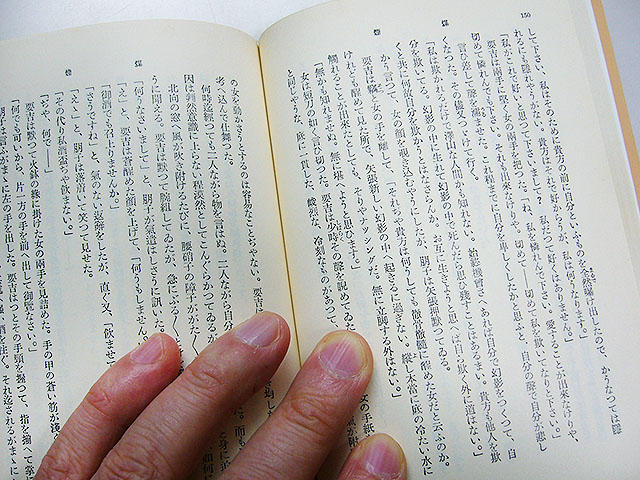
著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)
1909(明治42)年、ある心中未遂事件が世間を大きく騒がせました。当事者は、青年文士の森田草平(もりた・そうへい)と、のちに「元始女性は太陽であった」と宣言して女性運動の先駆者となった平塚らいてう。森田は妻子を持つ身であったこともあり、激しい非難にさらされることになりました。
その非難に答えるという意味もあったのでしょう。彼は、この一件を題材とした小説を発表します。文学の師であった夏目漱石の斡旋で『朝日新聞』に連載されたその作品、『煤煙』は、大きな評判となり、森田草平の名は、一躍、新進文学者として注目を浴びることとなりました。
さて、先日、ある古書店で岩波文庫の『煤煙』を見つけたので、買い求めて読んでみました。すると、その中ほどで主人公の男性が発する、こんなセリフが気になりました。
「それじゃ貴方は何(ど)うしても徹骨徹髄(てっこつてつずい)に醒めた女だと云うのか。」
「徹骨徹髄」とは、「骨髄に徹する」を四字熟語にした表現で、文字通りには〈骨の髄まで〉という意味。〈心の奥底まで〉とか〈ものごとの根本まで〉といった意味で用いられます。古くは、11世紀ごろの中国の禅の書物に見られることばで、日本でも現在に至るまでよく読まれている『碧巌録(へきがんろく)』では、4回も使われています。
とはいえ、このことば、あまりメジャーな四字熟語ではありません。手元の四字熟語辞典を10冊ばかり調べてみても、収録しているのは3冊だけ。そこで、私が読書の中で出会ってはメモしてきた、のべ1万5000件を超える四字熟語の用例リストを当たってみたところ、記録されていた例は2つだけでした。
その1つめは、漱石の超有名作、『吾輩は猫である』。1905(明治38)年から翌年にかけて連載された作品です。もう1つも漱石作品で、1906(明治39)年に発表された『草枕』。漱石は、1909(明治42)年には、禅を主要なモチーフの1つとした長編、『門』の連載を始めているくらいですから、『碧巌録』をはじめとする禅の書物に目を通していたとしても、不思議ではありません。そういう読書体験の中で、漱石は「徹骨徹髄」に出会い、それを己の文章表現に取り入れていったのでしょう。
一方、森田草平は、『草枕』を読んで感銘を受け、漱石の門下生となったのだとか。とすれば、『碧巌録』から漱石が受け継いだ「徹骨徹髄」は、漱石自身の文章を通じて森田草平に受け継がれ、『煤煙』で用いられたのでしょう。たった1つのことばの中に、文学者の師弟関係が表れているようで、興味深く感じたことでした。
≪参考リンク≫
≪おすすめ記事≫
四字熟語根掘り葉掘り46:「百面億態」はどこから来たか? はこちら
四字熟語根掘り葉掘り53:恋と理屈と「夏炉冬扇」 はこちら
≪著者紹介≫
円満字二郎(えんまんじ・じろう)
フリーライター兼編集者。 1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。 著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)など。 また、東京の学習院さくらアカデミー、NHK文化センター青山教室、名古屋の栄中日文化センターにて、社会人向けの漢字や四字熟語の講座を開催中。 ただ今、最新刊『四字熟語ときあかし辞典』(研究社)に加え、編著の『小学館 故事成語を知る辞典』が好評発売中!
●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/
≪記事画像≫
岩波文庫『煤煙』より










