四字熟語根掘り葉掘り59:「一心同体」ではもの足りない?
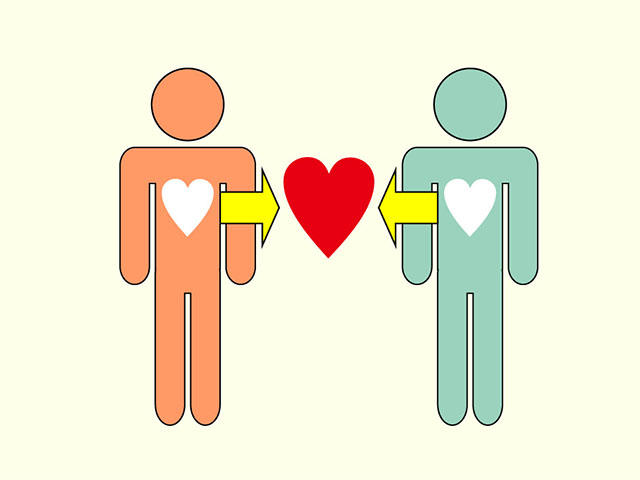
著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)
学校の漢字テストで、「一心同体」という四字熟語を「一身同体」と書いたら、間違いなくバツになることでしょう。私が原稿でそう書こうものなら、校閲をしてくださる方から思いっきり赤字が入ることでしょう。
しかし、現実には、「一身同体」の使用例は少なくはありません。私が見つけたものだけでも、かの福沢諭吉を初め、明治時代にジャーナリストとして活躍した矢野龍渓、文豪として押しも押されもせぬ永井荷風や谷崎潤一郎、昭和の小説家、坂口安吾や武田泰淳など、錚々たる面々が、「一身同体」を用いています。
これらは、単なるうっかりミスかもしれません。昔は校閲の体制も整っていなかったから、作家さんが手書きでついつい書き間違えたものが見逃されてしまったのだ、と考えるのが常識的なところでしょう。
とはいえ、多くの人が同じ間違いをするのならば、そこには何か理由がありそうなものです。
「一心同体」の「一心」とは、〈心を1つにする〉こと。「心を1つにする」というのは日常的によく使われる表現ですから、「一心同体」の「一心」は、ごくありふれたふつうの表現だと言ってよいでしょう。
「同体」の方も、「一心」との関係から考えれば、〈体を同一にする〉ことでしょう。しかし、ある1つの体を複数の人間が共有することはできません。つまり、こちらはありえないことを述べる大げさな表現。「一心同体」とは、ありふれた表現のあとに非現実的な表現を付け加えて強調したものだ、と考えることができます。
あえて細かく説明するならば、〈心を1つにするんだけど、それがありえないくらい激しくて、まるで体まで同じになって感じられるくらい〉といったニュアンスでしょうか。平凡な表現をおおげさに拡大して示すというのが、「一心同体」のレトリックなのです。
これが、「一身同体」になると、「一心」というありふれた表現が、〈身体を1つにする〉という、現実には起こりえない表現に取って代わられてしまいます。そこに、同じ意味の表現を重ねてさらに強調する形になるのです。
つまり、強調の度合いとしては、「一心同体」よりも「一身同体」の方が激しい、といえるでしょう。作家さんが強い思い入れを持って「一心同体」を使おうとするとき、その思い入れのあまり「一身同体」と書いてしまう。それが、「一身同体」の使用例が少なからず存在する1つの理由なのではないでしょうか。
さらに言えば、「一心同体」ではもの足りないと感じた作家さんが、意図的に「一身同体」という表現を創り出すことだってありえるでしょう。いつの日か、「一身同体」が市民権を得る時代が、来るのかもしれません。
≪参考リンク≫
≪おすすめ記事≫
四字熟語根掘り葉掘り46:「百面億態」はどこから来たか? はこちら
四字熟語根掘り葉掘り54:「徹骨徹髄」は師匠から弟子へ はこちら
≪著者紹介≫
円満字二郎(えんまんじ・じろう)
フリーライター兼編集者。 1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。 著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)など。 また、東京の学習院さくらアカデミー、NHK文化センター青山教室、名古屋の栄中日文化センターにて、社会人向けの漢字や四字熟語の講座を開催中。 最新刊、『漢字の植物苑 花の名前をたずねてみれば』(岩波書店)が2月21日に発売。
●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/
≪記事画像≫
筆者作成










