四字熟語根掘り葉掘り65:「夜雨対牀」が生まれるまで
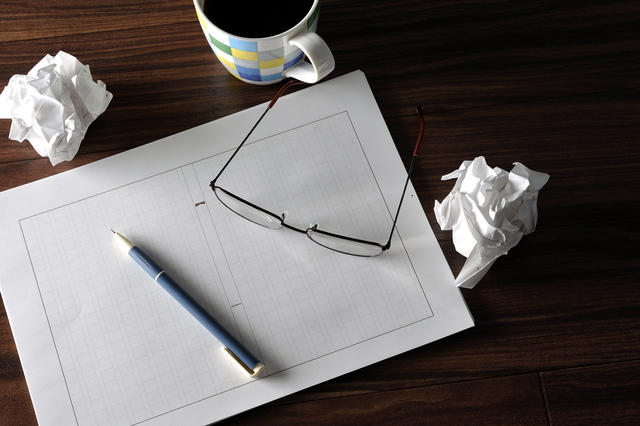
著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)
8世紀、唐王朝の時代に生きた韋応物(いおうぶつ)といえば、静謐な自然をうたった落ち着いた作風で、現在でも人気がある漢詩人の1人。彼が、ある友人と別れるときに贈った作品の中に、次のような一節があります。
寧(なん)ぞ知らん、風雪の夜
復(ま)た此(ここ)に対牀(たいしょう)して眠らんことを
現代語に訳せば、〈風が吹き雪が舞う晩にこうやって布団を並べて眠ることができるのは、次はいつのことだろうか〉といったところ。吹雪の夜、友人と枕を並べて来し方行く末を語り合うなんて、しみじみとしていて、なんともいい場面ですね。この印象的な一節からは、「風雪対牀(ふうせつたいしょう)」という四字熟語が生まれていますが、現在ではほとんど見かけることはありません。
韋応物が亡くなったあと、8〜9世紀の大詩人、白居易(はくきょい。雅号によって白楽天とも呼ばれます)は、これまた友人にあてた詩で、おそらくこの詩句を踏まえて、次のようにうたいました。
能(よ)く来たりて同宿するや否や
雨を聴きて対牀して眠らん
〈泊まりがけでこっちへ来ないか? 雨の音を聴きながら枕を並べて語り合おうよ〉。ここからは「聴雨対牀」という表現が生まれているのですが、残念ながら、四字熟語辞典の類いに採録された例はないようです。
さて、それから250年ほどが過ぎた北宋王朝の時代、以上を下敷きにした第3の表現が現れます。その生みの親は、11世紀に活躍した文豪、蘇軾(そしょく。雅号によって蘇東坡[そとうば]とも言われます)。彼は、「夜雨(やう)」の晩に弟と「対牀」しながら仲睦まじく過ごすようすを何度も詩にうたいました。
そこから生まれたのが、「夜雨対牀(やうたいしょう)」。〈家族や友人とのとても親密な関係〉を指して使われます。先の2つに比べると、最もよく知られた表現となっています。
「風雪対牀」と「聴雨対牀」を比較すると、「聴雨」の方が絶え間なく続く雨の音が聴覚を刺激して、静けさがかえって強調されて感じられます。「夜雨対牀」では、雨の音を響かせつつ、「夜」の闇が視覚的な効果を上げて、静けさをさらに際立たせていると言えるでしょう。
詩人とは、先人たちの作品を勉強しながら、新しい表現を求めて工夫を重ねるものです。親しい二人の語らいの場面に似つかわしい静けさを表すのには、どうすればよいか? 決定版たる「夜雨対牀」という四字熟語が誕生するまでには、詩人たちの表現追求のドラマがあったのです。
≪参考リンク≫
≪おすすめ記事≫
四字熟語根掘り葉掘り45:漢和辞典と「捲土重来」の謎 はこちら
四字熟語根掘り葉掘り59:「一心同体」ではもの足りない? はこちら
≪著者紹介≫
円満字二郎(えんまんじ・じろう)
フリーライター兼編集者。 1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。 著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)、『漢字の植物苑 花の名前をたずねてみれば』(岩波書店)など。
●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/
≪記事画像≫
ナオ/ PIXTA(ピクスタ)










