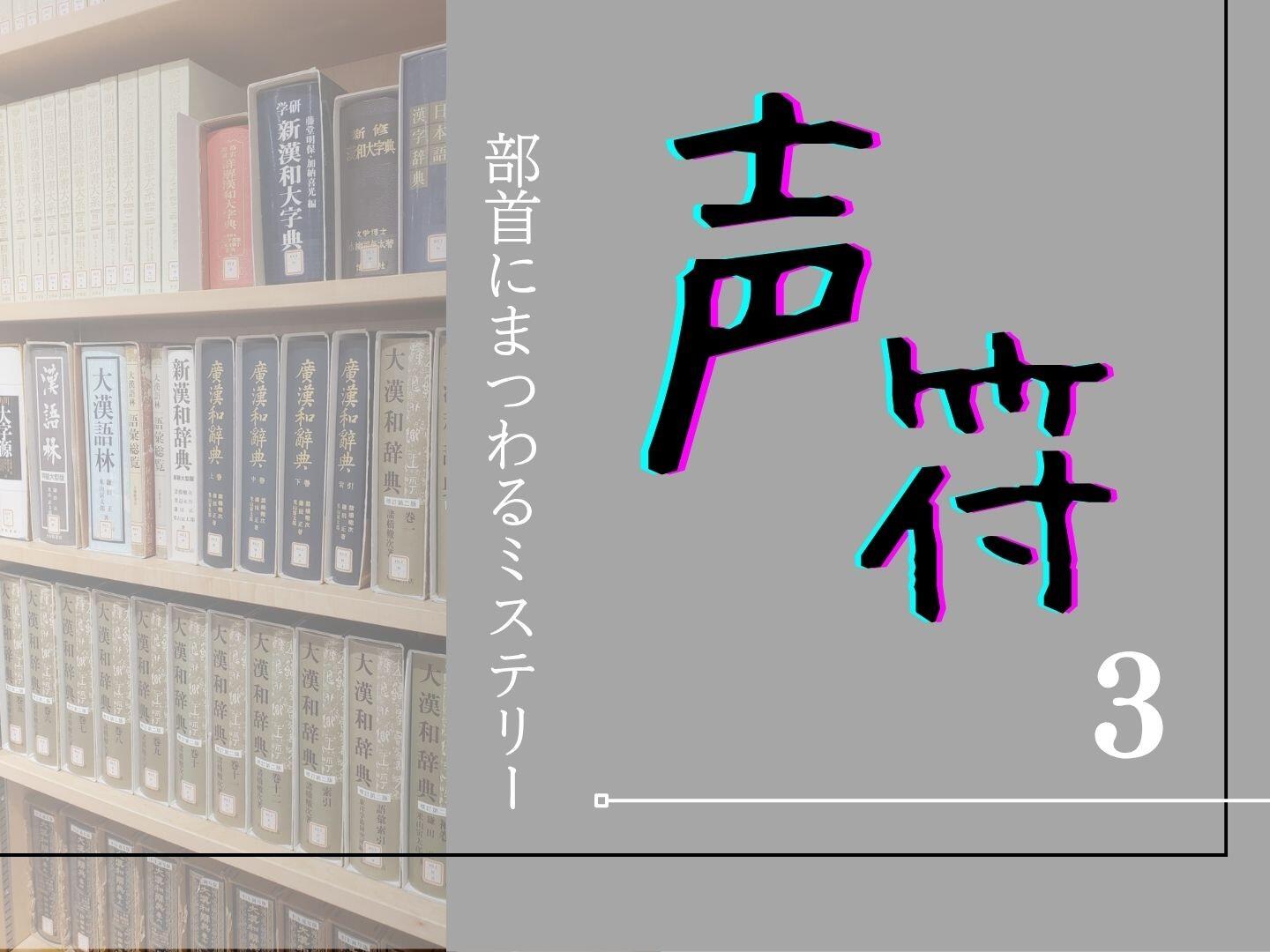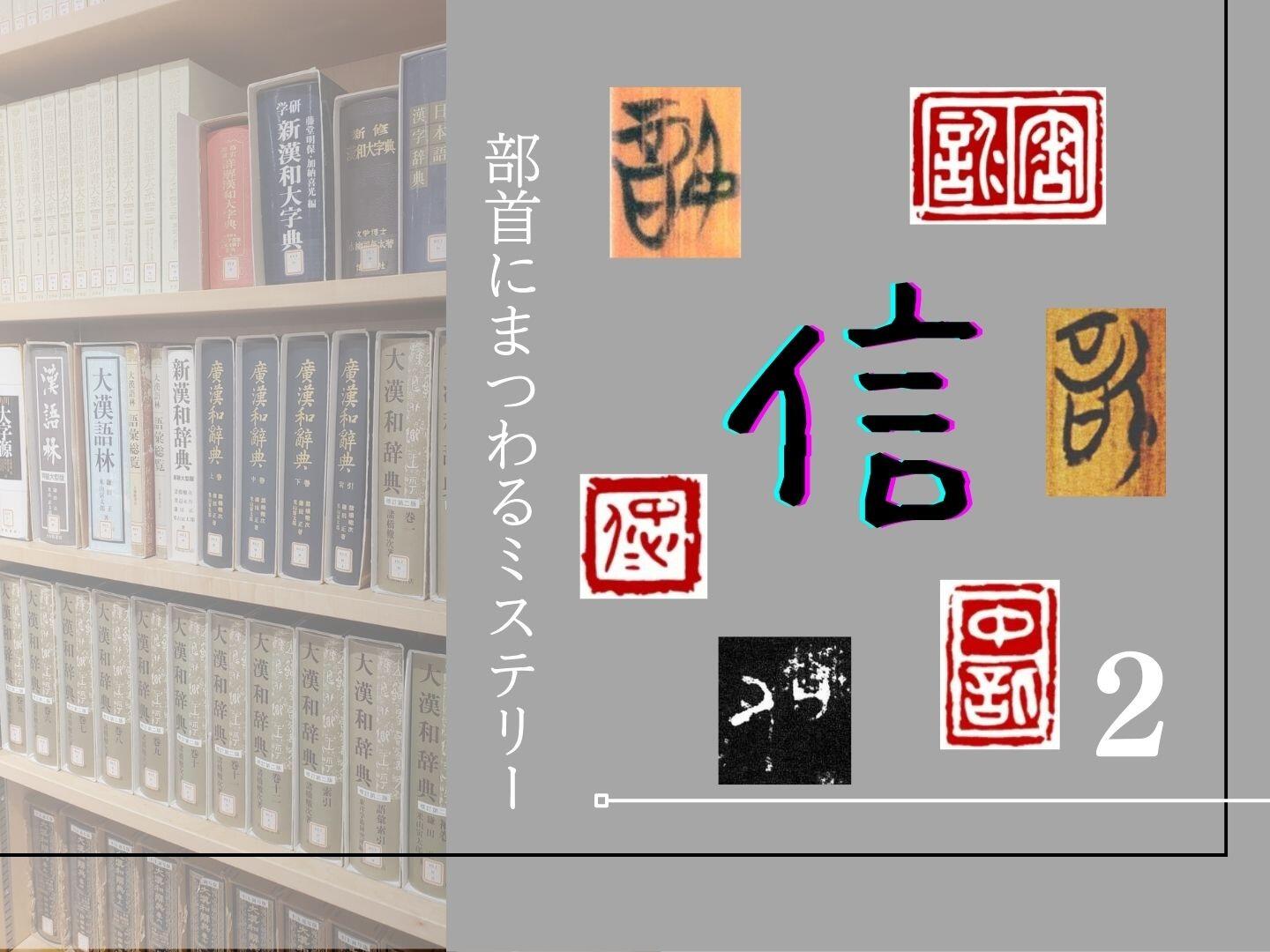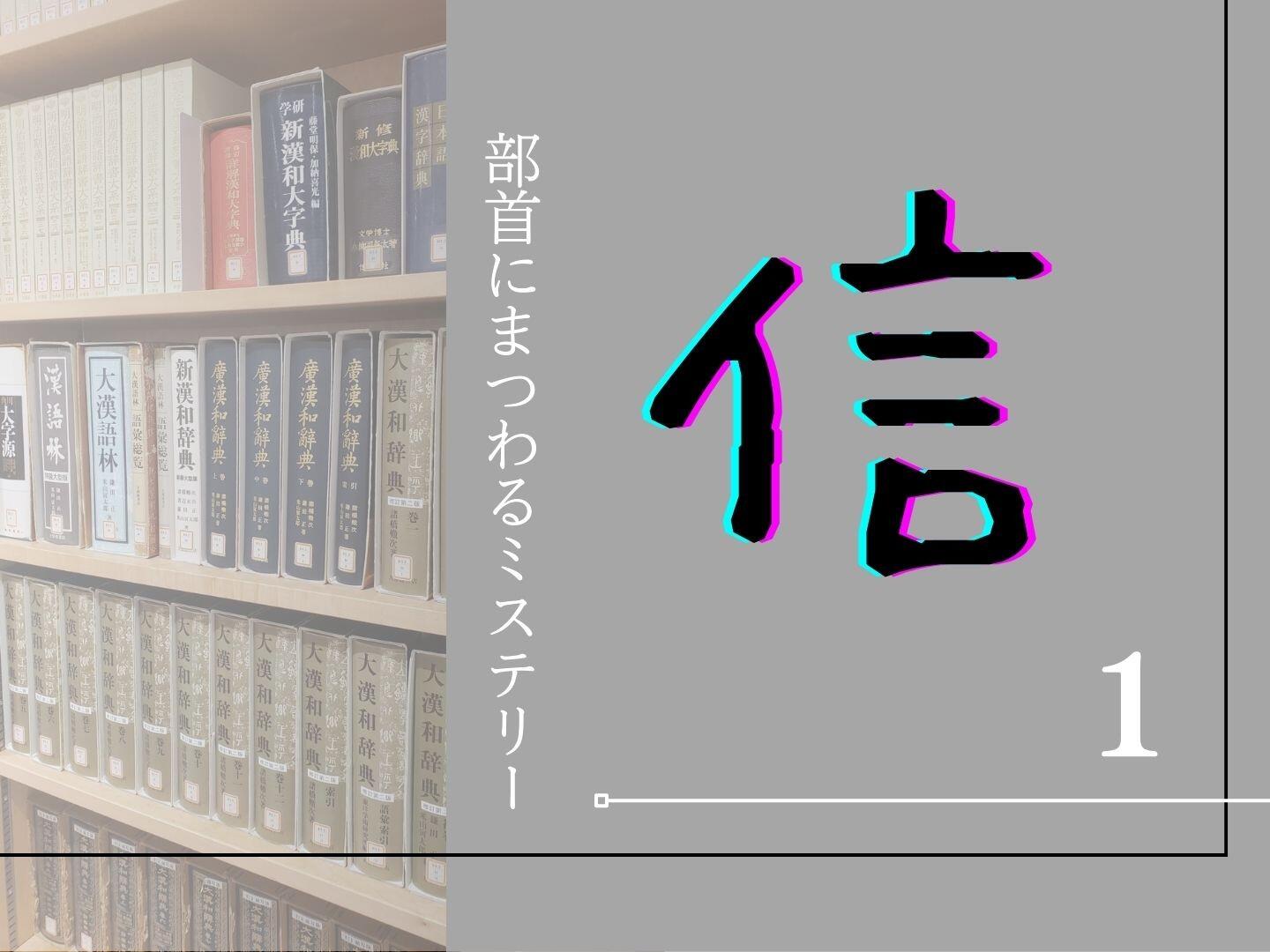漢字コラム47「蟬」両羽で鳴くもの?

著者:前田安正(未來交創株式会社代表取締役)
架空の海坂藩が舞台の時代小説『蟬しぐれ』。藤沢周平の代表作です。下級武士家に生まれた牧文四郎の成長物語が中心に展開されます。物語に添うように語られる幼なじみ福との淡い恋。蟬時雨が哀愁を演出します。盛夏の喧噪(けんそう)をもたらす鳴き声とともに、もの悲しさを醸し出す蟬について、調べてみました。
セミは「蟬」と書き、「セン」「ゼン」という音を持ちます。この音を担うのが「單」の部分です。これは「単」の旧字体です。「単」は「タン」という音を表すだけではなかったのです。「戦=セン」や「禅=ゼン」の例を見れば、わかるかと思います。
「蟬」は「單」に「虫」がついたものです。「虫」は生き物全般を表します。中国の字書「説文解字」には「両羽で鳴くもの」とあります。まるで鈴虫やコオロギを説明しているようです。蟬がどうやって鳴くのかを知らなかったとも思えないのですが……。「説文解字」を編纂(へんさん)した後漢の許慎は、蟬に興味がなかったのでしょうか>。
面白いことに、「説文解字」には「單」は「大きい」という意味だと記されています。「一つであるさま」「孤独であるさま」「弱々しい」「複雑でない」という、私たちが通常理解している「單」の意味とは、異なる解釈です。科学的な根拠がないというおしかりを受けるかもしれませんが、「單」が蟬の「大きな鳴き声」を象徴していたかもしれないと想像を膨らませることもできるかもしれません。
「蜩(チョウ)」もセミという字です。「大きいセミ、クマゼミ」だと辞書にあります。「大きい」とあるのに、「單」は使われていません。類語などを取り上げている字書「爾雅(じが)」の注釈書には「小さな青い蟬」とあります。ここでは「小さい」という解釈です。日本では「茅蜩(ぼうちょう)」や「蜩」を「ひぐらし」と読むようになりました。平安中期の漢和辞書「倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)」には「茅蜩」を「比久良之」と記しています。
「蜩」は古くから日本の文学にも親しまれてきました。『万葉集』には、夏の雑歌として大伴家持(やかもち)が「隠(こも)りのみ居(を)ればいぶせみ慰むと出(い)で立ち聞けば来鳴くひぐらし」(巻8)と詠んでいます。『古今集』には秋の情景として「ひぐらしの鳴く山里の夕暮は風よりほかに訪(と)ふ人もなし」(詠み人知らず)などがうたわれています。『源氏物語』の中でも「幻(まぼろし)」では夏に、「宿木(やどりぎ)」では秋の場面に登場しています。文学的にも季節のあわいを埋める重要な役割があったのでしょう。ちなみに季語としては、蟬は夏、蜩はツクツクボウシとともに秋です。
蟬はカゲロウとともに、はかない命の代名詞になっています。「空しい」という意味を持つ「うつせみ(空蟬)」は、もとは「うつしおみ(顕臣)」と言い「この世に生きている人」という意味でした。音韻の変化に伴い「顕臣→空蟬」となり、蟬の抜け殻のイメージが重なって意味も変質したのです。
蟬の命は成虫になってから10~20日くらいですが、幼虫期は地中で数年から17年ほど過ごします。蟬の一生を通してみると案外長いのです。一方のカゲロウは、幼虫期間は1~3年程度、成虫は数時間から1日だそうです。蟬よりよほどはかない生き物なのです。その名の由来は、成虫がゆらゆら飛び交うさまが、陽炎に似ているからとも言われています。
≪参考資料≫
「漢字の起原」(角川書店 加藤常賢著)
「漢字語源辞典」(學燈社 藤堂明保著)
「漢字語源語義辞典」(東京堂出版 加納喜光)
「言海」(ちくま学芸文庫 大槻文彦)
「学研 新漢和大字典」(学習研究社 普及版)
「全訳 漢辞海」(三省堂 第三版)
「漢字ときあかし辞典」(研究社、円満字二郎著)
「日本国語大辞典」(小学館)、「字通」(平凡社 白川静著)は、ジャパンナレッジ(インターネット辞書・事典検索サイト)を通して参照
前田安正オフィシャルサイト「ことばデザインワークス・マジ文ラボ」https://kotoba-design.jp/
≪参考リンク≫
漢字ペディアで「蟬」を調べよう。
漢字ペディアで「蜩」を調べよう。
≪おすすめ記事≫
漢字コラム13「戦」地をはらって平らかにする はこちら
漢字コラム38「虫」鳥も亀も魚も人も、みんなムシなんだ はこちら
≪著者紹介≫
前田安正(まえだ・やすまさ)
未來交創株式会社代表取締役/ビジョンクリエイター/文筆家
玉川大学文学部非常勤講師
朝日新聞校閲メディアプロダクション校閲事業部長
早稲田大学卒業、事業構想大学院大学修了
82年朝日新聞社入社、名古屋編集センター長補佐、大阪校閲センターマネジャー、用語幹事、校閲センター長、編集担当補佐兼経営企画担当補佐などを歴任。「漢字んな話」「漢話字典」「ことばのたまゆら」「あのとき」など、十数年にわたり朝日新聞に漢字や日本語に関するコラム・エッセイを毎週連載。
2019年文章コンサルティングファーム未來交創株式会社を立ち上げ、わかりやすい文章の書き方、コミュニケーションの楽しさを伝える仕事をしている。「文章の書き方・直し方」など、企業・自治体の広報文の研修に多数出講。テレビ・ラジオ・雑誌・ネットなどのメディアにも数多く登場している。
《著書》
9.1万部を超えた『マジ文章書けないんだけど』(2017年・大和書房/19年・台湾で翻訳出版)を始め、
2010年『漢字んな話』、12年『漢字んな話2』(三省堂)
2013年『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』(すばる舎/19年・韓国で翻訳出版)
2014年『間違えやすい日本語』(すばる舎)
2015年『しっかり!まとまった!文章を書く』(すばる舎)
2017年『3行しか書けない人のための文章教室』(朝日新聞出版)
2018年『クレオとパトラのなんでナンデさくぶん』(大和書房/20年・中国で翻訳出版予定)
2019年『ヤバいほど日本語知らないんだけど』(朝日新聞出版)
2020年『ほめ本』(ぱる出版)、『きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける』(朝日文庫)、『使える!用字用語辞典』(共著・三省堂)
などがある。