四字熟語根掘り葉掘り79:今年は「大盤振舞」できるかな?
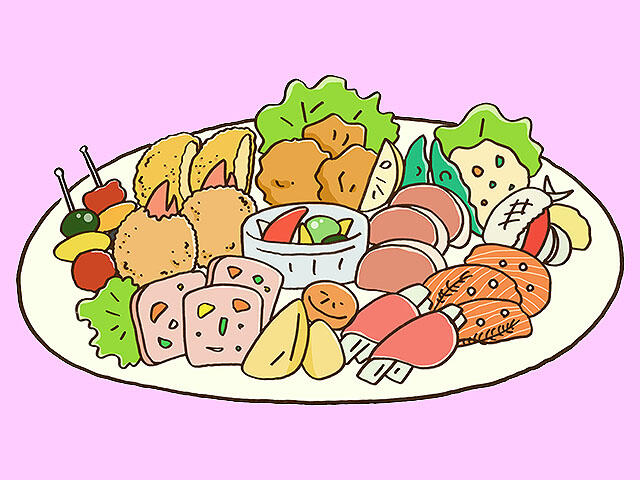
著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)
みなさま、明けましておめでとうございます。今年のお正月は、コロナ禍のためにあちこちへ出かけるのははばかられて、例年とはまったく異なるものになりましたね。そのぶん、家族と一緒においしいごちそうを食べて過ごした方も多かったのではないでしょうか。
さて、江戸時代には、庶民がお正月に親類を招いて料理でもてなすことを「椀飯(おうばん)」と呼びました。ここから、〈大勢の人を料理でもてなす〉ことをいう「椀飯振舞(おうばんぶるまい)」という四字熟語が生まれています。
「椀」は、音読みは「ワン」で、食器の〈おわん〉を表す漢字。「椀飯」はそのまま読めば「ワン・ハン」ですが、これが「ワンバン→ワウバン→オウバン」と変化したわけです。この「オウバン」がさらに変化したのが「オオバン」。ここまで来ると、もとは「椀飯」だったという意識が薄れ、「大盤」と当て字されるようになります。
そこで、「椀飯振舞」も、現在では「大盤振舞(おおばんぶるまい)」と書かれるのが一般的。料理を振る舞う場合だけではなく、広く〈気前よく金品を使う〉場合に、よく用いられますよね。
「盤」は、部首「皿(さら)」が付いていることにも現れているように、本来は、〈円形で比較的浅めの食器〉を意味する漢字。つまり、「椀飯振舞」も「大盤振舞」も、漢字的には料理と深く関係しているわけです。
ところが、「盤」という漢字は、実際にはとても広い意味で用いられます。「円盤」「吸盤」のように〈円形で平たいもの〉を指すのは序の口で、「碁盤」「野球盤」などでは〈勝負ごとを行うための台〉。そうかと思えば、「基盤」「地盤」では〈よりどころとなるしっかりしたもの〉ですし、「羅針盤」「配電盤」のようにある種の〈計器〉についても使われます。
というわけで、現在の私たちは、「盤」という漢字を見ても食器を思い出すことはまずありません。「椀飯振舞」が「大盤振舞」と書かれるようになった背景には、発音の変化だけでなく、こういう漢字のもたらすイメージも影響していたのではないでしょうか。料理をはっきりと連想させる「椀飯」よりもその印象があまりない「大盤」の方が、〈気前よく金品を使う〉場合にはなじみやすいですからね。
ところで、「椀飯」は、言ってみれば〈どんぶり飯〉。対する「大盤」は、文字通りにとらえれば〈大皿料理〉。新型コロナウイルスの感染を防ぐためには、大皿料理に直接、箸を伸ばすのは禁物です。早く感染状況が落ち着いて、「大盤振舞」が楽しめるようになってほしいものです。
≪参考リンク≫
漢字ペディアで「大盤振舞」を調べよう
漢字ペディアで「椀飯振舞」を調べよう
≪おすすめ記事≫
四字熟語根掘り葉掘り65:「夜雨対牀」が生まれるまで はこちら
四字熟語根掘り葉掘り74:「急転直下」と落ちていく意識 はこちら
≪著者紹介≫
円満字二郎(えんまんじ・じろう)
フリーライター兼編集者。 1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。 著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)、『漢字の植物苑 花の名前をたずねてみれば』(岩波書店)など。
●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/
≪記事画像≫
「イラストAC」より、みこさんのイラストを利用。










