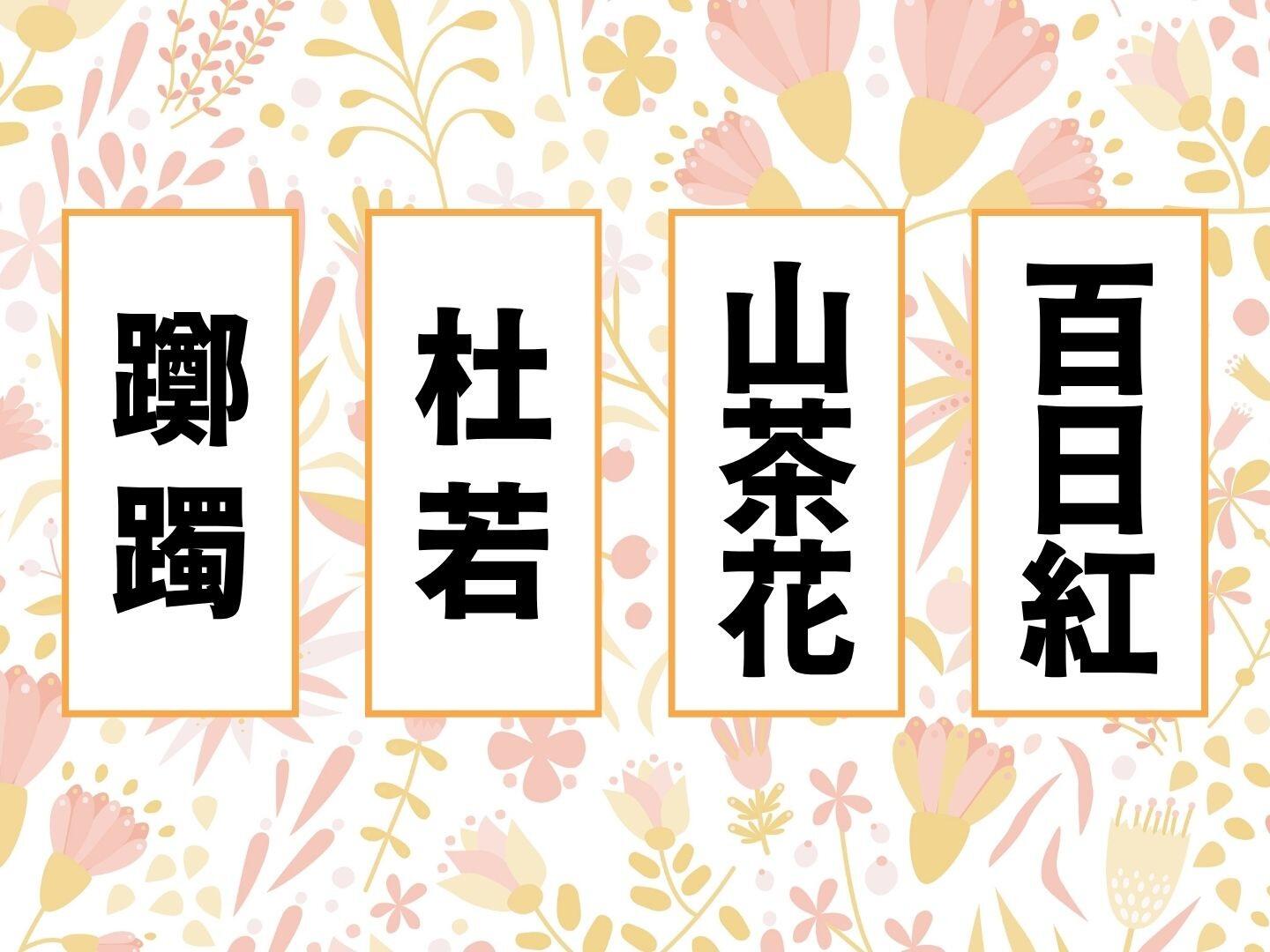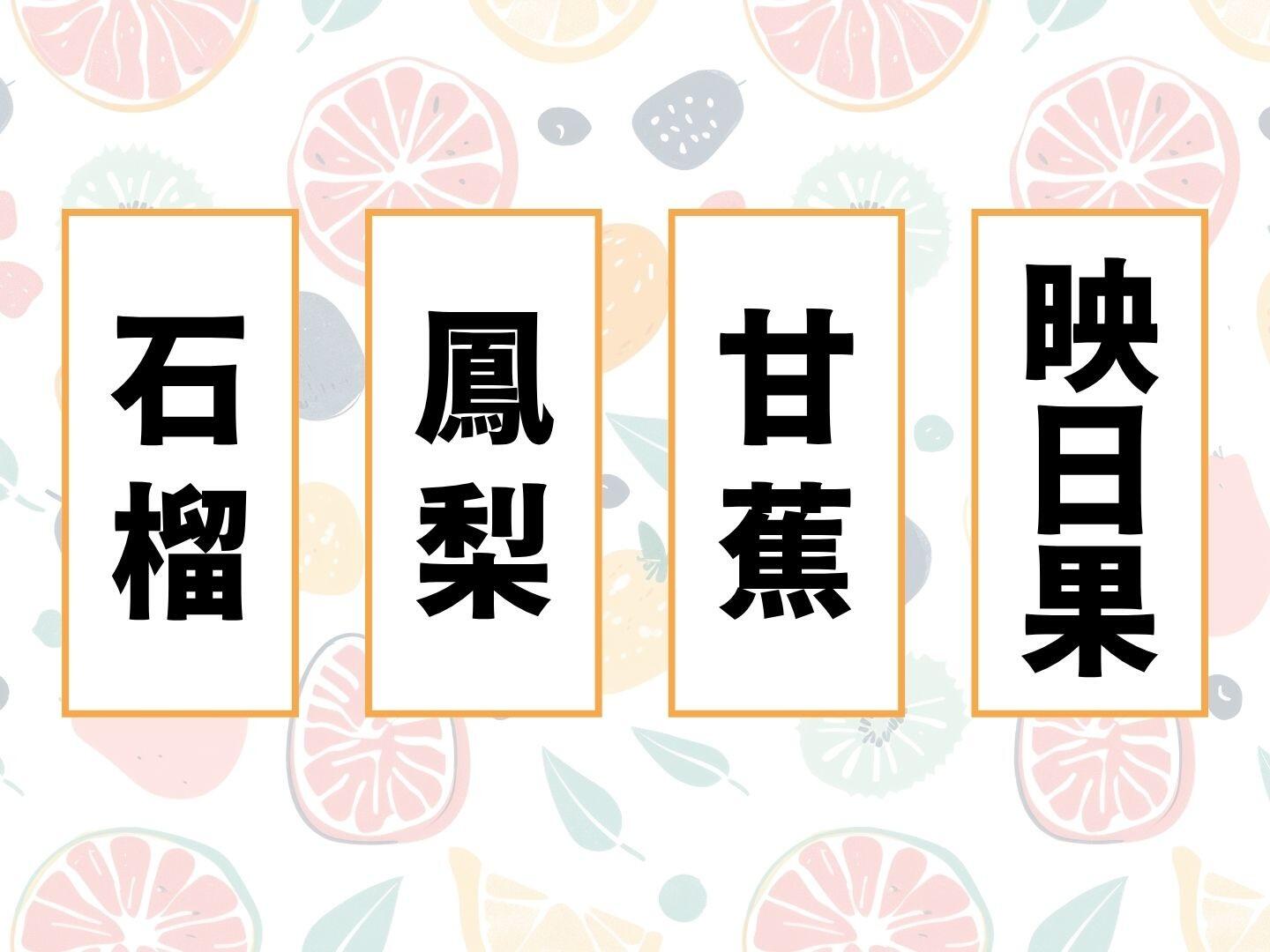新聞漢字あれこれ63 ノリ養殖に欠かせません

著者:小林肇(日本経済新聞社 用語幹事)
トップ画像を見て読者の皆さんがまず思い浮かべる漢字は何でしょうか。いろいろありそうですが、1字だと少し難しいかもしれません。
私が答えとして用意していたのは「篊」です。新聞からこの字を採集したのは6回。JIS第4水準の「超1級漢字※」で、あまり見かけない字ではあります。主に「ひび」と読み「ノリ・カキなどの養殖で、胞子や幼生を付着させるため、遠浅の海中に立てておく枝付きの竹や粗朶(そだ)」(大辞林)のこと。ここ数年は、年に1回程度紙面に登場しています。
2月は日本経済新聞朝刊文化面でホリプロ創業者の堀威夫(ほり・たけお)さんが「私の履歴書」を執筆。全27回にわたり、華やかな昭和芸能史と半生を連載中です。その第2回に、生まれ育った横浜・根岸での戦時中の話で「海岸には篊と呼ばれる海苔の養殖に使う竹が並んで立っていた」というくだりに「篊」が出てきました。これまで採集した6回すべてが文化関係の紙面にあり、うち5回がノリの養殖に関するもの。「海苔篊」は春の季語だそうで、俳句欄にも2度載っているのを見ました。
残る1回が、伝統漁法のひとつ石干見(いしひび・いしひみ)を紹介する記事に、その語源として「篊」が出ていました。もともと篊とは「海中に並べ立て、一方に口を開け、満潮時に入った魚を干潮時に捕る仕掛け」(大辞林)で、後にノリなどの養殖に利用されるようになったことのようです。
ではなぜ「篊」を「ひび」と読ませるのか。江戸時代後期の随筆『嬉遊笑覧』(1830年)には「ひゞとはひゞきの略なるべし魚聚れば竹木の枝動くもの故ひゞと云歟今品川鮫洲の邊にて海苔をとるひゞはもと魚を取しものなり」とありました。漁具である「篊」は、魚が集まれば竹の枝が動いて音が響くことから「ひびき」で、略して「ひび」になったという説です。なかなか風情がありますね。
「篊」が立ち並ぶノリ養殖の風景はどこか懐かしさを感じさせるものがあります。それが人々の記憶に残り語り継がれ、歴史としても記録されていくのでしょう。文化系の記事に「篊」が登場する理由はそんなところにありそうです。
※超1級漢字:JIS第1・第2水準以外の漢字のこと。筆者の造語。漢検1級の出題範囲である約6000字がJIS第1・第2水準を目安としていることから。
≪参考資料≫
喜多村信節、日本随筆大成編輯部『嬉遊笑覧 下巻 第五版』成光館出版部、1932年
鈴木幸一「私の履歴書③ 放課後フラフラ」日本経済新聞2019年10月3日付朝刊
田村正孝「潮の干満使う スロー漁法」日本経済新聞2019年8月30日付朝刊
中村博「海苔のふるさと 東京・大森」日本経済新聞2020年5月2日付朝刊
堀威夫「私の履歴書② 滝之上」日本経済新聞2021年2月2日付朝刊
『増補改訂JIS漢字字典』日本規格協会、2002年
『大辞林 第四版』三省堂、2019年
『日本国語大辞典第二版第十一巻』小学館、2001年
≪参考リンク≫
「NIKKEIことばツイッター」はこちら
≪おすすめ記事≫
新聞漢字あれこれ32 日本経済を支える「塡」 はこちら
新聞漢字あれこれ61 「酛」 日本酒好きなら知っている はこちら
≪著者紹介≫
小林肇(こばやし・はじめ)
日本経済新聞社 用語幹事
1966年東京都生まれ。金融機関に勤務後、1990年に校閲記者として日本経済新聞社に入社。編集局 記事審査部次長、人材教育事業局 研修・解説委員などを経て2019年から現職。日本新聞協会新聞用語懇談会委員。漢検漢字教育サポーター。漢字教育士。 専修大学協力講座講師。
著書に『マスコミ用語担当者がつくった 使える! 用字用語辞典』(共著、三省堂)、『謎だらけの日本語』『日本語ふしぎ探検』(共著、日経プレミアシリーズ)、『文章と文体』(共著、朝倉書店)、『日本語大事典』(項目執筆、朝倉書店)、『大辞林第四版』(編集協力、三省堂)、『加山雄三全仕事』(共著、ぴあ)、『函館オーシャンを追って』(長門出版社)がある。2019年9月から三省堂辞書ウェブサイトで『ニュースを読む 新四字熟語辞典』を連載。
≪記事画像≫
柳井研一郎/PIXTA(ピクスタ)