四字熟語根掘り葉掘り84:悲劇の夫婦の「相思相愛」
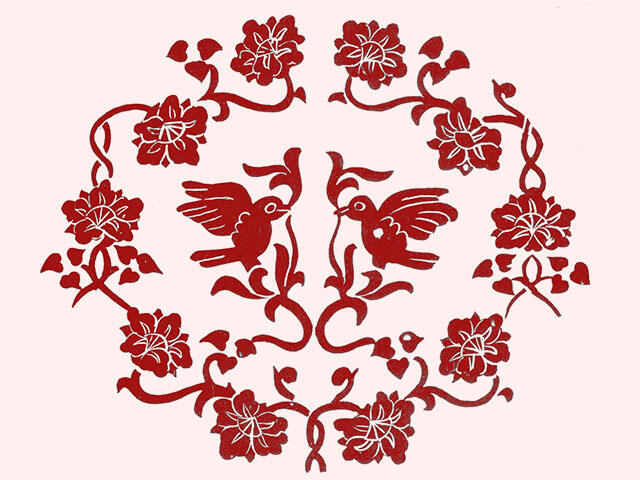
著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)
「相思相愛(そうしそうあい)の仲」というと、ふつうに思い浮かべるのは、〈両思い〉の恋人同士でしょう。プロ野球のドラフト会議での指名する球団と指名を受ける選手だとか、合併を計画している企業同士だとかに対しても用いられますが、それは、もののたとえというものです。
基本的なイメージが恋人同士であることから、「相思相愛」の歴史はそんなに古くはないことが予想されます。なぜなら、「愛」という漢字がいわゆる〈恋愛〉の意味合いで広く使われるようになったのは、近代以降だから。実際、私の知っている限りでは、この四字熟語の日本語での使用例は、1888(明治20)年ごろより前にはさかのぼることができません。
目を中国に転じても、それより古い「相思相愛」の使用例は見あたりません。ただ、「思」の代わりに「親」を用いた「相親相愛」であれば、12世紀ごろ以降の中国の文章で、少なからず用いられています。近代になるまでの中国では、「愛」とは〈親愛〉のイメージだったのでしょう。
とはいえ、〈恋愛〉のイメージで「愛」を使うことがなかったわけではありません。たとえば、4世紀ごろに書かれた『捜神記(そうじんき)』という書物には、「相思」と「相愛」がごく近いところに続いて出て来る、こんな物語が収録されています。
……紀元前3世紀、戦国時代の終わりごろのこと。宋という国に、ある夫婦が住んでいました。仲睦まじく暮らしていた二人を、あるとき悲劇が襲います。妻の美貌に目をとめた王が、彼女を強引に自分の後宮に入れ、夫を強制労働の刑に処してしまったのです。
悲しんだ妻は、ひそかに夫に手紙を送り、自殺をほのめかします。それを読んだ夫は、やがて自殺。妻も後を追い、高台から身を投げました。「せめて亡きがらだけは夫と一緒に葬ってください」という遺書を残して。
ところが、王はそれを許さず、二人を隣り合った別々のお墓に埋葬させました。そして、「お前たち夫婦はあくまで『相愛』だというのだな。ならば、墓を1つにしてみるがよい。それができれば、わしももう邪魔はすまい」とあざ笑ったのです。
すると不思議なことに、それぞれのお墓から木が1本ずつ生えてきました。2本は伸びるにつれ、土の中では根を重ね合わせ、地上では枝を絡ませていきます。さらには、つがいのオシドリが巣を作り、朝夕、悲しく鳴き交わすという状態に。宋の国の人々は二人の運命を哀れんで、この木を「相思樹」と呼んだ、ということです。
このお話から「相思相愛」が生まれたというわけではありませんが、なんとも悲しくも美しい物語ですよね。
≪参考リンク≫
≪おすすめ記事≫
四字熟語根掘り葉掘り32:乾杯の歌と「比翼連理」 はこちら
四字熟語根掘り葉掘り76:「枯木寒巌」にだって春は来る! はこちら
≪著者紹介≫
円満字二郎(えんまんじ・じろう)
フリーライター兼編集者。 1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。 著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『漢字の植物苑 花の名前をたずねてみれば』(岩波書店)など。最新刊『難読漢字の奥義書』(草思社)が発売中。
●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/
≪記事画像≫
『唐代図案集』を元に、筆者作成










