四字熟語根掘り葉掘り95:軍靴の響きと「自粛自戒」の苦労
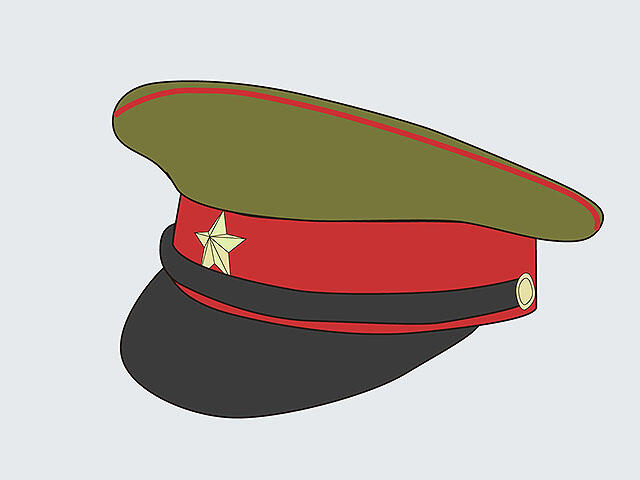
著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)
新型コロナウイルスの流行が始まってから、約1年半。その間ずっと、私たちは感染を拡大させるような行動を自粛するよう、言われ続けてきました。「自粛疲れ」は、程度の差こそあれ、だれもが感じていることでしょう。
以前、「自粛」ということばの使われ方について調べていて、ちょっとおもしろい表現に出会ったことがあります。いわゆる「戦前」の文章に時折出て来るフレーズ、「自粛自戒(じしゅくじかい)」です。
この表現が目に付くのは、1936(昭和11)年、ちょうど、二・二六事件が起こった直後から。長引く不況のもと、政治家や財閥への不満が社会に渦巻いていた時代です。
二・二六事件は、陸軍の一部の青年将校たちが引き起こしたクーデター未遂ですから、軍部がその監督責任を感じて「自粛自戒」したのはもちろんのことでした。しかし、ことはそれだけでは収まらず、政治家や財閥も反省する必要があるとして「自粛自戒」が求められるようになります。
やがて、その風潮は国民全体を覆っていきました。たとえば、政府が家主に対して、家賃の値上げを「自粛自戒」するように呼びかけるとか。経営サイドから髪形についての「自粛自戒」を強要された、百貨店の女性店員もいたようです。本来ならば自分から進んでするものなのに、それが他人から押しつけられるようになるあたりは、いつの時代も変わらないようです。
「自粛自戒」のちょっとした流行が続いたのは、太平洋戦争が敗戦で終わるまでのこと。その後は使用例が急激に減少します。現在では、この表現を載せている国語辞典や四字熟語辞典は、ほとんどありません。コロナ禍の今と同じように「自粛」の必要性が叫ばれる時期は過去にもありましたが、その流れに乗って「自粛自戒」が華々しく復活することはなかったのです。
つまり、かつてはよく使われた「自粛自戒」は、結局は表現として定着することはできず、だれもが認める四字熟語にはなりそこねたわけです。それはなぜなのでしょうか?
その理由を探るのはむずかしいことですが、単に「自粛」とだけ言うよりも、「自戒」を付け足して「自粛自戒」と言う方が、意味が強くなることは明らかです。だとすれば、昭和のあの時代の人たちが強いられていた「自粛自戒」は、現在の私たちに求められている「自粛」よりもさらに息苦しいものだったのではないでしょうか……。
だからといって、私たちの「自粛疲れ」が少しでも軽くなるわけではありません。ただ、私自身は、両親や祖父母が経験した戦争の時代の苦労を思いつつ、もう少し、我慢を続けてみようと思っています。
≪参考リンク≫
漢字ペディアで「自粛自戒」を調べよう
漢字ペディアで「自粛」を調べよう
漢字ペディアで「自戒」を調べよう
≪おすすめ記事≫
四字熟語根掘り葉掘り60:「不要不急」の判断基準 はこちら
四字熟語根掘り葉掘り73:数をめぐって「自縄自縛」 はこちら
≪著者紹介≫
円満字二郎(えんまんじ・じろう)
フリーライター兼編集者。 1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。 著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)、『漢字の植物苑 花の名前をたずねてみれば』(岩波書店)など。最新刊『難読漢字の奥義書』(草思社)が発売中。
●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/
≪記事画像≫
筆者作成










