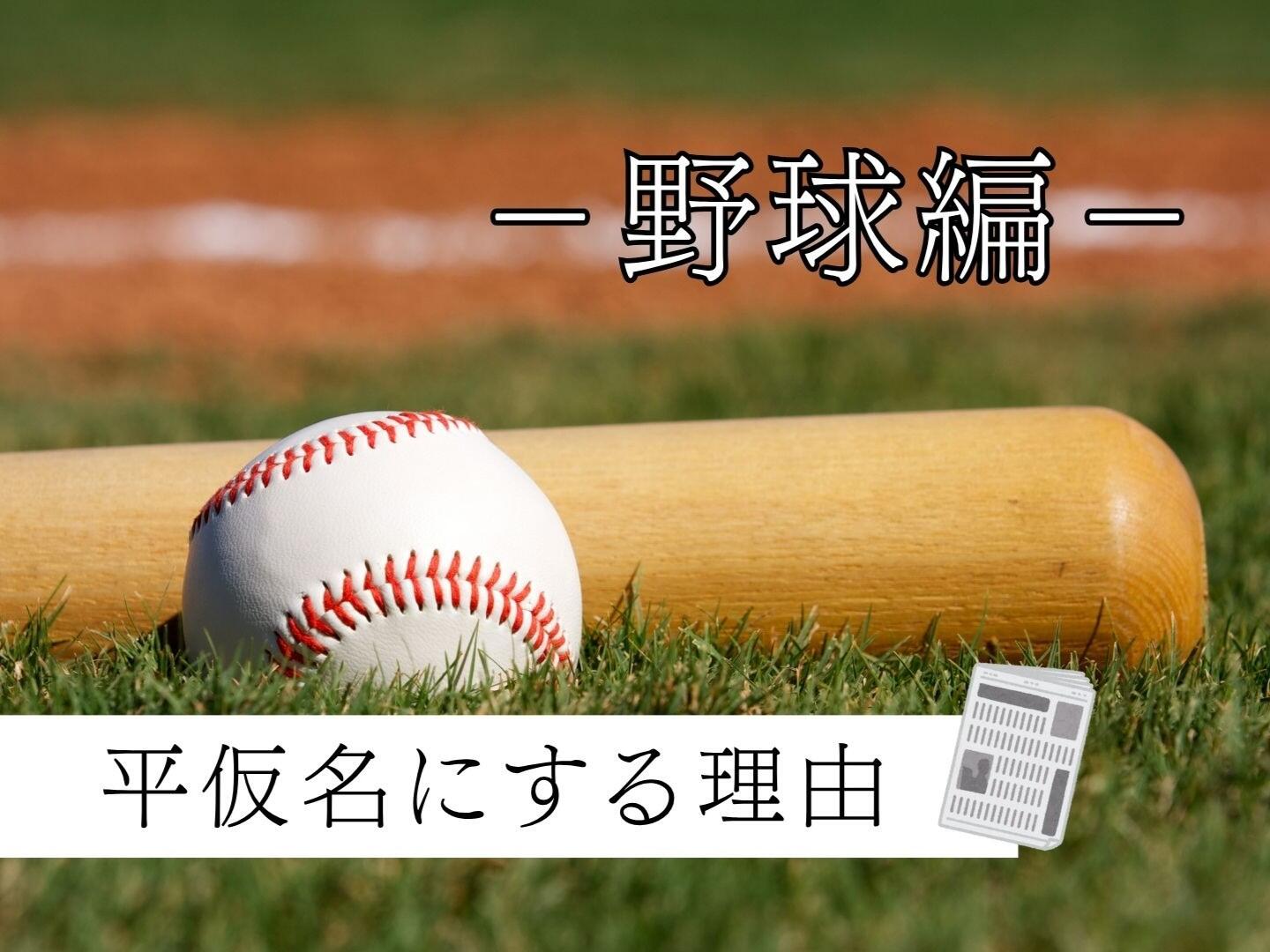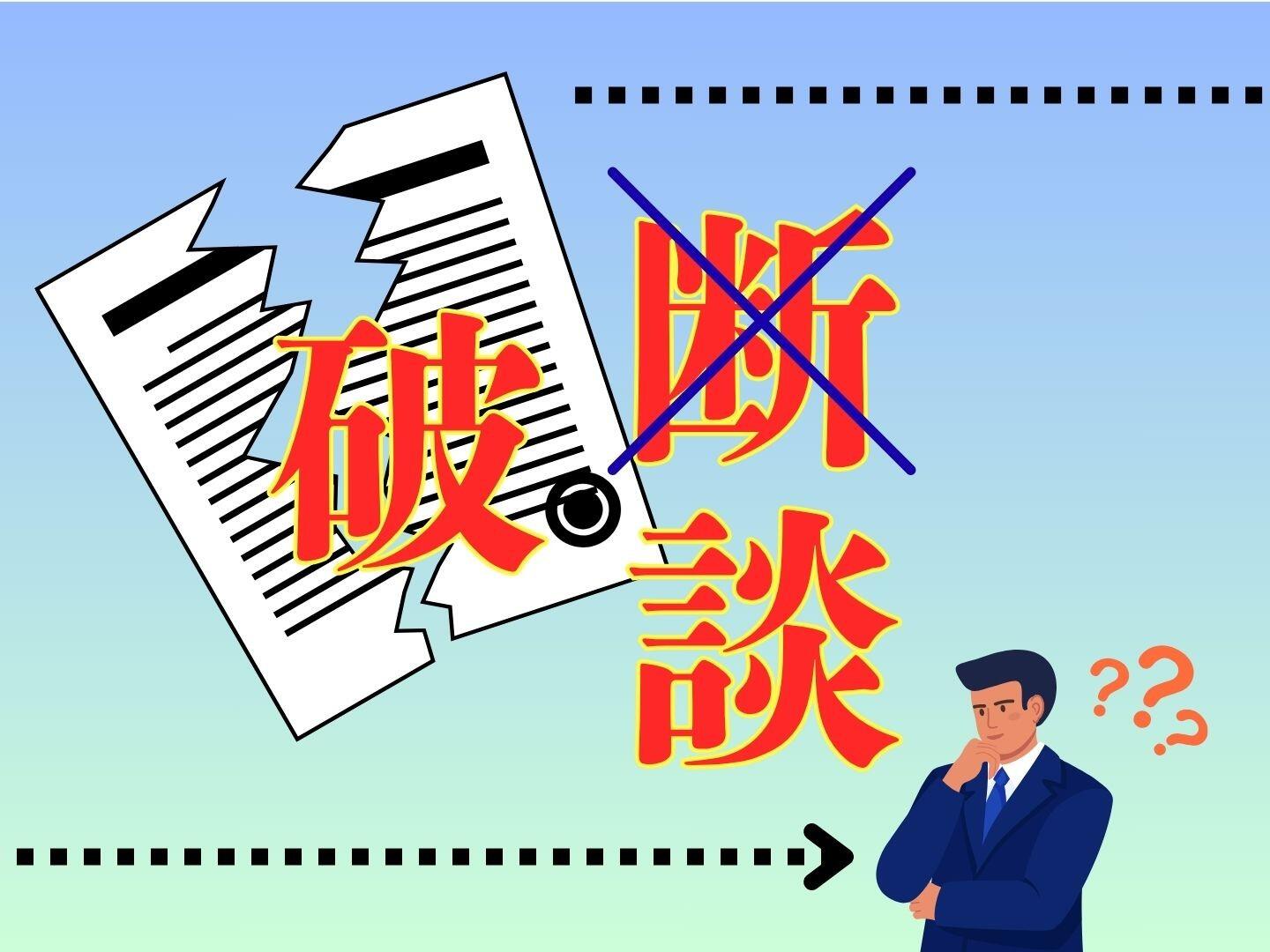新聞漢字あれこれ166 旧字→新字「新聞の漢字を考える」

著者:小林肇(日本経済新聞社 用語幹事)
3月1日、日本経済新聞社大阪本社で行われた第81回大阪NIEセミナー(大阪NIE推進協議会など主催)で「新聞の漢字を考える」というテーマで講演をしてきました。
NIEとは「Newspaper in Education(教育に新聞を)」の略で、学校などで新聞を教材として活用する活動です。セミナーには教育関係者を中心に一般読者の方々を含む約50人が参加。そこで、新聞表記の基準、新聞漢字の問題点、表外漢字などについて話をしました。
質疑応答のとき、読者の方から、新聞が人名の旧字を新字(常用漢字)に直す理由を問われました。この方は褒章を受けたときの新聞で、名前の「將」の字が「将」になって掲載されたとのことで、説明を求めてきたのでした。
講演の中でも話しましたが、幅広い年代の人たちを読者に持つ新聞は、現在標準とされる漢字を使うことを原則としています。これは、学校教育で習うような字を使うことで、記事をはやく、わかりやすく読んでもらうという趣旨によります。こうした運用は新聞に限ったことではありません。例えば、渋沢栄一(1840~1931)の生きていた時代は今のような常用漢字を使っていたわけではありませんが、現在の教科書や国語辞典では「澁澤榮一」のような表記はせずに「渋沢栄一」としています。これも読み手へのわかりやすさを意識したもので、同じく1万円札も「渋沢栄一」と表記しています。
これは「澁澤榮一」のような旧字体を使う表記を否定していることではありません。名前は個人のものとして尊重されるべきであるからです。ただ、名前は個人のものですが、文字(漢字)は社会的なもの。字を通して情報をやりとりし、相互が理解するためには、現在標準とされるわかりやすい字を使いましょう、という考え方になるわけです。
こうした説明は理解いただけたようですが、社会生活で役所関係や金融機関の書類に名前を書くような場合は、旧字体を使わざるをえないという現実もあります。旧字体の部分字形は複雑なこともあり、質問者の方は「相手に『將』の字を説明しても通じないことがある」と言い、寂しそうに「改名したほうがいいのかな」と話されていたのには、私も考えさせられました。
わかりやすさと正確性。どちらか一方だけが正しく、もう一方が誤りだというわけではありません。旧字と新字の関係を分断することなく、どちらも同じ字であり、ケース・バイ・ケースで使い分けてよいものであるとの考え方を、NIEで共有できるようにすることも大事になってくると思います。
次回、新聞漢字あれこれ第167回は4月16日(水)に公開予定です。
≪参考資料≫
金武伸弥『新聞と現代日本語』文春新書、2004年
≪参考リンク≫
「日経校閲X」 はこちら
≪おすすめ記事≫
新聞漢字あれこれ24 「株式曾社」のどこが変? はこちら
新聞漢字あれこれ141 「麴」と「麹」どちらを使うか はこちら
≪著者紹介≫
小林肇(こばやし・はじめ)
日本経済新聞社 用語幹事
1966年東京都生まれ。1990年、校閲記者として日本経済新聞社に入社。2019年から現職。日本新聞協会新聞用語懇談会委員。漢検漢字教育サポーター。漢字教育士。 専修大学協力講座講師。
著書に『マスコミ用語担当者がつくった 使える! 用字用語辞典』(共著、三省堂)、『方言漢字事典』(項目執筆、研究社)、『謎だらけの日本語』『日本語ふしぎ探検』(共著、日経プレミアシリーズ)、『文章と文体』(共著、朝倉書店)、『日本語大事典』(項目執筆、朝倉書店)、『大辞林第四版』(編集協力、三省堂)などがある。2019年9月から三省堂辞書ウェブサイトで『ニュースを読む 新四字熟語辞典』を連載。