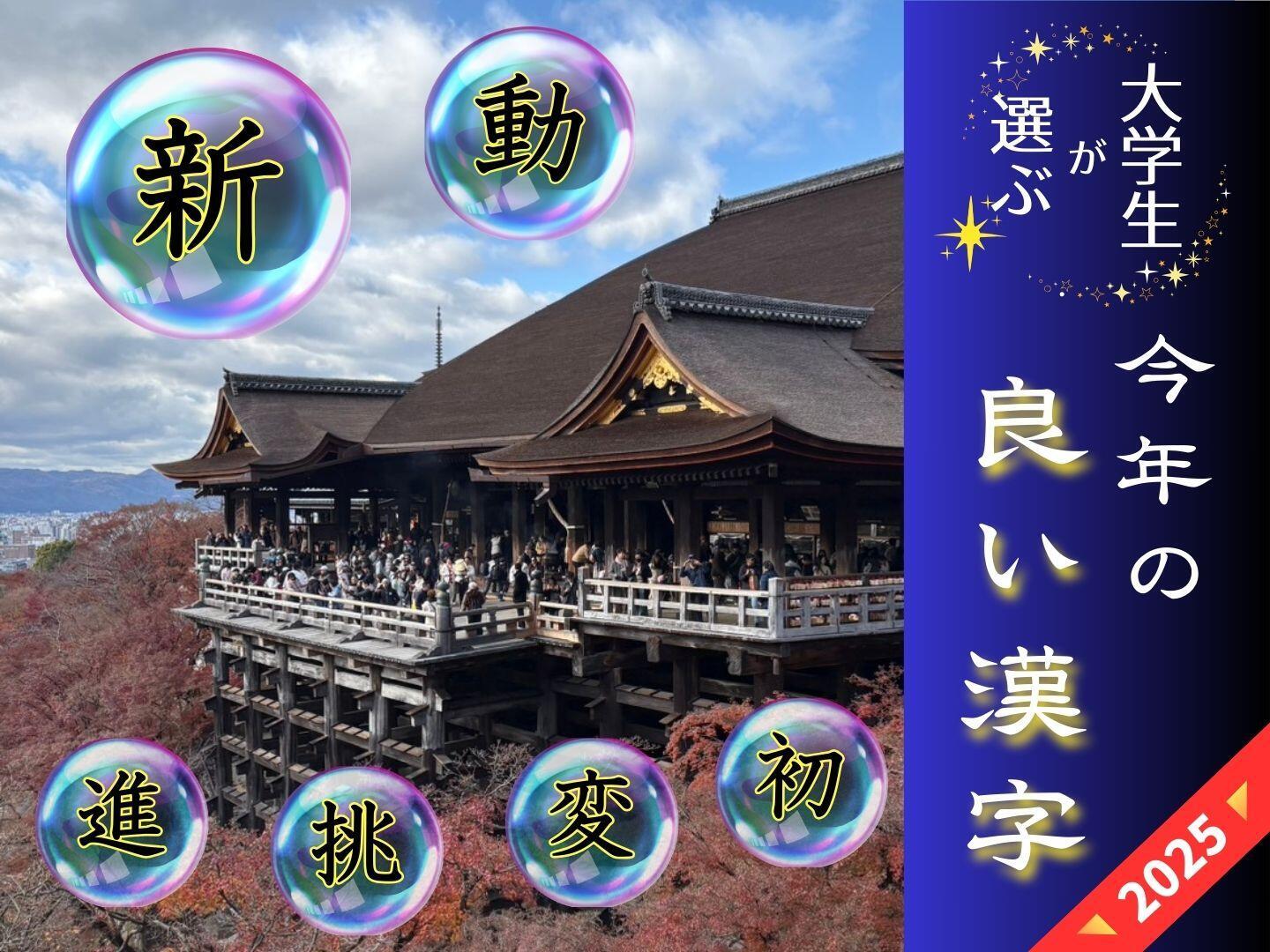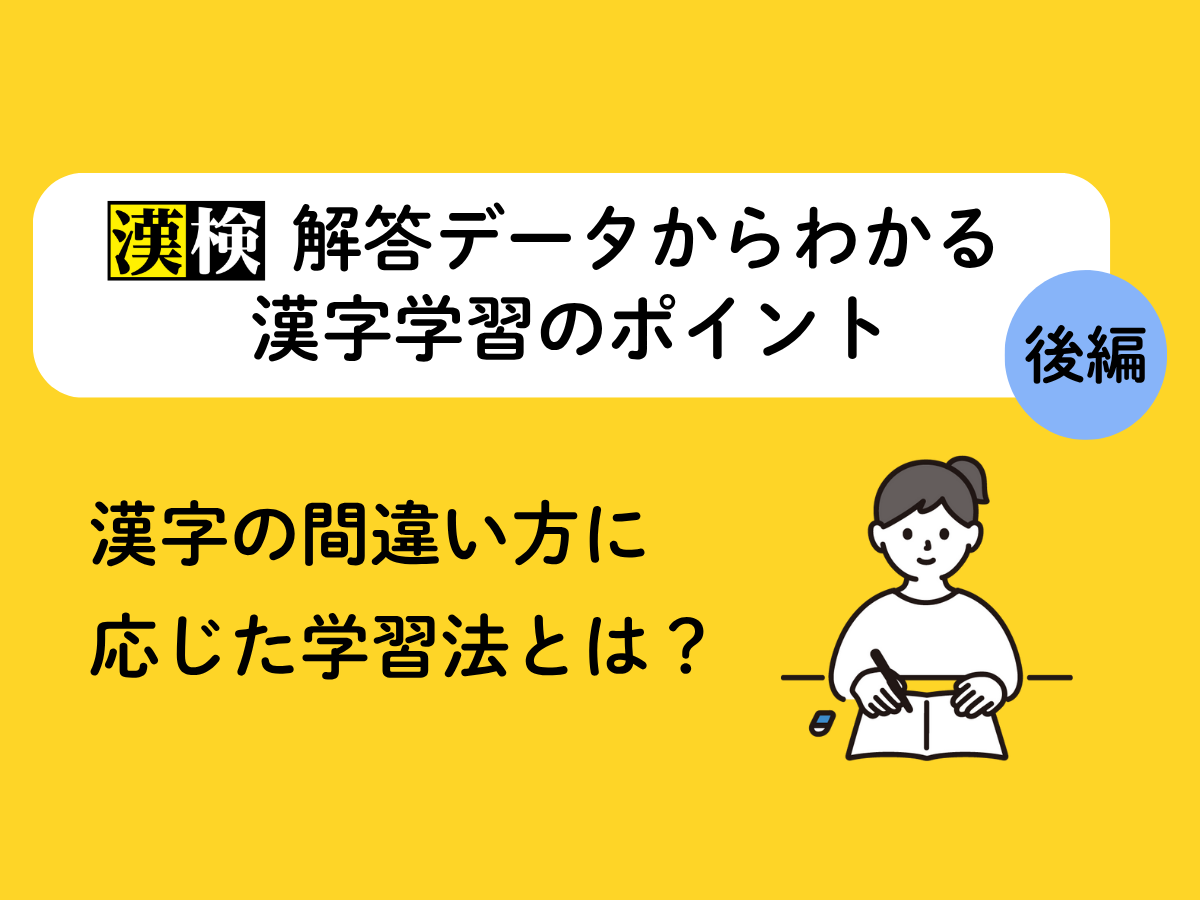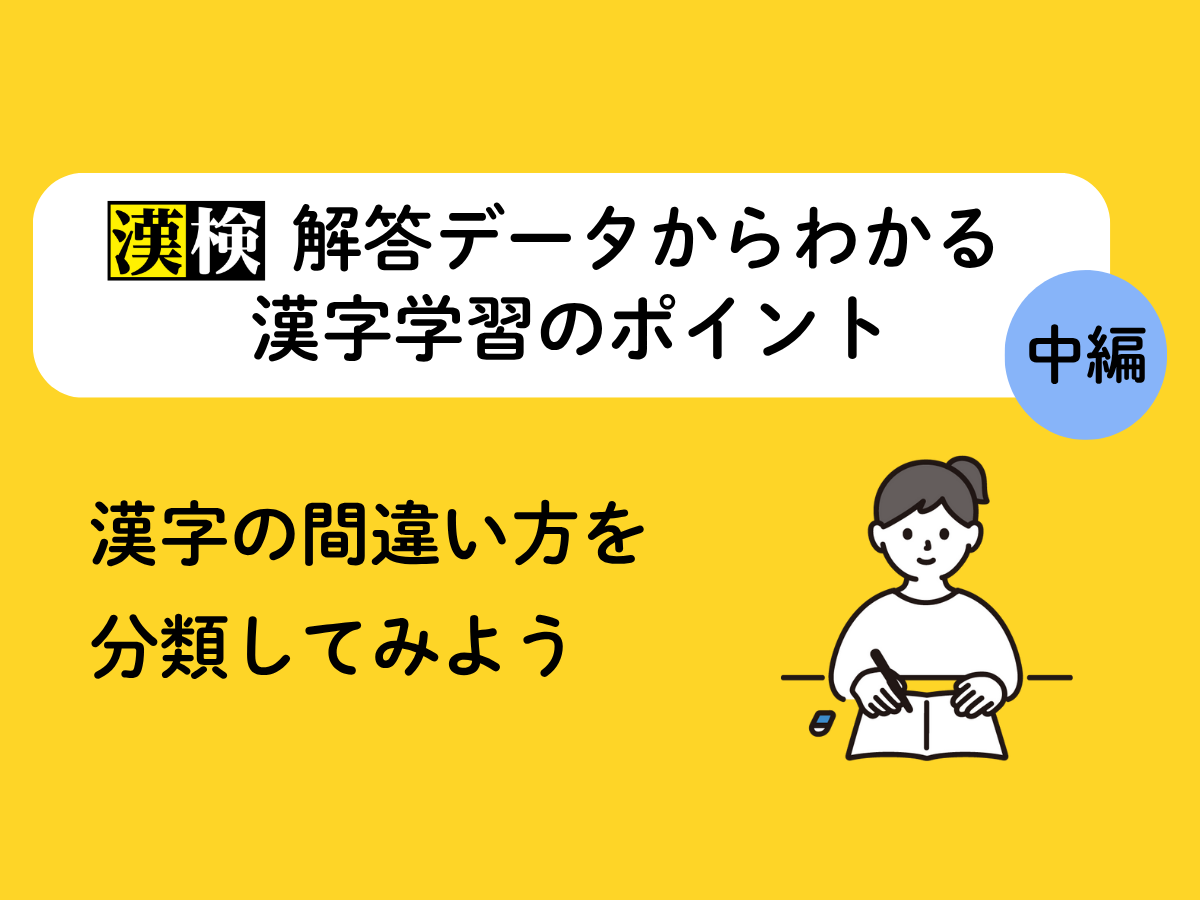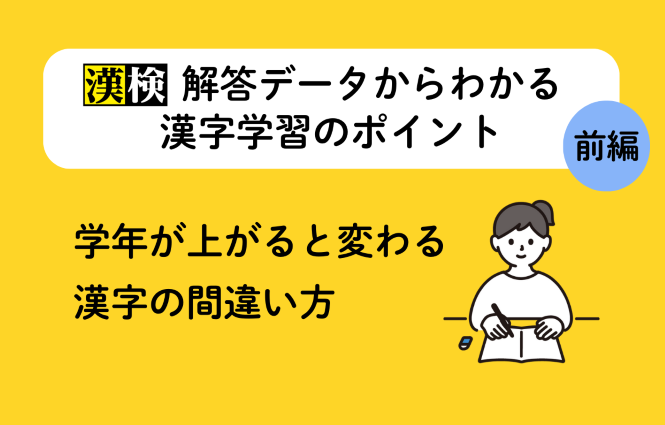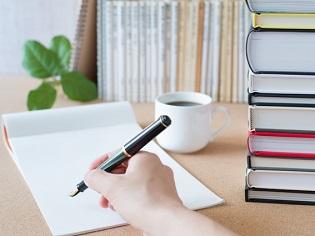手書き文字の基準が、より具体的にわかりやすくなる!

2016年2月29日に文化庁の文化審議会国語分科会から「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)」が発表されました。全国紙でも紹介されたので、すでにご存じの方も多いでしょう。
この指針では、
・手書き文字と印刷文字の表し方には、習慣の違いがあり、一方だけが正しいのではない。
・字の細部に違いがあっても、その漢字の骨組みが同じであれば、誤っているとはみなされない。
ということが、具体的な例や説明とともにわかりやすく示されています。
例えば、皆さんはこんな経験はないでしょうか?
・漢字の書き取りテストを受けたら、「ここははねてはいけません」とか「この点はこちら向きに打ちましょう」、「ここははらいましょう」など細かい部分ばかり指摘されてバツにされた。
・「令」という字を手書きしたときに最後の2画を「マ」のように書いたら、印刷された文字と同じ形で書くようにと言われてしまった。
これらは、漢字の「字体」と「字形」についての誤解が生んだ問題といえます。
「字体」とは、その文字特有のの骨組みに当たるものです。
「字形」とは、それを手書きしたときに現れる形のことを指します。
同じ「字体」を書き表したとしても、100人書けば100通りの「字形」があることになります。
もともと、当用漢字表の時代から「その文字特有の骨組みが読み取れるのであれば、誤りとはしない」という方針がとられてきていましたが、近年、パソコン等の普及により印刷文字の字形だけが正しいと誤解する人が増えたり、手書きする際にとめ、はねなどの細かい部分に必要以上の注意が向けられているというような問題点が指摘されてきました。
今回の指針は、そうした問題を解決するべく、常用漢字2136文字すべてについて、手書き文字の具体例が示され、詳しい解説やQ&Aが含まれた内容になっています。
文字は他者との意思伝達を行うために用いられるものですので、相手に読みやすい文字を書くという配慮は必要です。
漢字を習い始めた時は、とめ、はね、はらいなどを意識しながら文字を整えて書く練習も大切です。
ただ、あまりに細かい字形の違いにこだわりすぎると、文字を書くこと自体が面倒なものに感じてしまうかもしれません。
特に、漢字を毎日学んでいるお子さんたちには、漢字を読めた、書けたという喜びを味わいながら、楽しく学んでほしいですね。
この指針に対する理解が広がれば、漢字を手書きすることへの苦手意識が薄まるのではないかと期待できます。
もし、お子さんが書いたノートを見ていて、「こんな書き方でもいいのかな?」と気になることがあれば、今回発表された指針を参考にしてみてください。
なお、4月には指針の内容をまとめた冊子も配布されるようです。
≪参考リンク≫
文化庁ホームページ「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)について」