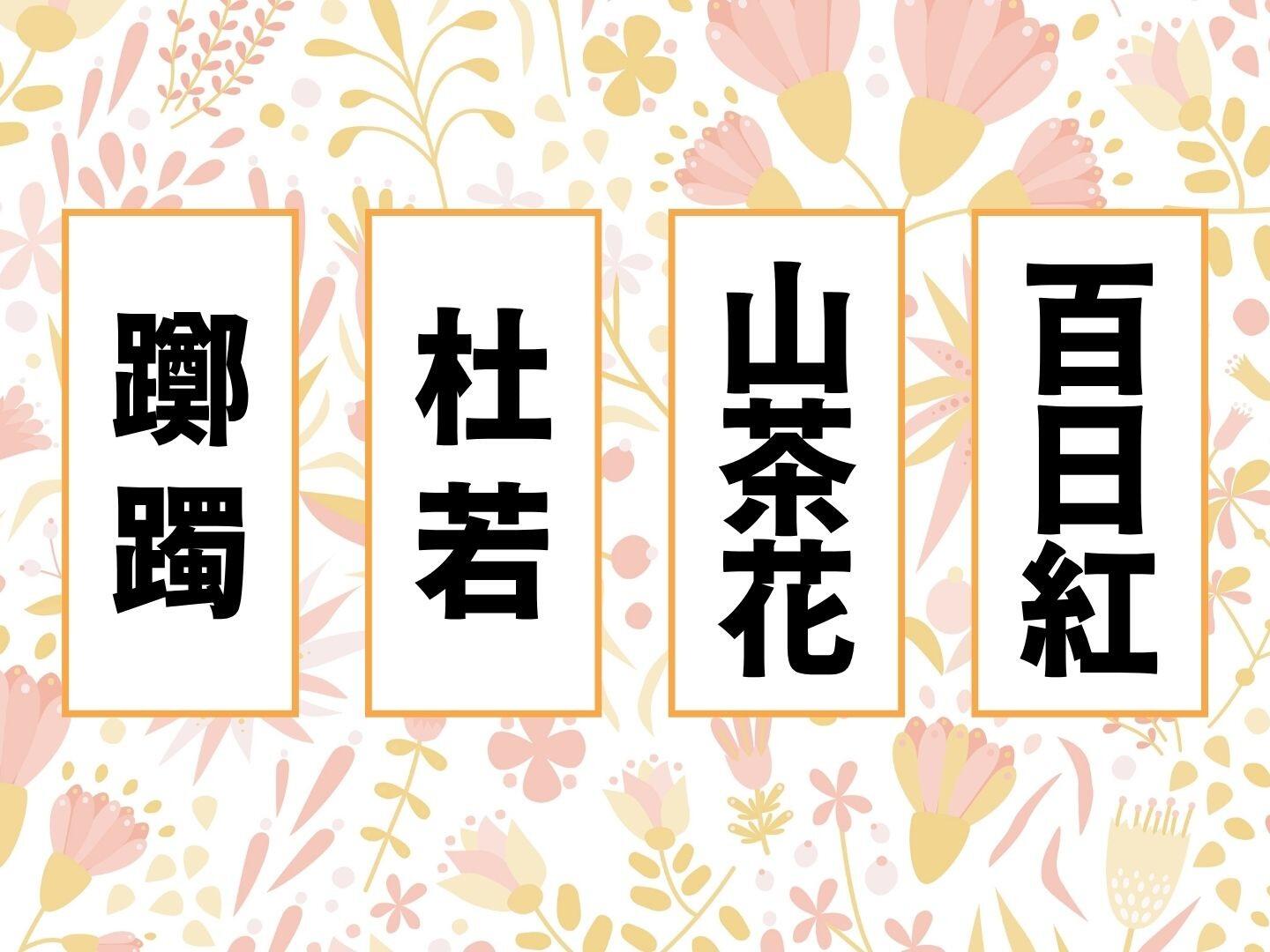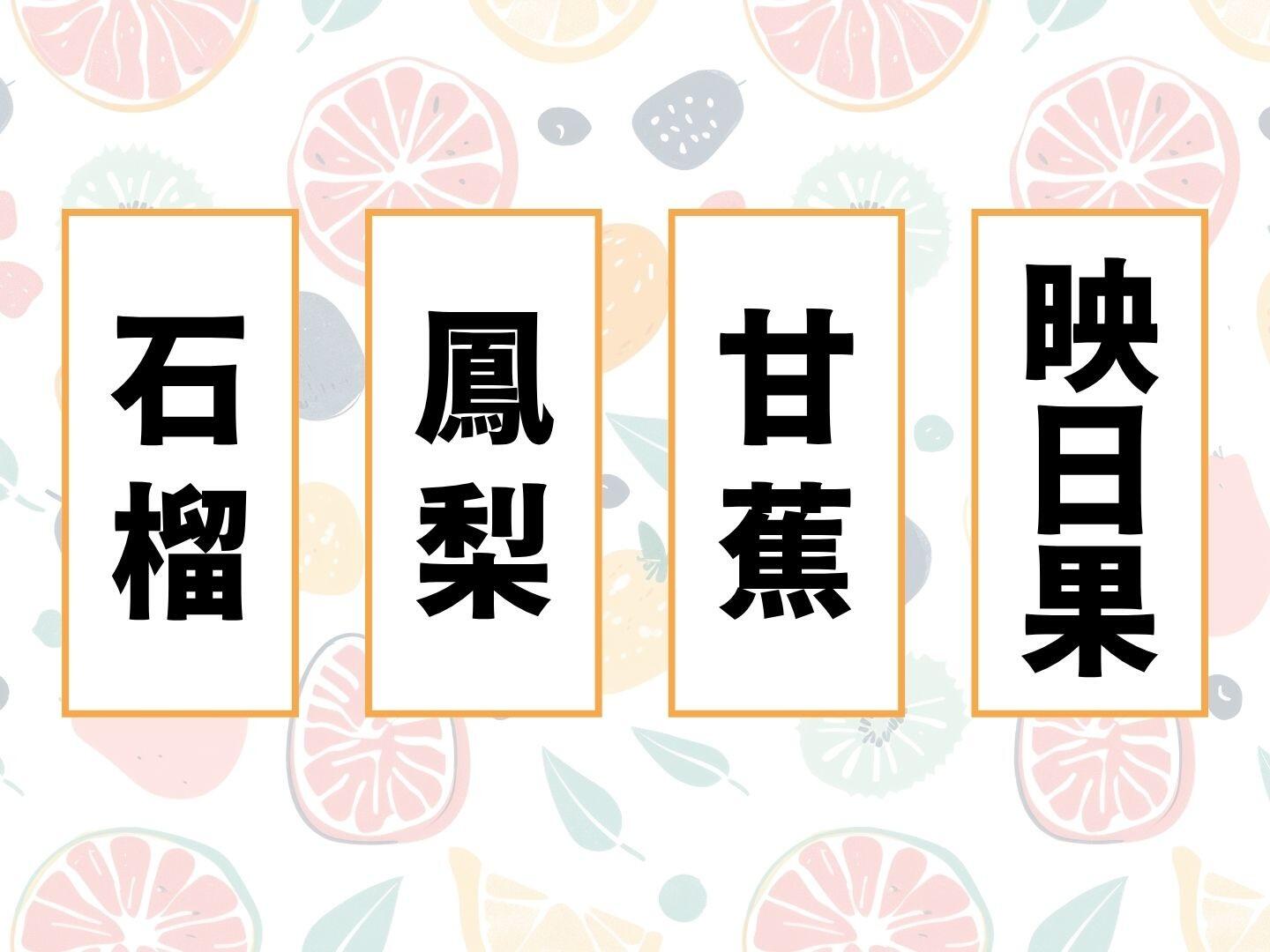歴史・文化難読漢字
「ひじき」を漢字で書くと?

9月15日は「ひじきの日」(三重県ひじき協同組合制定)だそうです。このひじきを漢字で書くと、ある動物の漢字が含まれます。
それは、「鹿」または「羊」です。
「ひじき」は漢字では、「鹿尾菜」や「羊栖菜」などと書かれます。ではどうして「鹿尾菜」という表記となったのでしょう。江戸時代の本草学者である人見必大(ひとみさだすく)によると、
「鹿に尾はなく、鹿の短く黒い毛がこの藻に似ているから(鹿尾菜と)名付けたものかもしれない」(『本朝食鑑』巻3)
とのことです。
確かに、鹿の尻尾の周りには黒い毛が生えていますね。

なお、有名な古典『伊勢物語』には、想いを寄せる女性に、男がひじきといっしょに次のような和歌を贈る話があります。
「思ひあらば むぐらの宿に 寝もしなむ ひじきものには袖をしつつも」
(日本語訳) 私を思ってくださる愛情がおありなら、荒れた家でも満足です。あなたと二人、袖(そで)を重ね引き敷いて、心あたたかにそこで共寝(ともね)をしましょう (『新日本古典文学大系17』岩波書店より)
「引敷物」に「ひじきも(藻)」の意味を掛けた和歌です。 実用的なひじきと恋愛の歌、現代人にはなかなかイメージが結びつきませんね。
甘いお出汁で野菜や揚げなどと一緒に炊くととってもおいしいひじき。食べる時には、漢字の事も少し思い出してくださいね。
≪参考リンク≫
≪記事画像≫
記事上部画像:ささざわ / PIXTA(ピクスタ)
記事内画像:can / PIXTA(ピクスタ)