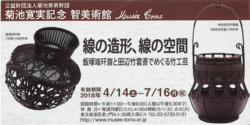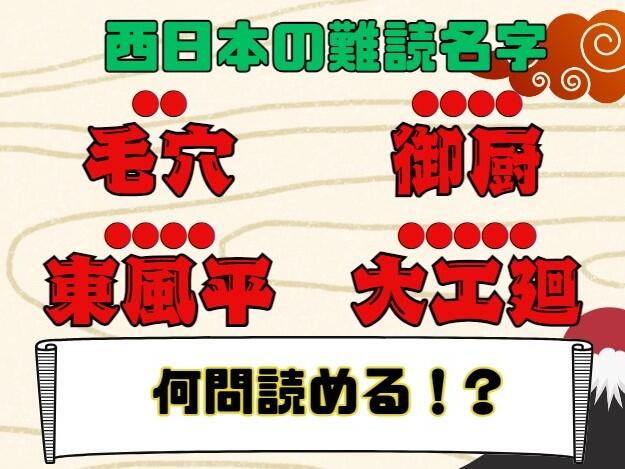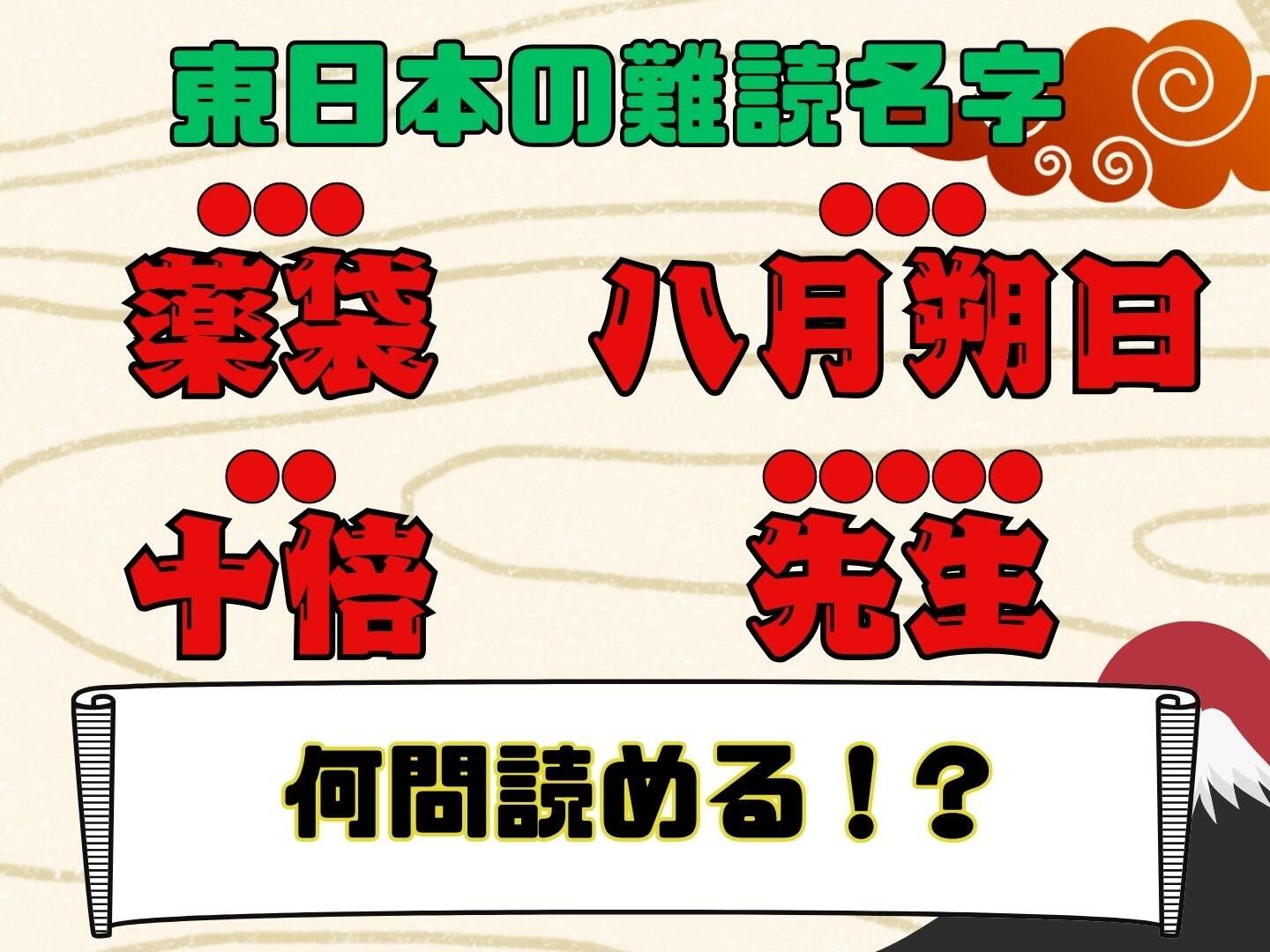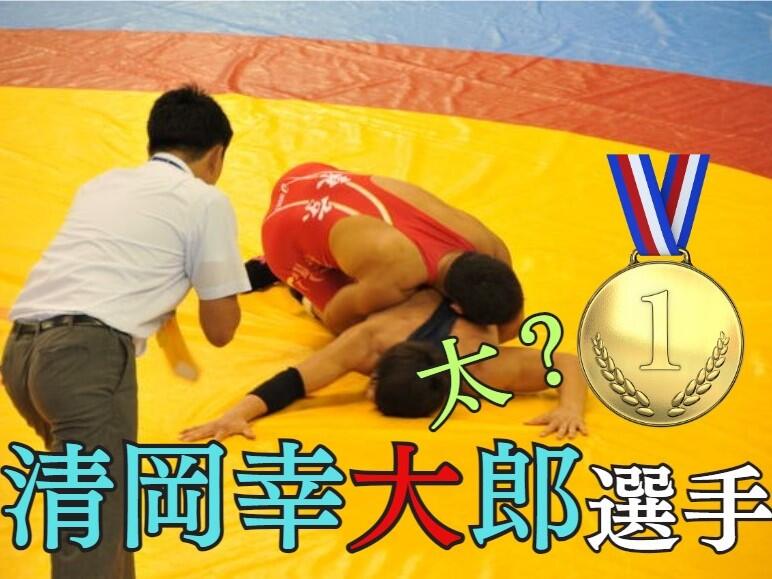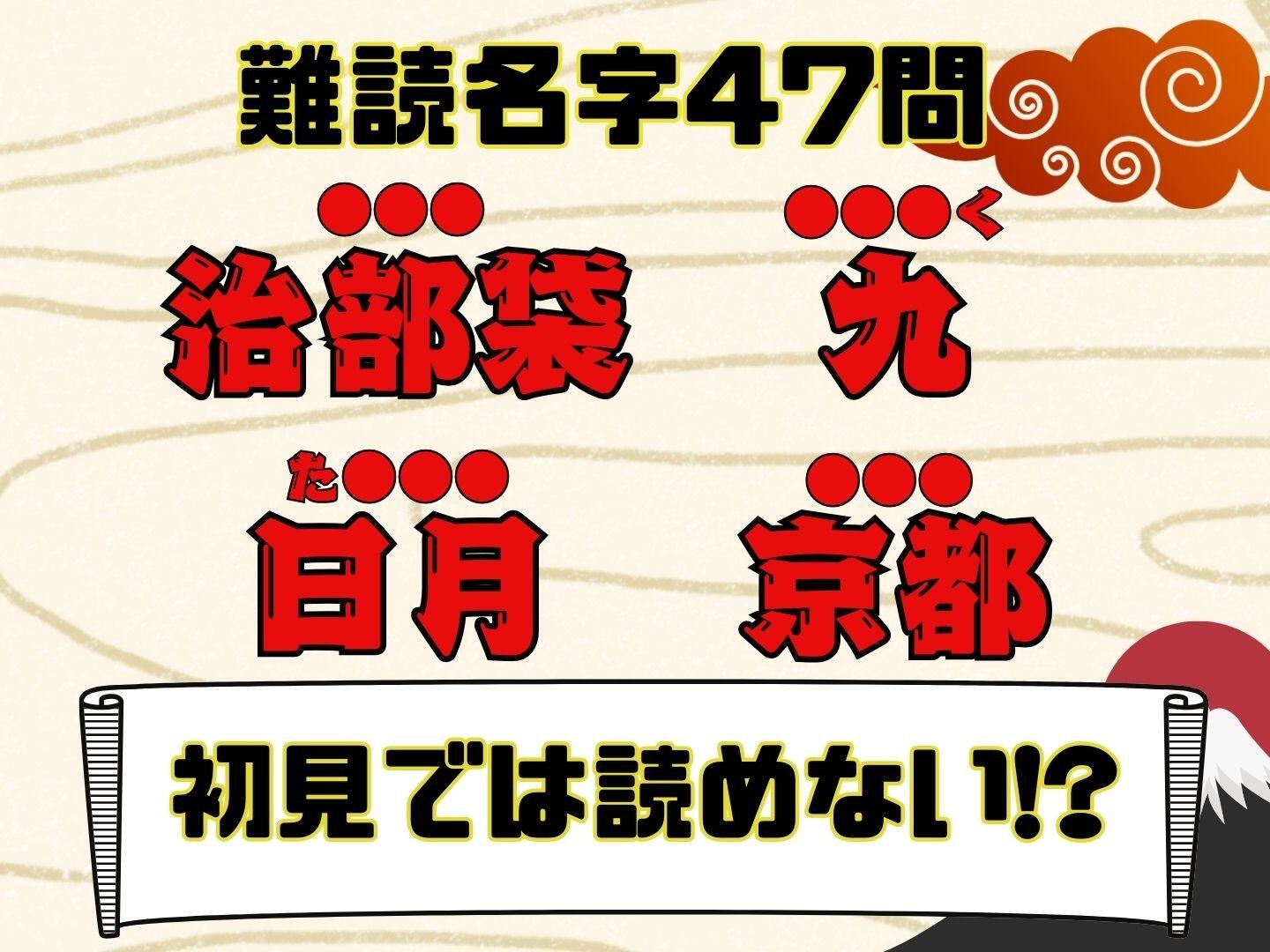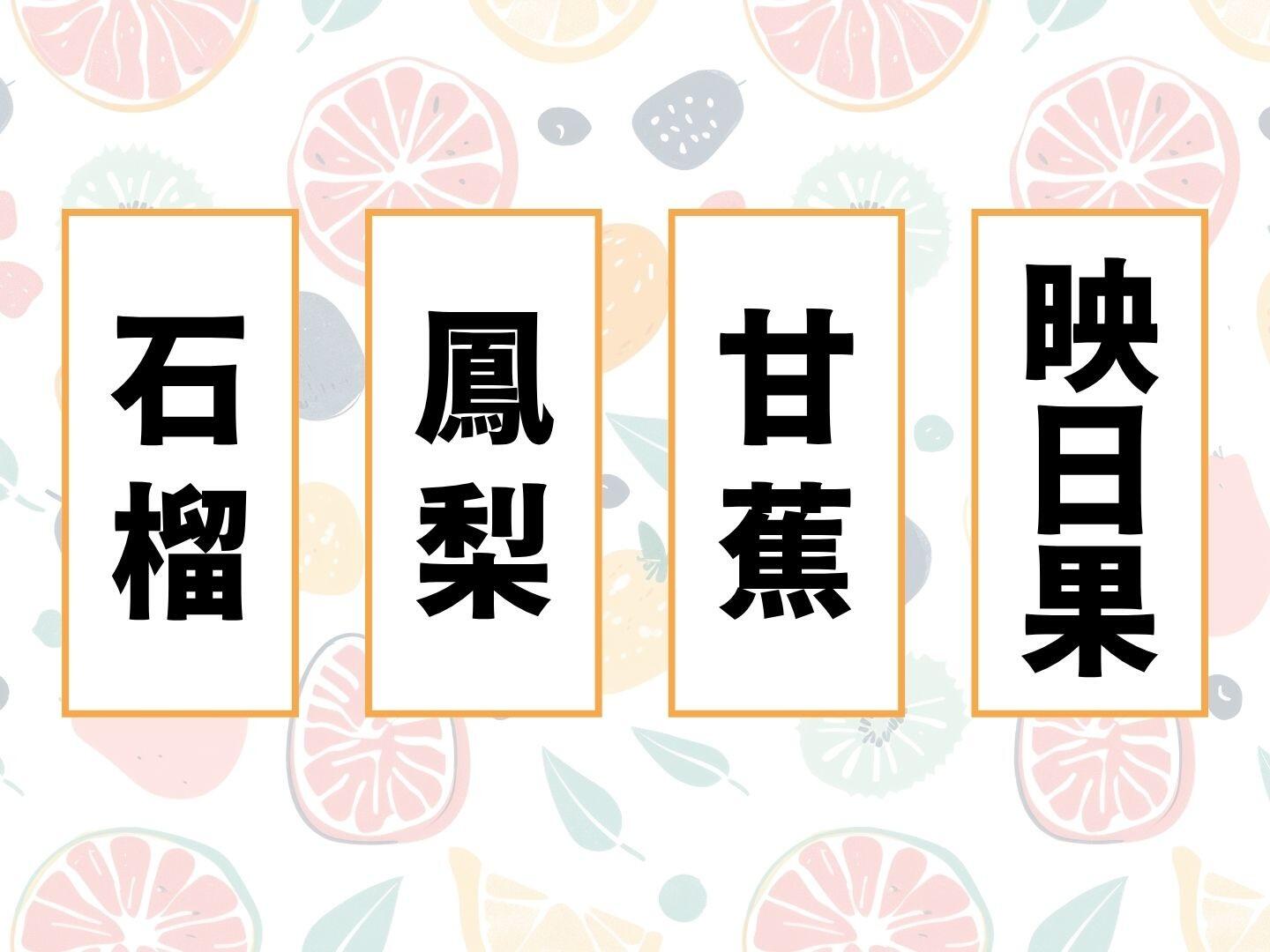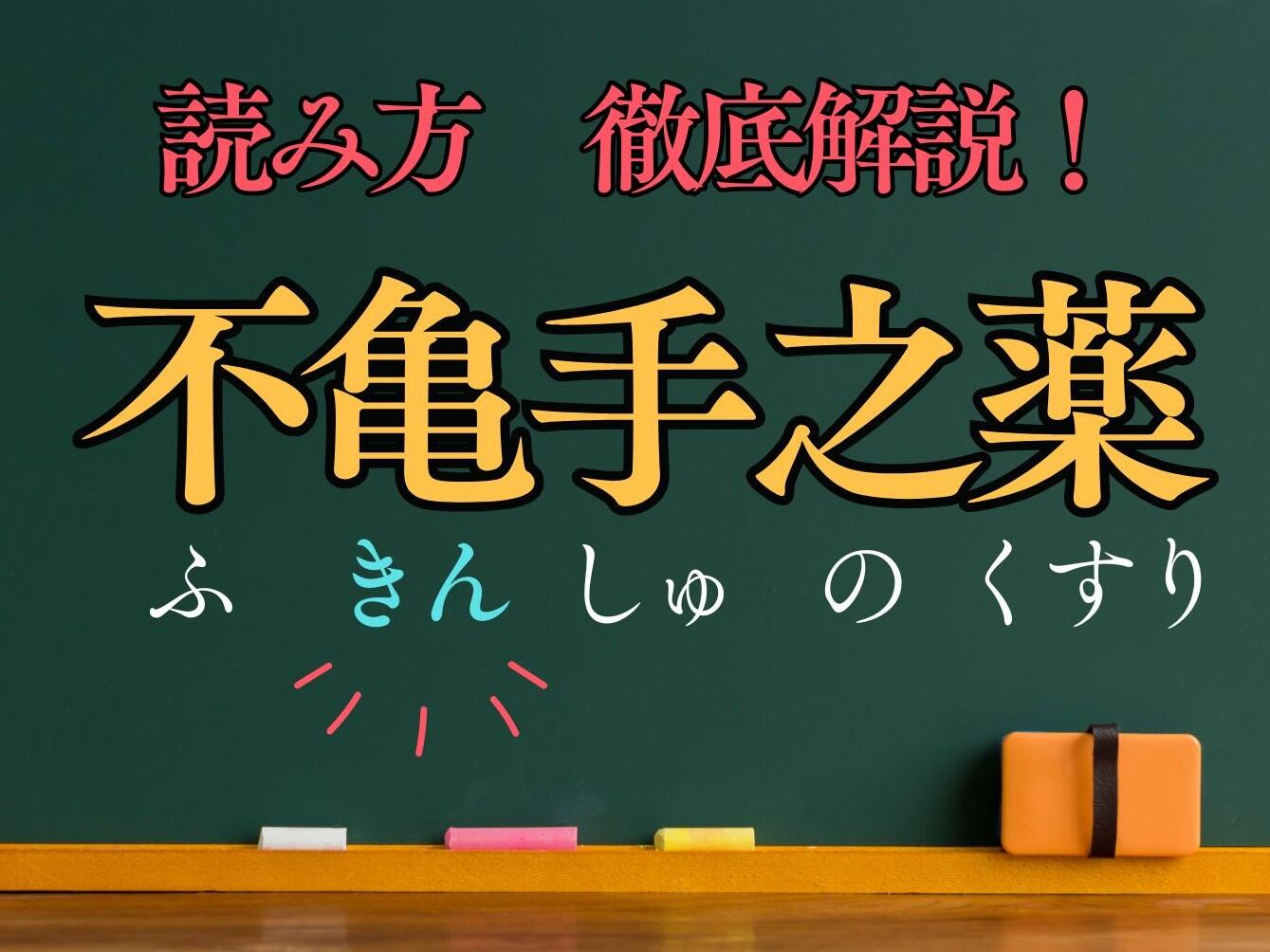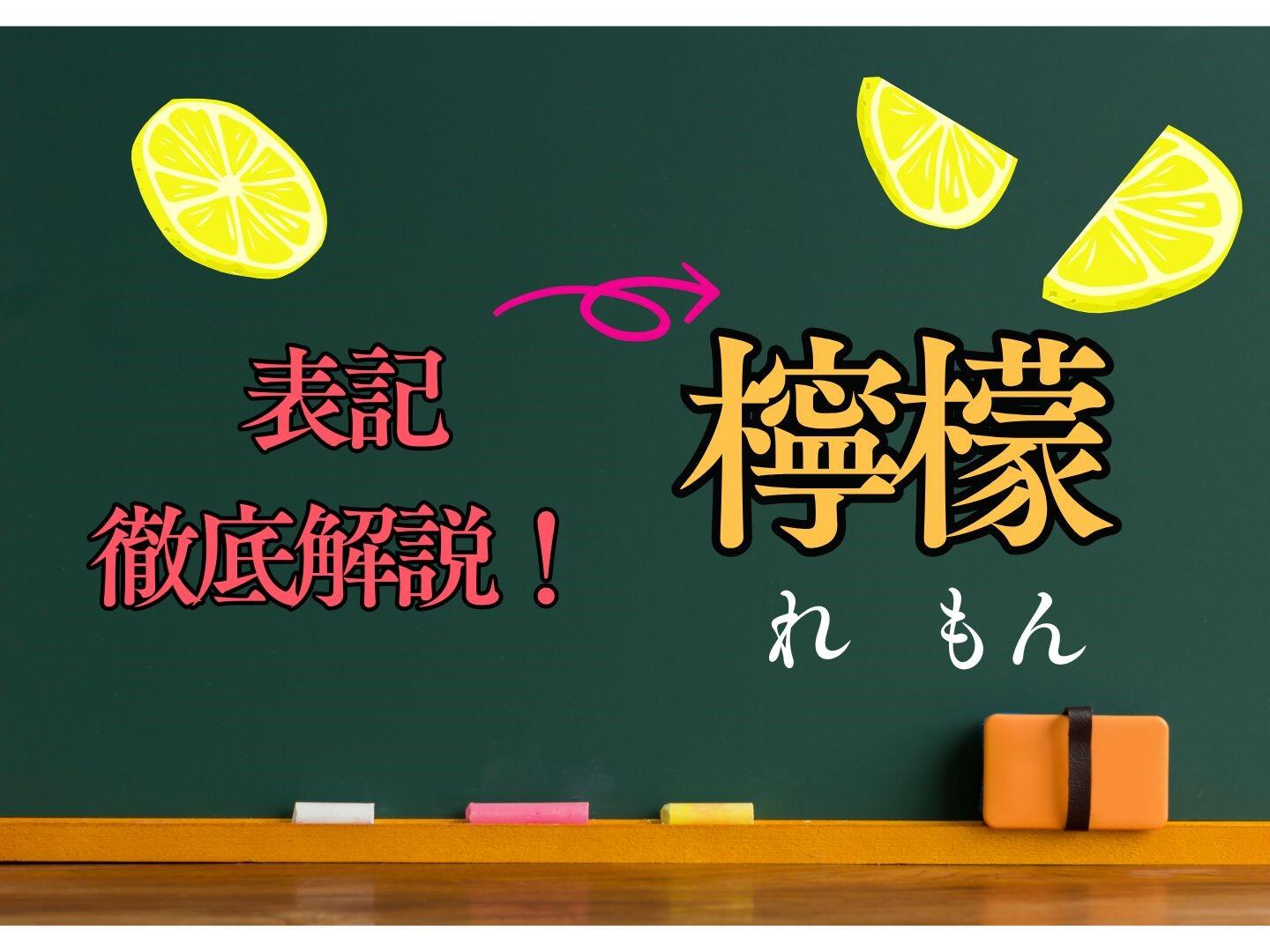新聞漢字あれこれ36 竹工芸家の名前が表すもの

著者:小林肇(日本経済新聞社 用語幹事)
毎年1月1日付の新聞は別刷りの特集などがあって読み応えがあります。日本経済新聞では今年も100ページを超える紙面でした。そうした膨大な量の文字の中に「![]() (かん)」という字が1つ見えました。
(かん)」という字が1つ見えました。
朝刊第4部の文化特集の記事に「東京国立近代美術館工芸館は金沢市に移転する。(中略)飯塚琅![]() 斎や佐々木象堂の作品など1900点以上を移転する」とありました。この竹工芸家、飯塚琅
斎や佐々木象堂の作品など1900点以上を移転する」とありました。この竹工芸家、飯塚琅![]() 斎(1890~1958)の「
斎(1890~1958)の「![]() 」の字を初めて見たのは2011年のことでした。6月2日付朝刊文化面に載った琅
」の字を初めて見たのは2011年のことでした。6月2日付朝刊文化面に載った琅![]() 斎の孫である飯塚万里さんの記事を読み、琅
斎の孫である飯塚万里さんの記事を読み、琅![]() 斎の次男で人間国宝だった父親の飯塚小
斎の次男で人間国宝だった父親の飯塚小![]() 斎(1919~2004)とともに、名前に「
斎(1919~2004)とともに、名前に「![]() 」の字を使っていることに興味を持ったのです。
」の字を使っていることに興味を持ったのです。
JIS第3水準の〝超1級漢字〟※である「![]() 」を大漢和辞典で引くと「琅
」を大漢和辞典で引くと「琅![]() は、玉に次ぐ美石」とありました。では「なぜ、美石と竹に関係があるのだろう?」と疑問に思いましたが、気にはなりつつもその先は調べずに終わり、作品を見れば分かるかもしれないとは漠然と思っていました。
は、玉に次ぐ美石」とありました。では「なぜ、美石と竹に関係があるのだろう?」と疑問に思いましたが、気にはなりつつもその先は調べずに終わり、作品を見れば分かるかもしれないとは漠然と思っていました。
そして7年後、2018年4~7月に菊池寛実記念 智美術館で「線の造形、線の空間 飯塚琅![]() 斎と田辺竹雲斎でめぐる竹工芸」展が開催されていたので、行ってみました。展示室に入って周囲を見渡すと、「『琅
斎と田辺竹雲斎でめぐる竹工芸」展が開催されていたので、行ってみました。展示室に入って周囲を見渡すと、「『琅![]() 』とは美しい竹の意で、『琅
』とは美しい竹の意で、『琅![]() 斎』は篆刻家の蘆野楠山から贈られた号」と書かれたプレートがあり、喜び勇んで手帳にメモをした私。そのまま帰ろうと出口に向かった時に、作品を見ていないことに気づき、慌てて展示室に戻り鑑賞したことを覚えています。
斎』は篆刻家の蘆野楠山から贈られた号」と書かれたプレートがあり、喜び勇んで手帳にメモをした私。そのまま帰ろうと出口に向かった時に、作品を見ていないことに気づき、慌てて展示室に戻り鑑賞したことを覚えています。
実は「琅![]() 」は国語辞典にも載っている語で、ご存じの方にとっては当たり前の語なのかもしれません。日本国語大辞典には1番目の意味として「碧玉に似た美しい宝石。また、美しいもののたとえ。江戸時代以来濃緑色の硬玉の勾玉(まがたま)をさすが、同じ色の硬玉・軟玉のものを広くいうこともある」と示した次に、2番目の意味として「(その色彩・光沢から)美しい竹の称」とありました。色が関係しているのかと、これを読んで納得。私は「
」は国語辞典にも載っている語で、ご存じの方にとっては当たり前の語なのかもしれません。日本国語大辞典には1番目の意味として「碧玉に似た美しい宝石。また、美しいもののたとえ。江戸時代以来濃緑色の硬玉の勾玉(まがたま)をさすが、同じ色の硬玉・軟玉のものを広くいうこともある」と示した次に、2番目の意味として「(その色彩・光沢から)美しい竹の称」とありました。色が関係しているのかと、これを読んで納得。私は「![]() 」の字ばかり気にしていて「琅」から辞書を引こうとしていなかったのです。そのため意味が分かるまで7年もかかってしまいました。基本的なことをし忘れるなんて実に情けない。
」の字ばかり気にしていて「琅」から辞書を引こうとしていなかったのです。そのため意味が分かるまで7年もかかってしまいました。基本的なことをし忘れるなんて実に情けない。
小さいことにこだわりすぎて全体をとらえられない例えとして「木を見て森を見ず」とよく言いますが、私の場合は「字を見て語を見ず」と言いましょうか。とはいえ、すぐに意味が分からなかったからこそ、7年たって琅![]() 斎や小
斎や小![]() 斎の作品を直接鑑賞する機会を得られたのかもしれませんね。今度は作品鑑賞を第一の目的に金沢に行ってみることにしましょう。
斎の作品を直接鑑賞する機会を得られたのかもしれませんね。今度は作品鑑賞を第一の目的に金沢に行ってみることにしましょう。
※超1級漢字:JIS第1・第2水準以外の漢字のこと。筆者の造語。漢検1級の出題範囲である約6000字がJIS第1・第2水準を目安としていることから。
≪参考資料≫
菊池寛実記念 智美術館「『線の造形、線の空間 飯塚琅![]() 斎と田辺竹雲斎でめぐる竹工芸』展作品目録」2018年
斎と田辺竹雲斎でめぐる竹工芸』展作品目録」2018年
小林肇「新聞の外字から見えるもの」明治書院『日本語学』2016年6月号
芝野耕司編『増補改訂JIS漢字字典』日本規格協会、2002年
日本国語大辞典第二版編集委員会『日本国語大辞典第二版第十三巻』小学館、2002年
諸橋轍次『大漢和辞典 巻七 修訂第二版第五刷』大修館書店、1999年
≪おすすめ記事≫
・新聞漢字あれこれ34 2019年「今年の超1級漢字」 はこちら
・新聞漢字あれこれ35 エビちゃんを探せ! はこちら
≪著者紹介≫
小林肇(こばやし・はじめ)
日本経済新聞社 用語幹事
1966年東京都生まれ。金融機関に勤務後、1990年に校閲記者として日本経済新聞社に入社。編集局 記事審査部次長、人材教育事業局 研修・解説委員などを経て2019年から現職。日本新聞協会新聞用語懇談会委員。漢検漢字教育サポーター。漢字教育士。 著書などに『謎だらけの日本語』『日本語ふしぎ探検』(共著、日経プレミアシリーズ)、『文章と文体』(共著、朝倉書店)、『日本語大事典』(項目執筆、朝倉書店)、『大辞林 第四版』(編集協力、三省堂)、『加山雄三全仕事』(共著、ぴあ)、『函館オーシャンを追って』(長門出版社)がある。2019年9月から三省堂辞書ウェブサイトで『ニュースを読む 新四字熟語辞典』を連載。
≪記事画像≫
トップ画像:pine / PIXTA(ピクスタ)
記事中画像 : 「線の造形、線の空間 飯塚琅![]() 斎と田辺竹雲斎でめぐる竹工芸」展の入場券の半券
斎と田辺竹雲斎でめぐる竹工芸」展の入場券の半券